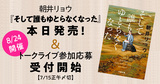幕末を舞台に若き殿様の活躍を描く『大名倒産』。「江戸もいまも人間は変わらない」と語る浅田氏に、この小説にこめた思いを聞いた。

──新作『大名倒産』は、幕末の江戸時代を舞台に財政赤字に苦悩する若き殿様の活躍を描く時代小説です。小説の冒頭で、ご自身が幼い頃に見かけた「江戸時代生まれの老人」の話が出てきます。この思い出を踏まえて、「これから始まる話はさほどの昔話ではない」と書かれたことで、物語がぐっと身近に感じられます。
浅田 幸か不幸か明治維新というコペルニクス的な社会転換があり、その後、天災や戦争を挟んだことで江戸を遠い昔ととらえがちです。まるで江戸と明治の間には鉄の壁があるように思っているひとも多いでしょう。しかし、自分が子供のころを思い出せば、江戸時代生まれの人が周囲から一目置かれていたり、世界最長寿の男性と言われた泉重千代さんなどは慶応元年生まれとされていた。大政奉還は1867年のこと。いまからわずか150年前です。そんな昔のことではないし、人間だってそんなに変わっているはずがない。
新選組三部作(『壬生義士伝』『輪違屋糸里』『一刀斎夢録』)を刊行した後、新選組の子孫の方々と高幡不動でお参りをしたんです。子孫の方が一堂に集まっていただきましたが、これが驚くことに、誰の子孫だか見ただけで分かるんですよ。
──「あなたは近藤勇の親戚!」「あなたは土方歳三」と分かるのですか?
浅田 そう。4代たっているけど、人間の遺伝子ってすごいもんだと思いました。そう考えると、『大名倒産』は、いまの企業小説と置き換えてもらって、何の問題もありません。
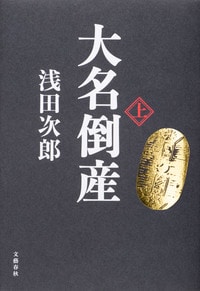
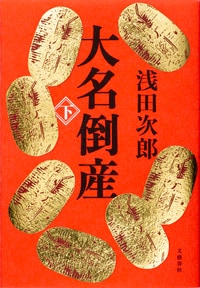
──藩は企業で、お殿様は社長ですね。
浅田 そう。その社長が代わったときに取り巻きがどのように動いていくかなんて、この小説を読めばよく分かる。幕末になると老中がコロコロ代わるけど、企業だって役員が次々に代わるのは危険信号でしょ。特に経理の役員が辞めた時は本当に危険だね。
──自分の仕事先を思い出して、ドキッとしている方も多いかもしれませんね。
浅田 江戸時代は260年間も平和を維持できた、一度も大きな戦争が起きなかったという稀有な時代です。僕は平和を愛する者ですが、ただ、災害に見舞われたり戦争をするようになれば、人々は因習にとらわれるよりも物事を見直すよう迫られます。それが、時代を進化させることもある。しかし、この時代はなーんにも起きない。そうなると一番怖いのは、何も変える必要がない、変えてはならないという考えに固執し始めること。それで、理由もわからぬ「繁文縟礼(はんぶんじょくれい)」が積み重なっていく。
──これは、一般企業にも言えることです。
浅田 幕末の資料を読むと、何のためにやっているのか分からない「慣例」が本当に多い。
──浅田さんにとっては『黒書院の六兵衛』(2013年刊 現在は文春文庫)以来の時代小説となります。
浅田 僕の時代小説の大きなテーマのひとつに「お殿様小説」というものがあります。戦国武将小説はたくさんあるが、とりわけ平和な江戸になってからのお殿様小説は少ない。書く側も小説にならないと思っているんでしょう。しかしですよ、お殿様とはいえ、一人一人の人生があり、個性があるわけで、当然面白い話がたくさんあったはずです。「大名も殿様も人間である」という部分を自分なりに掘り下げたいと思ってきた。そういう意味で『大名倒産』は僕が書きたかったことに真正面から取り組んでいます。
──今回の主人公、越後松平丹生山三万石の藩主・松平和泉守信房(小四郎)は弱冠21歳。庶子の四男で、まさか自分が家督を継ぐなど考えてもいなかったのに、ひょんなことから御家の跡を襲ぐことになります。実は、その背景には父親の企みがあるわけですが、そうとは知らずにお殿様となった小四郎は、借金25万両、利息だけで年3万両というとんでもない財政赤字と懸命に取り組んでいく。この小四郎の真面目さというか、健気さが小説のひとつの読みどころです。
浅田 小四郎の真面目な生き方は僕の青春時代の理想像なんですよ。僕は、20歳前後のころは真面目じゃなかったからなぁ(笑)。悪いことをいっぱいしつつも、「真面目にならなきゃ」ってずうっと思ってきた。人生に悔いはないが、唯一がそれ。
──真面目に生きていれば、と?
浅田 そう。根は真面目なんだけどなぁ。だから、主人公には理想を込めたかった。
このインタビューの完全版は2019年12月21日発売のオール讀物1月号に掲載されます。
-
『妖の絆』誉田哲也・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2025/07/11~2025/07/18 賞品 『妖の絆』誉田哲也・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。