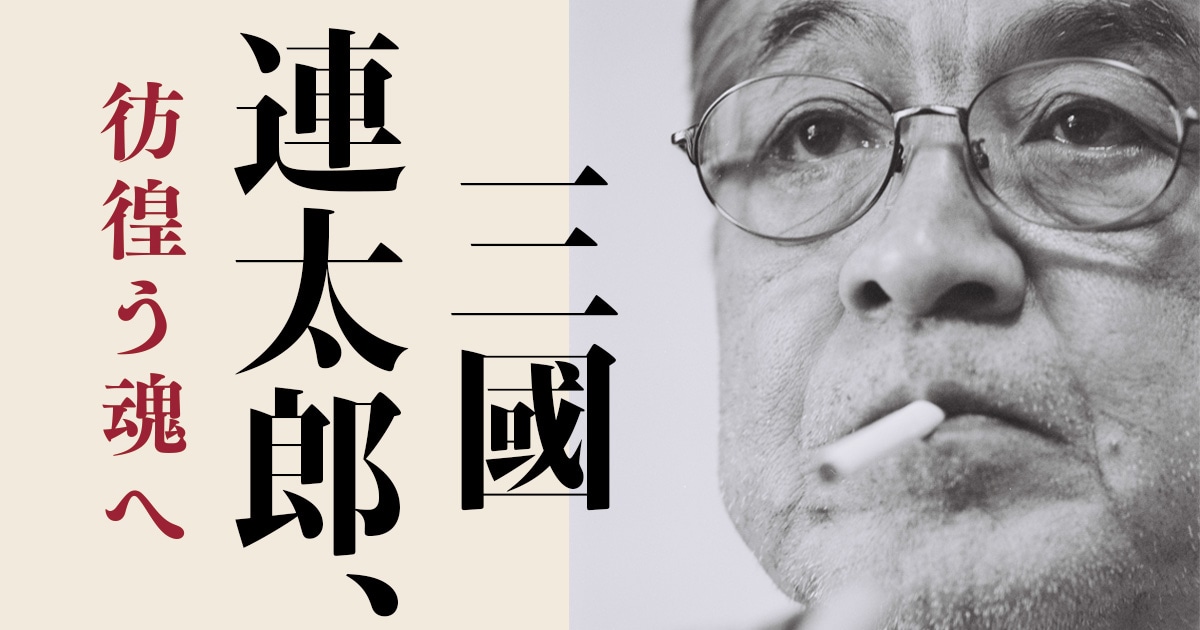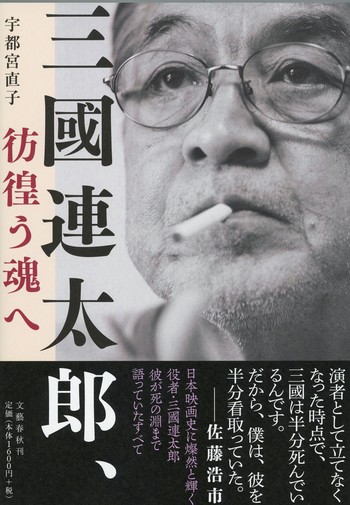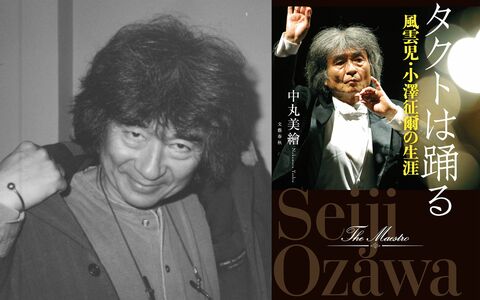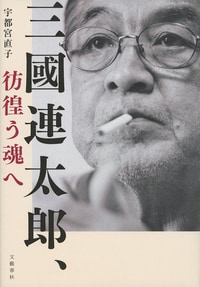
三國連太郎さんと出会ったのは、三十年くらい前だ。その頃、私は仕事を始めたばかりだった。人生でいちばん幸せだった頃かもしれない。気力に満ちていたし、健やかだった。
ある日、私は都内の撮影所にいた。広くて暗い、倉庫のようなところだ。そこで、三國さんと会った。正確に言えば、見かけた。三國さんは大スターで、とても駆け出しのライターが近づける存在ではなかった。
親しくなったきっかけは、三國夫人だ。隅で、メモを取る私に声を掛けてくれたのである。
「あなた、よく来ているけれど、何しに来ているの?」
夫人は気さくな人で、まるで旧知の間柄のような雰囲気で話をした。彼女がもし、そういう人でなかったら、私が三國さんと知り合うことはなかっただろう。
私は普段、いろんな人に会い、さまざまな場所に行く。だが、ほとんどの場合、その場以上のつきあいにはならない。そう心がけているせいもあるが、かなりの人見知りだからだ。ともあれ、それを機に、私は夫人と挨拶を交わすようになり、一緒に撮影の様子を見るようになった。
三國さんと初めて言葉を交わしたのは、撮影所の中にある食堂だった。三國さんはお化けのようなメイクをしていた。
とくに人見知りでない人でも、「三國連太郎」との食事は緊張するのではないか。私はひどく無口になった。言えたのは「こんにちは。初めまして」くらいだ。
気を遣ってくれたのか、三國さんが言った。
「この顔はメイクをしていまして、普段はこうではありません」
「それはそうよねえ」
夫人は笑ったが、私は笑えなかった。苦しまぎれに、咳をした。
あとになって聞いた話だが、このとき三國さんは、私のことを「ずいぶん変わった人だ」と思っていたらしい。
別れ際に勇気を振り絞って、ノートにサインを書いてもらった。三國さんはさらさらと名前を書き、その横に大きく「夢」と添えた。一期一会のつもりだった。でも、それから、私は折に触れ、三國夫妻と会うようになった。三國さんが八十代になり、病に倒れてからも、だ。
本文に綴ったように、三國さんとはたくさん話をした。当初は書籍にするつもりはなかったので、取材という意味ではだいぶ遅れてしまったという思いがある。助けてくれたのは、歳月にほかならない。
私は、三國連太郎という「役者」に徹底的に魅せられていた。その生き様を尊敬していた。プライベートでは、父親のような存在だった。三國さんからは、「あなたは家族のようなもの」と言ってもらっていた。
命や死について、よく話した。それらはまったくタブーではなかった。三國さんは、むしろ好んでそういう話をした。話しながら、笑うこともあった。
一方、三國さんは老いを恐れていた。死ではなく、演じられなくなるのを怖がっていた。
「最後まで役者でいたいと思っています。それを奪われることが嫌です。ものすごい恐怖を覚えます。演じられない僕に、生きる価値はありませんから」
静かな口調の中には、独特の激しさがあった。とてつもなく熱かった。
最後に三國さんに会ったのは、二〇一二年の初秋だった。その後、私はがんに罹患し、入院、手術をした。長い治療が始まり、そこからは訪ねられなくなった。偲ぶ会等の案内も頂戴したが、当時は歩行が難しく出席できなかった。
ただ、私に心残りはない。三國さんが入院している間に、自分なりの別れを済ませていた。掛けてもらった言葉はしっかり覚えている。私は生涯、それらを忘れないだろう。
撮影所の食堂でもらったサインは、今も手元にある。「夢」は色褪せず、傍らにあるのだ。

(あとがきより)