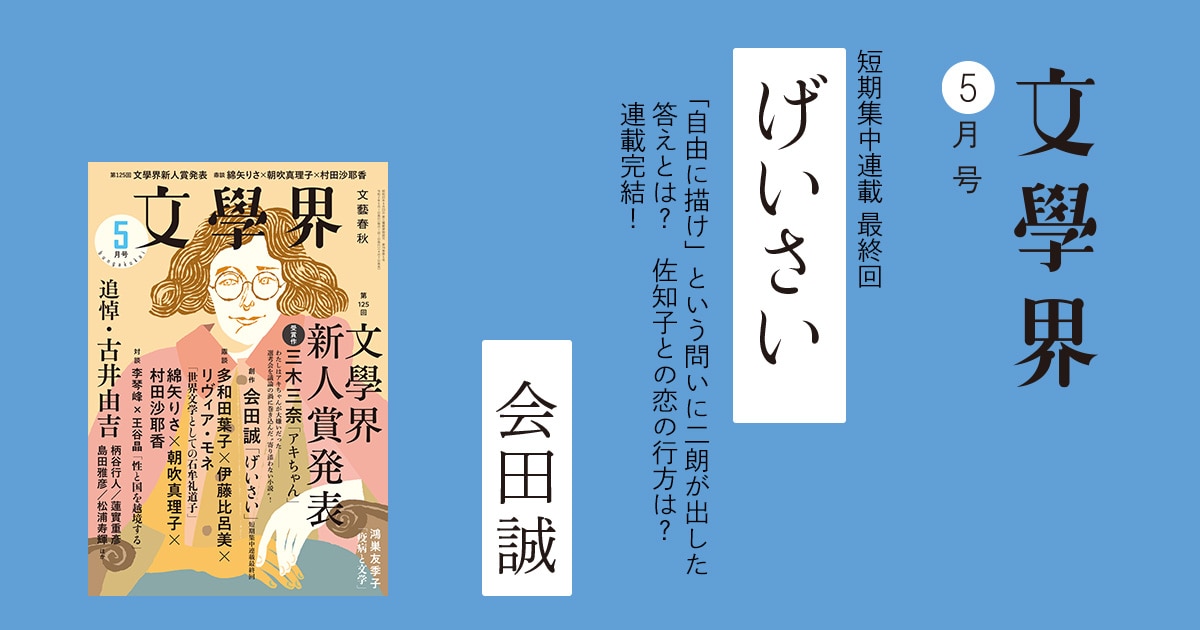「こーいうふうにさあ……好きなことだけして、なんとなくダラーっと生きていきたいんだよなあ……ずうっと……」
そういった意味のことを、シゲさんはその後1時間あまりの間に、言い方を変えて何度も繰り返した。よほど彼にとって大事な主張だったのだろう。
「アンタいつまでそんなバカみたいなこと言ってんの。現実を見て」
「ほら、この若い人たちの教育上、良くないから」
「みんなもこんな風になっちゃダメよー」
シノさんの口調はダメ亭主を諭すしっかり者の女房そのままで、二人が付き合ってることは――それも長い期間――高村に訊くまでもなく察せられた。
バッタさんはあまり喋らない人だったが、それは気難しさとは逆の、マイペースさゆえだった。表情はそれ以外できないんじゃないかと疑うくらい、つねに楽しそうで――つねに眉毛の両端が下がっていた。縁側で猫と日向ぼっこしてる御隠居の風情が、まだせいぜい二十代前半にしてすでにあった。
三人はずっと他愛もない冗談まじりの話を続けていたのだろう――高村による一通りの紹介が終わると、特にこちらに気を遣うこともなく、またそれを再開させたようだった。今日の自分たちのステージがいかに最高だったかという話。ここにいない誰かが女に捨てられた話。どこかの模擬店の焼き鳥が生焼けだった話……。それぞれの話は面白く、とりわけアメ横の売り子のように声がしゃがれたシゲさんのお喋りには、どこか芸人めいた華があった。大半の話は、ここに記しておく価値のある内容ではなかったが。
「な、さっきの模擬店の雰囲気とぜんぜん違うだろ?」
高村は僕に耳打ちした。
「オレ、あの油絵科の雰囲気、苦手なんだ。いやハッキリ言って、嫌いだね。あの延々と続く不毛な議論」