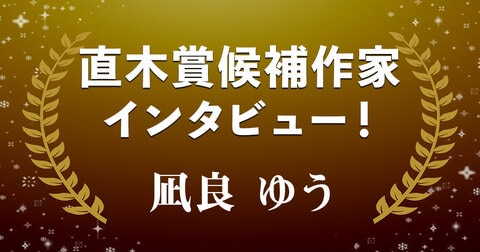名づけえぬ関係性に光を

家族でも、恋人でも、友人でもないふたりが、思いがけない出会いと別れを経験したのち、十数年の時をへて再会し、惹かれあう(そしてその再会を世間は大バッシングする)――という、およそ類例のない男女の関係性を描いて大きな反響を呼んだのが、二〇二〇年本屋大賞に輝いた『流浪の月』だ。
名前のない、まったく新しい人間関係を小説によって描き出した凪良ゆうさんは、最新作『わたしの美しい庭』でも、いまだ名づけられたことのない、“疑似家族”とも呼べぬような、ゆるやかな共同体に光を当てている。
舞台は五階建てのマンション。最上階に住むオーナー兼、屋上に建つ縁切り神社の宮司でもある統理(とうり)は、別れた亡妻が別の男との間に遺した女児・百音(もね)を引き取って、単身で育てている。
彼らの部屋に毎朝、朝食をつくりにやってくるのが隣家の青年・路有(ろう)で、そこに同じマンション三階に住む三十九歳独身の医療事務職・桃子、さらに桃子の元彼の弟で、現在、鬱で休職中の基(もとい)までが加わって、なんとも不思議な生活空間が築かれていくのだ。
「テーマが一貫してると言われることもあるんですけど、そのつど私の中に存在するものを掘って探りながら書いているだけで、自分では意識してないんです。だから、着想のきっかけを尋ねられても、うまく答えられなくて。
ただ、私自身、縁の薄い家族関係の中で育ったことは多少、影響してるかなと思います。幼い頃から知らない人がよく家に出入りしていましたし、わりと早い時期に親と離れて暮らすようになったせいか、いまだに“正しい親子関係”がわからない。“普通の家族”のディテールを描けないんです。それで自然と、『普通』や『つながり』になじめない人たちの姿を描いてしまうのかもしれないです」
世間から「変わってる」と見られてしまう統理ら義父娘。ゲイの恋人との失恋に傷つく路有のほか、桃子も、基もそれぞれ屈託を抱えているが、彼らのしがらみを断ってくれるのが、マンション屋上の縁切り神社だ。百音たちが形代に「緑を切りたいもの」を記し、お祓い箱にストンと落とすシーンの清々しさたるや、読んでいる我々の屈託も払い落としてくれるかのよう。
二十代の頃、有名な縁切り神社のすぐ近所に住んでいたという凪良さん。
「みんな、いろんなものに踏ん切りをつけるきっかけを探してるんじゃないでしょうか。いまは『絆を大事に』と言われる時代ですけど、『絆』がつらいなら無理しなくていい。断ち切ることで、新たな一歩を踏み出せる人もいると思うんです」
なぎらゆう 二〇〇六年「小説花丸」掲載の『恋するエゴイスト』でデビュー。昨年刊行された『流浪の月』で二〇二〇年本屋大賞を受賞。著作に『神さまのビオトープ』など