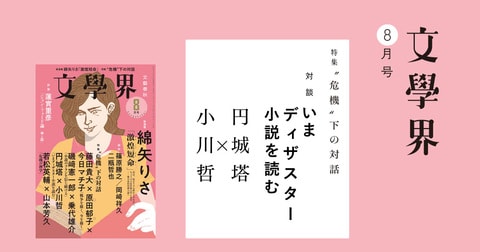では、『ドノバン珊瑚礁』で、室内でいっせいに開かれる雨傘という異様なオブジェの群れを目にしたわたくしたちは、ジョン・フォードのほかの作品で、戸外にたたずむ男女が、雨を避けようとして傘をさしている情景など思い浮かべることができるだろうか。おそらく、そうしたことをさらりとやってのけうるものなど、この世界にはほとんど存在していまいと断言できる。まず、フォードにおける傘といえば、むしろ日傘だからである。すでに『アイアン・ホース』(The Iron Horse, 1924)の開通式の場面で、御婦人たちのさしている数えきれないほどの日傘を誰もが記憶していることだろうから、『ドノバン珊瑚礁』のエリザベス・アーレン Elizabeth Allen がいつも手離さずにいる真紅の日傘のことをすぐさま思い浮かべるだろうし、この島の総領事であるシーザー・ロメロ Cesar Romero につきそっている東洋系の執事もまた、紅いろの日傘――ときに日本の番傘のようにもみえる――を手離すことがない。
日傘とは異なり、フォードにおける雨傘と聞いてかろうじて想起しうるのは、『大空の闘士』(Air Mail, 1932)のおかしな航空整備士スリム・サマーヴィル Slim Summerville と、『最後の歓呼』(The Last Hurrah, 1958)の老婆ジェーン・ダーウェル Jane Darwell ぐらいだろうか。この航空整備士がさしている雨傘がどのような運命をたどるかは後に見てみることとし、『最後の歓呼』で葬儀に参列する老婆が握っていた男ものとしか思えない長い傘に触れておくにとどめる。それは、隣の若い新聞記者のジェフリー・ハンター Jeffrey Hunter をからかいぎみに、その腹のあたりを二度ほど豪快に小突くための武器でしかなく、雨を避けるというそれ本来の用途などこれっぽちも考慮されてはいない。にもかかわらず、フォードの映画では、しばしば豪雨が画面を思いきり濡らしているという事実を否定するのはむつかしいのである。