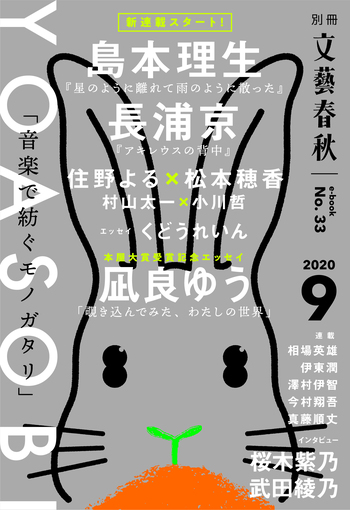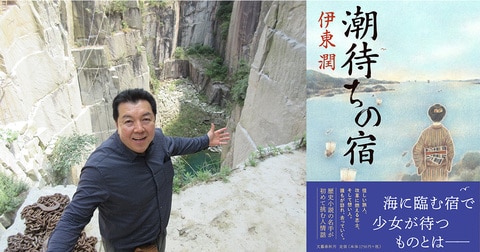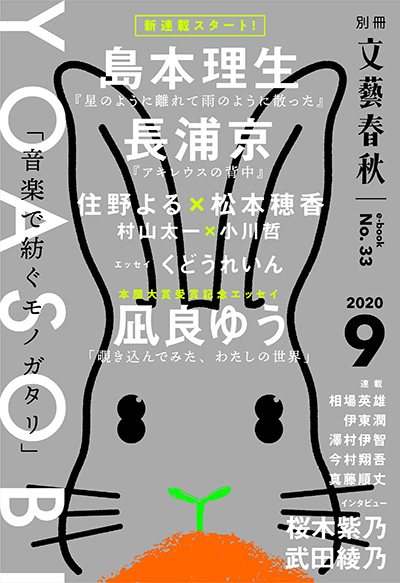
政子は涙を流しながら心中懇願した。だが若くて体力も人に勝る頼家は、なかなか死んでくれない。鴆毒は、その場で殺すのなら大量に仕込めばよいだけだ。だが後で効くようにするには、その量をどうするかが極めて難しい。
「ああ、く、ぐわー!」
地獄の邪鬼もかくあらんという声を上げ、頼家が気を失った。
看護に当たっていた者たちは、血と嘔吐物にまみれながら肩で息をしている。それは政子も同じだった。
――ああ、可哀想な万寿。
いまだ唇をわななかせている頼家の額に触れると、凄まじい熱を発していた。もちろん汗もひどくかいている。
医家が言う。
「汗がこれほど出ているということは、よき兆しです」
茫然としていた政子は、その言葉でわれに返り、義時を見た。
すでに広縁から庭に下りていた義時は、拝跪しつつ医家の話を聞いている。
政子が医家に問う。
「何でこうなったのですか」
「さて、単なる食あたりで、これほど苦しむことはありません」
医家には、毒の類が原因だと分かるのだろう。だが医家は、それをはっきり口にするのを憚ったようだ。
政子の視線に気づいたのか、義時と目が合った。だが義時は咎めるように政子をにらみつけただけで、再び顔を伏せ加減にして中空を見つめた。
――何を考えているのか。
もし頼家が死なずに正気を取り戻せば、この急病の原因を究明し始めるだろう。その時、頼家は真っ先に義時に疑いの目を向けるはずだ。
――まず疑われるのは小四郎、続いて父上、そして私。
そこまで考えた時、交代の女房たちがやってきた。先頭に立つのは妹の阿波局だ。
「姉上、後はお任せ下さい」
一瞬、その凄惨な有様に啞然としたものの、阿波局が落ち着いた口調で言った。
「分かりました。この場はお任せします」
政子は大きなため息をつくと、奥の間に引き取った。
湯浴みをして着替えた政子が、再び頼家の許に向かおうとした時だった。
「姉上」と呼ぶ声が庭から聞こえた。日もすっかり暮れていたため、義時が庭に控えているのに気づかなかったのだ。
「後ほど、名越にてお待ち申し上げております」
庭燎に半身を照らされていた義時は、それだけ言うと、黒い闇の中に溶け込んでいった。
翌日、頼家は御所に移されたが、その苦しみは断続的に続き、地獄の底から聞こえてくるかのごとき呻き声は、御所の外にまで聞こえたという。