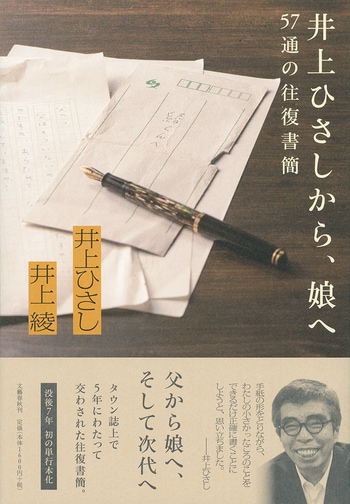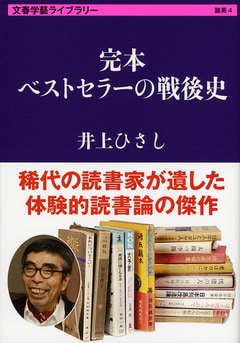なかでも母を悩ませたのは、組員たちの雑談でした。街の遊廓の女たちの噂話から工事現場近くの女学校の生徒さんの品定めまで、ヒマがあれば女の話ばかり。母は子どもをこんなところへ置いていてはいけないと思った。また会計のおじさんがお金を持ち逃げして労貸の支払いにも苦労していた……。
天国のようなという幻想はすぐに消えました。その日のうちに、わたしたちは児童相談所というところへ連れて行かれていろんなテストを受けさせられたのですが、そのとき相談員の先生がこういったのです。
「きみたちのところは戦災孤児専用の保護施設で、みんなみなし児なんだ。兄弟でくっついていると、みんなから妬まれるかもしれない。所内ではできるだけ赤の他人のふりをしていた方がいいだろうね」
児童相談員の予言は当たりました。もちろん楽しいことは山ほどありましたが、しかし肉親が生きているというだけで、ことごとくつらくあたられる。これには閉口して、こんなことなら一関の飯場の方がいいやと思いはじめたころ、母が面会にやってきました。カナダ人の院長先生から許可をもらった母は、わたしたちを仙台市内に連れ出して、まず映画館へ行きました。
「あんたたちは映画が大好きだったわね。今日は二本も三本も映画を見ましょう」
「ぼくらと一緒にいるのは、両親を亡くした子たちばかりなんだよ。そんなところへのこのこやってくるなんて、どうかしている。映画なんかどうでもいい」
母の顔を見て体がはち切れそうになるくらいうれしかったのに、わたしの口から飛び出すのは、恨みごとばかりでした。
「ご馳走をたべようか。ライスカレーがいいかな、それともチャーシューメンがいいかな」
「食べたくない」
「しばら東一番丁を歩こうか」
「歩きたくない」
「喫茶店でアイスクリームを食べよう」
「いやだ」
「じゃあ、どうしたいの」
「なにもしたくない」
こうしてわたしたち母子三人は仙台の盛り場で、ただうろうろしていました。そしてそのうちに、母が静かに泣きだしたのです。
すぐにでも子どもを引き取って帰りたいのに、さまざまな事情がそれを許さない。子どもにしてもその事情を察していて一緒に一関に帰りたいとは言えない。そういったことが団子になって、わたしたちを立往生させていたのでしょうが、なによりもわたしは、自分のなかに根深くひねくれた心が潜んでいることに気づいてびっくりしていました。
わたしの知るかぎり、母が涙を流したのはあのとき一度だけでした。母の涙の引き金を引いた中学三年のこのわたしを、わたしはまだ許していません。
『井上ひさしから、娘へ――57通の往復書簡』(文藝春秋刊)より
吉里吉里忌公式サイト
https://www.kirikiriki.inouehisashi.jp/