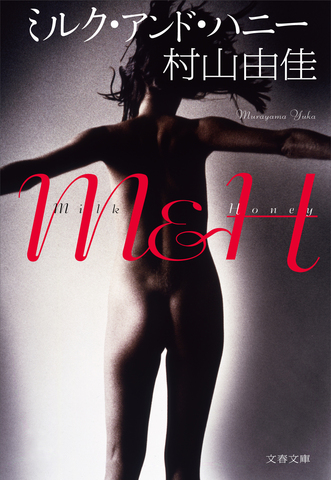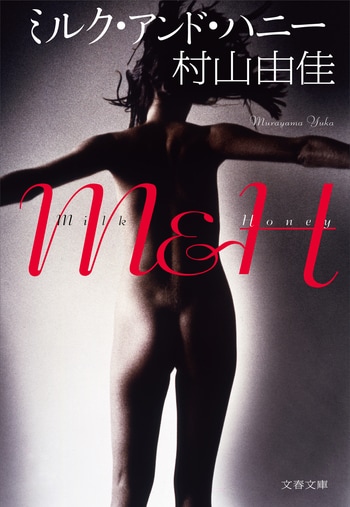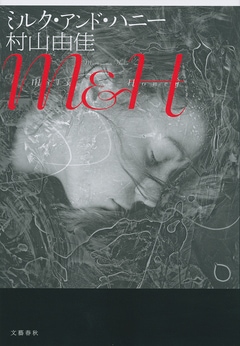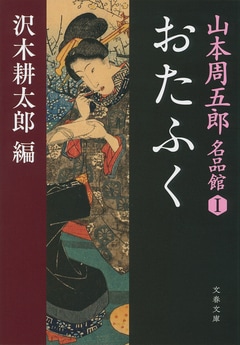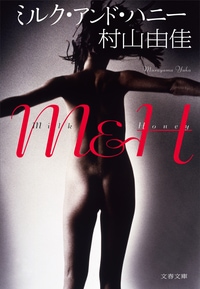
今回の物語は、恋人大林との暮らしから始まる。前作で奈津の求めるものを与え、読者には理想的な相手として映った大林が、前作から一年ほどでセックスレスになり、今の彼女をより寂しくさせる相手となっていることを知らされる幕開けは衝撃的だった。この部分を読んでしまったら、もう続きを読まないわけにはいかない。
「自分はヒモである」「風俗通いをやめるつもりはない」と堂々と宣言する大林と暮らしながら、奈津はかつての自分を突き放した志澤や、その傷を癒してくれた岩井と再び逢う。しかし、そこにはもはや以前のような心酔や、切迫した癒しを求める気持ちはない。満たされぬ心を抱えたまま、奈津は、女性限定の〈ボディエステ〉や、性的に開放されたハプニング・バーなど新たな世界に踏み出していく。その傍らで、性欲に縛られる自分を脱したいと、大林と結婚し、住まいを移り、自分の人生に対して真摯であろうとあがく。
この小説を凄いと思うのは、小説を小説として読む醍醐味と喜びに満ちていることだ。その後にどんな運命が待ち構えていようと、奈津の刹那刹那の感情から、彼女が必死にあがいて、最善の道を探そうとしていることが伝わる。その一刻一刻の感情や状況に嘘が一切なく、たとえば、大林への慈愛と憤怒の両方が、矛盾なくひとつの場面に存在する。小説だからこそ生まれる物語への没入感とドライブ感がそれを成立させるのだ。村山由佳の小説を読む楽しみがここにある。
相手に恋し、心酔している時には、奈津がそうであるように、読者もまたその男に心酔できるように徹底して言葉も感情も描写される。何故ならそれが恋だから。たとえ、その後ろにまやかしの要素が見え隠れしようと、読者にそれを明かすのは、男が目の前にいない、奈津と女友達、あるいは心を許した岩井との会話の中か、時が過ぎ相手から気持ちが完全に離れてからなのだ。だから、まったく先が見えない物語を紡いで見せながら、同時に、読者に想像させる。新たに現れたこの男は、果たして奈津に何を見せてくれるのか。見て見ぬふりをしてきた不穏な予感に運命がはまり込む時、ああ――と深く息を吐きながら、読者はどこかでああ、そうなると思っていた、とも同時に思う。自分が著者の術中にいたことに気づく。
なぜ、そんなことが可能なのか。それは、相手との恋に心底まいっていてさえ、主人公としての奈津がどこか、常に冷静に自分自身を俯瞰して見ているからだろう。
それは、作中で奈津が「やってしまった」と思うような種類のことであっても。
村山さんの描く奈津の物語がこんなにも魅力的で、読む手を止められぬほどおもしろいのは、奈津が自分自身を選択し、結果を引き受ける主人公であるからだ。激しい展開は、巻き込まれたものではなく、彼女自身が自分の心の求めるものに、繊細に丁寧に、力強くアクセスした先にある。この「繊細に丁寧に」というのが大事なポイントで、彼女は大胆だが、決して闇雲でない。自分自身が何を求めるのか、非常に自覚的に見据え、それがたとえ自分自身の内から発する欲望であっても慎重に見極めようとする。だから、「やってしまった」の前に、何度も「やはりこういうことになるのだな」と小さく納得を繰り返し、踏み込む時には、あらかじめ、「そうなってもいい」覚悟を決めている。その上でいつも、あらゆることに関して一線を超える。