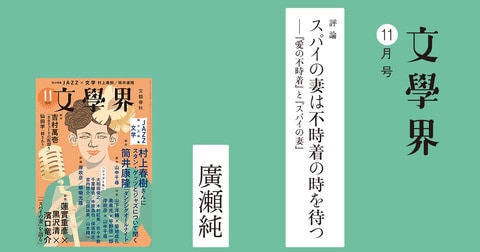1
葵はギターケースを背負い、山手線に揺られて新宿駅へ向かっていた。新宿のエルという会場でライブがある。葵のバンドにとって初のワンマンだ。事前にメジャーレーベルの社員が、視察にくることを聞かされていた。つまりは実質的なオーディションライブだ。審査する人間が良しと見なせば契約になるし、否と見なせばそれまでだ。審査される音楽なんてクソみたいだ、葵は思いつつも、メジャーとの契約は余りに魅力的だった。その矛盾した感情から逃れるように、イヤフォンを耳にして音楽を再生する。
“Girls Just Want to Have Fun ―― Cyndi Lauper”
俺が音楽を愛したのはいつだろう――、ヒステリックでチャーミングなシンディの歌声に耳を傾けつつ、葵は思う。小学校高学年でビリー・ジョエルを聴いたときだろうか、中学でツェッペリンを聴いたときだろうか、高校でニルヴァーナを聴いたときだろうか――、あるいは幼稚園児のとき、市内子供のうたコンクールで“星の家族”を唄い、銀賞を貰ったときだろうか。
あのコンクールに出るとき、祖母がわざわざ田舎から電車を乗り継いでやってきた。コンクールの前日に、葵は祖母の前で、予行練習をした。葵が唄う歌を、祖母は目を細め、目尻に皺を寄せて、恵比寿様の顔で聴いていた。歌は人を笑顔にできるのだと、思った。もしかしたら、俺が音楽を愛したのは、あのとき祖母の笑顔を見たからかもしれない。その祖母は、数か月前に肺炎をこじらせて他界していた。祖母をライブに誘ったことはない。自分がやっている音楽は、祖母を笑顔にすることはない。
葵のバンドは、九十年代にアメリカを中心に流行したオルタナティヴに属する音楽だった。インデペンデントから発生したこの音楽は、あのシアトルのムーヴメントに後押しされ、一気にメジャーシーンへ登場した。マッドハニー、シルヴァーチェアー、スクリーミング・トゥリーズ――、そうしたバンドが再評価され始め、日本のアンダーグラウンド・シーンで、小さなブームが起きていた。葵のバンド、Thursday Night Music Clubは、このシーンである程度の成功を収めていた。葵の楽曲が、若い世代の支持を得たのだ。
この続きは、「文學界」2月号に全文掲載されています。