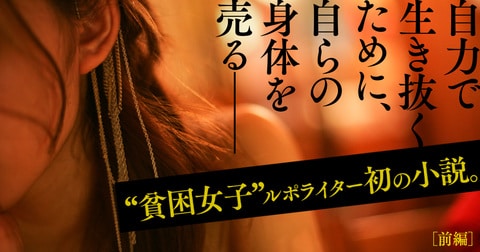現在、世界中の人々の関心の的はコロナ禍だろう。無責任で一貫性のない政府の対応に国民は怒りを通り越し、あきれ果てているのに、市民のそんな気持ちは政府に届かない。
それはなぜか、その問題を解決するにはどうすればいいのか。本書にはそのヒントが詰め込まれている。
8章立ての各章は、どれも新書一冊分の読み応えがある。「出生前診断」「障害者施設建設問題」「社会的入院」「ゲノム編集」「受精卵診断」「相模原殺傷事件」「コロナ禍」とテーマはバラエティに富んで多様な問題を取り上げているがその中心には、一本の太い背骨が走っている。
それは「これは本当に他人事なのだろうか」という視点である。
たとえば、障害者施設建設時の地域住民との軋轢に焦点を当てた章では、建設拒否の地元住民の、自己中心的な主張が赤裸々に写し取られている。身勝手な言説に眉を顰めた次の瞬間、自分がここにいたら似た発言をしたかもしれないという不安に囚われる。
差別される側の言葉が切実であればあるほど、居心地の悪さは増大するのだ。
本書はそんな風に、ある種の不快さをもたらすが、その発生源をたどっていくと今日の日本社会の在りように行き着く。今の日本社会は経済効率を最優先した弱肉強食の社会なので、切り捨てられる弱者は往々にして少数派だ。
だが見落としがちだが、実は弱者と強者は、ほんのささいなことで簡単に入れ替わる。新自由主義経済を基盤にした現代社会では敗者復活が難しいので、格差は広がっていくばかりだ。だがそれは自分がかつて多数派だった時、少数派である弱者に対し目配りしなかったせいで起こる、しっぺ返しでもあるのだ。
「相模原殺傷事件」の章では、障害者を大量に殺害した犯人は、実は社会の歪みの体現者かもしれない、と自省する。その視点はともすればセンセーショナルな面に走りがちなジャーナリズムへも一石を投じる。
私たちは大なり小なり、あの大量殺人犯の心性を持ち合わせている。小さな問題に目を向けず座視し、事態を改善しようとしなかった点で、私たちはあの事件の加害者でもある。
そうした不穏な気付きは第7章で一気に変身する。健常者が障害者を差別し、障害者は少数者であるが故に、その辛苦は社会から黙殺されてきたが、コロナ禍では全ての市民が「不自由な存在」になったという気付きに呆然とさせられる。
確かにコロナ禍は手酷い災厄ではあるが、もしもその中に新しい芽吹きを見出せるのだとしたら、大いなる希望にもなるだろう。
いや、そのように考えるしか、この災厄を乗り越える道はないのだと思う。本書はそのような思考のパラダイム・シフトのヒントを与えてくれる。2021年必読の書である。
ちばのりかず/1976年、広島県出身。毎日新聞記者。英リーズ大学大学院地球環境学研究科修了。生命科学や医学などを長く取材。
かみひがしあさこ/東京都出身。毎日新聞記者。早稲田大学第一文学部を卒業、96年入社。障害福祉、精神医療などを取材。
かいどうたける/1961年、千葉県生まれ。医師、作家。2006年『チーム・バチスタの栄光』でデビュー。近著に『コロナ黙示録』。