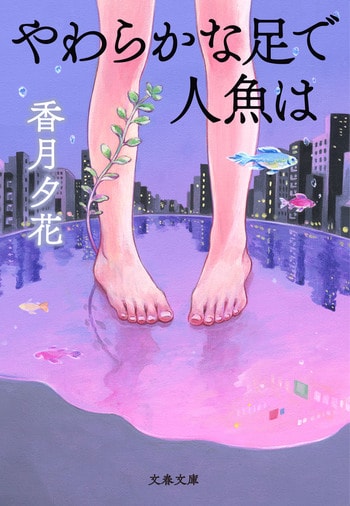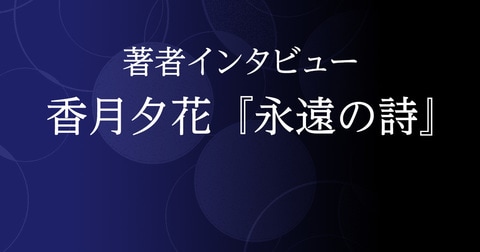墓石には黄色いペンキをかけられた。操縦していた娘の家の石塀にはスプレーで「人殺し」「親殺し」と書かれた。
来訪者の女性のつらい過去を知った、花屋を営む女性は思う。はじめに会った時、この来訪者を「完全無欠の幸福」な人間で自分たちを見下していると決めつけていた。「完璧に幸福な人間なんて、この世のどこを探したっているはずがないのに。心の薄皮を一枚はいだら、その下にどんな無残な傷が隠れているか分かったものじゃない」。
彼女が住む町は一年前、大雨で山が崩れ、何人もの人間が死んだ。彼女も、町もその悲しみのなかにあった。ヘリコプターの事故を起し世の批判にさらされた来訪者の悲しみはこの町のなかでこそはじめて癒された。「ここの人たちの中にいると、すごく安心するの」「みんな本当は悲しかったからなんだと思う。そんな顔を人に見せちゃいけないと思ってるから、誰も人前で泣いたりはしないけど、でも本当は、この町がまるごと悲しみの中につかってるんじゃないかって、そんな気がするの」。
この町では、悲しみが、人と人を優しく結びつけている。優しさとは文字通り、人の憂いを知ることに違いない。香月夕花は、この悲しみと優しさが溶け合う場所を探し続けている。
他者の悲しみを知る。それは、優しい人間にとっては時に大きな重荷となる。他者の悲しみに真剣に関わったら、自分の身が持たなくなってしまう。
「彼女の海に沈む」はその意味で、つらく痛ましい小説である。
中学校の教師が、教え子の中三の少女に振りまわされる。格差社会の現代ではありふれたことなのだろうが、現代の学校には必ず、不幸な家庭の子供がいる。両親の離婚、貧困、家庭内暴力……子供が幼なくして社会から疎外されてゆく。
香月夕花は彼ら見捨てられた子供の存在に心を痛める。『昨日壊れはじめた世界で』(新潮社、二〇二〇年)に描かれた、母親に捨てられた小さな女の子の悲しみは強く心に残っている。
「彼女の海に沈む」では、妻子のある中学教師が、家庭に恵まれず不登校になっている女生徒をなんとか立直らせたいと心を砕く。大勢いる生徒の一人一人に深く関わったら、自分のほうが壊れてしまうのに、この女生徒の「本当に助けてくれるの?」という訴えるような思いに引きずられ、「彼女の海」、つまり「他人の悲しみの海」に沈んでゆく。
他人の悲しみに敏感な人間の悲劇といえようか。それは、悲しみを書き続ける香月夕花のジレンマでもあろう。「悲しみ」という海は時に非情で、優しい人間も巻き込んでゆく。
「水に立つ人」は「オール讀物」の新人賞を受賞している。よくぞこの賞を受賞したと正直思う。というのは、分かりやすいストーリー性がないから。
小学校の先生をしている女性が、学校に出入りする、始業式や遠足などの行事を撮る写真館の若者に惹かれる。といってもよくある恋愛小説ではない。若者は山登りが好きで、ある時、山に空の写真を撮りに行って、そのまま帰らなくなった。若者はどこへ消えたのか。