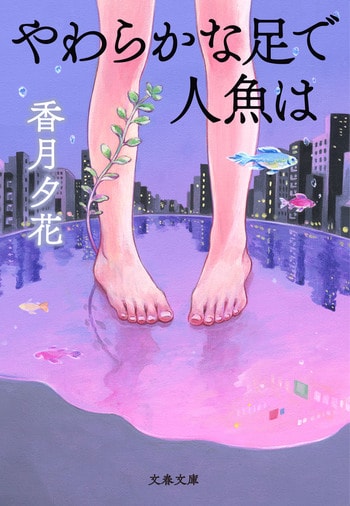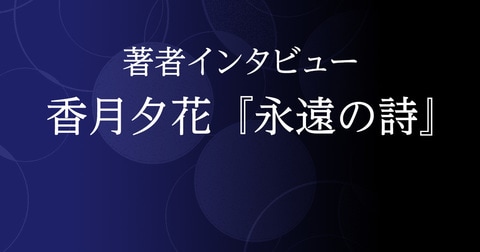この若者は、日本各地の教会の写真を撮るのが好きだった。若者を愛するようになった女性は、彼が残した写真を手がかりに、函館から五島列島まで、教会を訪ね歩く。
二人を結びつけているのは何だろう。
若者は「遠く」を見るのが好きだった。山を、さらにその向うの空を。彼女はそのことに惹かれたのではないか。そして彼が見た「遠く」を自分も見たいと思って旅に出た。
香月夕花の小説のいいところは、登場人物がある一瞬、「遠く」を見ることだ。現実から離れて遠くを見る。その瞬間、彼らは現実社会の息苦しさを忘れ、遠い世界と結びつく。傷ついた心が安らかになる。
「逃げてゆく緑の男」の若者は高層マンションの二十一階の部屋から都会の夜景を見る。「水風船の壊れる朝に」では家を売ることになる女性が祖母の墓のある墓地に行き、遠くの海を見やる。
ひとは遠くを見る時、素直になれる。「彼女の海に沈む」で不登校の女生徒が、自分を探しに来た先生に、以前、父親のトラックに乗っている時に見た海の話をする。
「あのとき、町並みの向こうに一瞬だけ、海が見えたの。金色の海。きれいなものをみんな溶かしたような海だった。あれからずっと、忘れられない。目をつぶると、今でもずっと見えてるような気がするの」
香月夕花の新しい作品『見えない星に耳を澄ませて』(角川書店、二〇二〇年)では、音楽療法の先生が星を見上げた。遠い星を見ると心が澄んでくる。安部公房の『第四間氷期』にこんな言葉がある。「星を見ながら、じっと宇宙の無限を考えたりしていると、ふっと涙があふれそうになったりする」。この涙は決して湿っていない。「宇宙の無限」という「遠く」(それを神と呼んでもいいかもしれない)に触れた時の粛然(しゅくぜん)とした涙だ。
「水に立つ人」では、カメラマンの若者が子供たちを撮影しようとして「なぜか懐かしそうに空を見上げた」。「懐かしそうに」とあるのが強く心に残る。この若者がいつも空を見上げているからなのか、あるいは、空の向うに彼は地球にやってくる前の故郷を見たのか(ここで、「たった今あの彩雲の辺りから降りてきました、とでも言うように」とあるのが、そう思わせる)。
香月夕花の主人公たちが見る「遠く」にはおそらく悲しみがあるに違いない。その悲しみは決して人を落込ませるものではなく、むしろ、生きることに疲れた人間たちを優しく包みこむ悲しみだろう。矛盾を承知でいえば「人の心を慰めてくれる悲しみ」。
最後の作品「やわらかな足で人魚は」はとりわけ素晴しい。母の許から裸足のままで逃げ出した幼ない子供の悲しみがまっすぐに伝わってくる。
この子供は八年後、施設で自分を守ろうとしてくれた「お兄ちゃん」の行方を追って旅に出る。この小説もつらい話でありながら、小さな救いがあるのは以前読んでもらった童話「人魚姫」を思い出しては、現実から離れようとしているからだろう。ここにも童話という「遠く」がある。
香月夕花の小説には確かに不幸な子供たちが登場する。だからといって香月夕花は決してそれを幼児虐待や育児放棄といった現実の言葉では語らない。むしろ海や風、花や木を語る言葉で描いてゆく。そのことで「遠く」からの声に耳をすませるように。