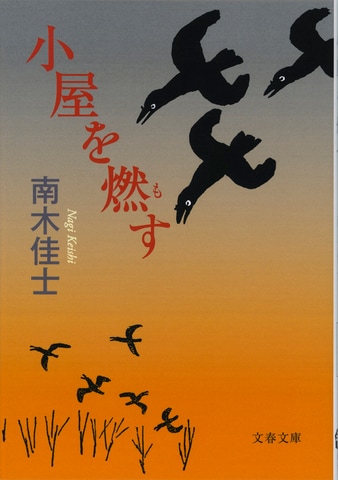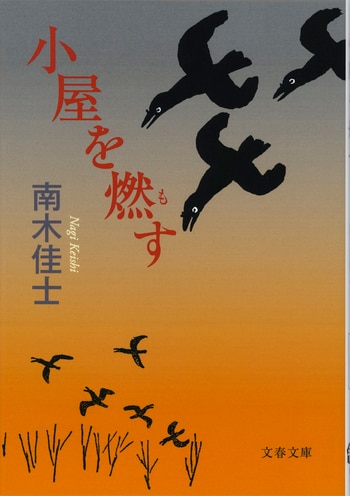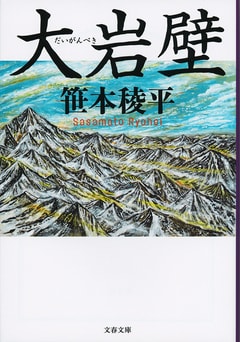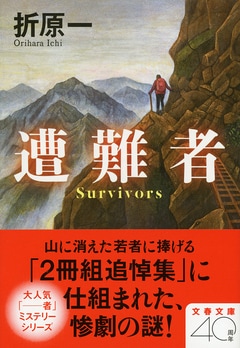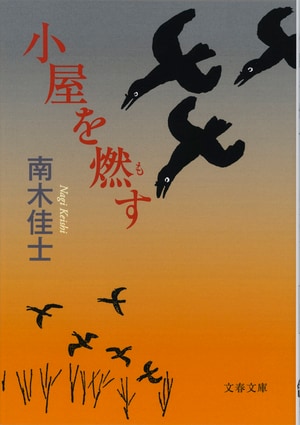
何年か前に埼玉県に住む母の教え子で、四年松組の級長だったという女性から村の本家宛に送られてきたコピーをいただき、その後しばらくして、これはあなたが持っているべきものだと思いますから、と勤務先の病院に送られてきた母の茶色く変色したはがきには青い茎と黄色い花のおおざっぱな菊のスケッチが描かれていました。全体の構成を考えずに書きたいことを書いてゆき、最後が詰まってしまう筆運びや、クレヨンを用いた絵の雑な描き方がおのれにそっくりで、身がざわつき、いたたまれなくなりました。父は絵も字もつまらないほど端正なひとでしたから。
肋膜炎と診断された幼児のわが身もともに入所していたらしいのですが、数枚のセピア色の写真で知るだけで記憶は欠けています。五十代半ばで肺の手術を受けた際、胸膜の癒着が強くて剥がすのに苦労した、と呼吸器外科医に言われました。手術を記録した動画データを提供してくれるとのことでしたが、忘れていたはずの、あるいは都合よく改編を重ねてきた過去の原資料と対面するのがおっくうで断りました。
母の死後数年で父は再婚しました。相手はかつて入院していた陸軍病院の看護婦でした。母と結婚する以前も、もしかしたら以降も付き合っていたのではないか、との祖母の疑念はそのまま孫に伝えられ、共有されました。
父は鉄鉱山の電気技師兼事務職で、家から離れた鉱山社宅で新たな妻と暮らしていました。そこに子供たちを引き取りたい、との親として当然の申し出をしたのですが、祖母は頑強に拒否し、泣いて嫌がる者を連れてってもうまくいくはずがあるめえ、との彼女のことばに守られて、掘りごたつに首を突っ込んで泣いていた記憶はたしかにありますが、これも改編されたものです、きっと。
鉱山が閉山になると、父と継母は東京郊外にある鉱山会社の社宅に移りました。中学二年になる春、東京に来ないか、との父の誘いにふわっと乗りました。祖母は悲しげな顔を見せ、ここで勉強して役場に入りゃあいい、と言ってくれましたが、一生をこの狭い谷間で暮らすのはなんとしても耐えられませんでした。山の向こうにある世界を見てみたかったのでしょう。
なじめぬ継母との暮らしはよく想い出せません。夜勤帰りで眠っている彼女を起こさぬよう、階段を静かに昇ったり……。
夜、社宅近くの早稲田大学のグラウンドに忍び込んで四百メートルトラックを全力で走っていたこと。途中入部のサッカー部では足が速いだけですぐレギュラーになれましたが、からだが固く、フェイントが下手だったゆえスポーツでは一流になれない現実が身にしみたこと。父や母に顔を合わせるのが苦痛だったから自室にこもって予習、復習をしていたら学校の成績がよくなり、三年生の三者面談の際に付き添ってきた父が、示された進学可能先の都立高校が学区のトップ校であるのに驚いていたこと。
高校では旺文社の「高一時代」の巻末にある文芸欄の短文に二回応募し、串田孫一選で一席と二席になったことがあります。賞品として安っぽい万年筆が贈られてきました。おのれの書いたものが活字になった初体験でしたが、日常の風景を切り取り、手持ちのことばで表現する行為がそれなりに認められてしまうと、なんだか、これからの人生を書くために生きてしまいそうで恐ろしくなり、その後は書くのをやめました。地に足をつけて生きたことを書くのでなければ文章なんて書く意味はない。祖母の自給自足に近い暮らしのなかで培われ、高校時代に定まったこの軸だけはいまに至るまでぶれていません。だからどうだというわけでもありませんが。