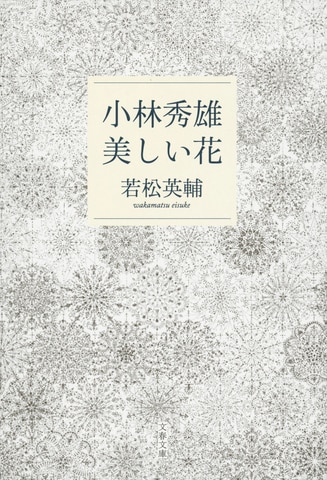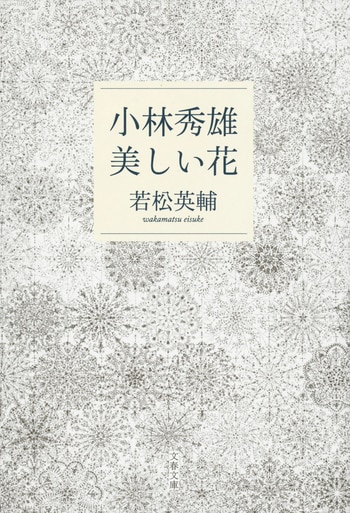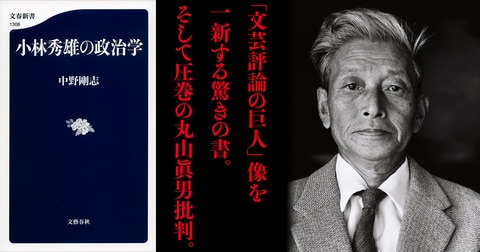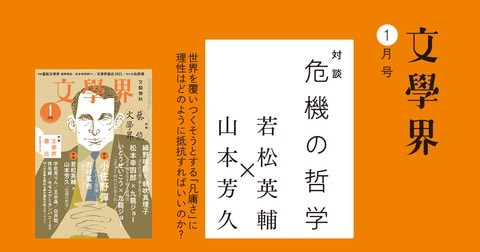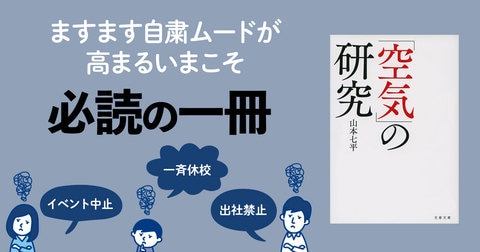「私にとって小林秀雄論を書くとは越知の『小林秀雄論』への無謀な挑戦であり続けた」と「あとがき」で自解しているが、若松氏が四十九歳で帰天した越知保夫の年齢になった年に刊行された本書は、〈文士の遺言〉として越知から受けとったバトンを次の世代につなぐ仕事ではなかったか。「あとがき」の「この本を、これまであまり小林に親しみのなかった人々の手にも届けという祈りを籠めて、世に送り出したい」との言葉は、小林の作品を「読む」ことが「自己への手紙のように思われてくる」新たな読み手が生まれ、その営為を持続する者の中から「その世界にむかって言葉を送り返したくなる」新たな書き手が次の世代にも生まれてほしいとの心からの祈願にちがいない。
ここで若松氏が越知と共に近代日本のカトリシズムの血脈を継承する批評家としてどのような点が、小林の見ていた世界を独自に描き出す精神的土壌になっているか、三点指摘しておきたい。
まず、第一は、若松氏において「カトリック」とは、越知が信頼するガブリエル・マルセルの言葉を受けて、宗教としての「カトリック」と真実の意味での「普遍(カトリック)」の二重の意味をもつ中で、カトリシズムが「普遍(カトリック)」を希求する信仰共同体でなくてはならないと捉えている点である。それはカトリック信者かどうかを越えて、すべての人に開かれている。それゆえ、若松氏が関心を寄せる批評の中心に、小林秀雄、井筒俊彦、中村光夫といった「普遍なるもの」を真摯に希求した求道の文学者たちが入ってくるのに何の不思議もない。「美しい花」が実在の顕現であるなら、それは「普遍なるもの」に触れていよう。
あまりに社会の変化が大きく速い今日、情報の氾濫の中で目先の流行や対処法にばかり目を奪われ、振り回されている時代であるからこそいっそう強く、私たちは、時代が変わっても変わらない普遍なる真善美を心のどこかで渇望しているのではないだろうか。カトリック批評家として若松氏はまさにその渇望に応える言葉を心から心へ届ける文学者であるゆえに、氏の言葉が今求められているのであろう。
第二に、宗教的献身の志が意識の奥に息づくカトリックの境遇に若松氏が育った点である。若松氏は、熱心なカトリック信者の母のもと、生後七十日で洗礼を受け、少年期には毎朝母と教会のミサに通い、生涯を神に捧げ人のために生きる神父と身近に接し、将来神父になることを考える体験をしている。この少年期の体験は越知にも遠藤周作にも共通する。こうした神と他者への宗教的な献身の志を意識の奥にもつ越知が批評という道を選んだ時、その営為が意識の領域における近代的自我の表出に向かうのではなく、「魂」の領域で展開され、「無私」の精神によって行われる方向に向かったのも必然であったろう。その越知の血脈を継いだ若松氏が「無私」の精神で小林の見た世界を献身的に描き出す本書は、自ずと「無私」の氏ゆえに浮かび上がらせることのできた鮮烈な小林秀雄の姿が表現された批評となっている。以前、若松氏に近況を尋ねた時、「自分は宅配便の配達人で、あちらからどんどん送られてきてなかなか休ませてくれないので、こちらはへとへとだけど、その分、あちらから守られてもいますから」とはにかみ顔で答えた言葉が忘れられない。その時、自分を「郵便脚夫」(詩「屈折率」)に例えた宮沢賢治を想わずにはいられなかった。賢治も法華経信仰をもって世界と他者への献身の志をもち、自分の作品を風や林からもらってきた(『注文の多い料理店』序)と語り、「普遍なるもの」を希求した求道者だった。