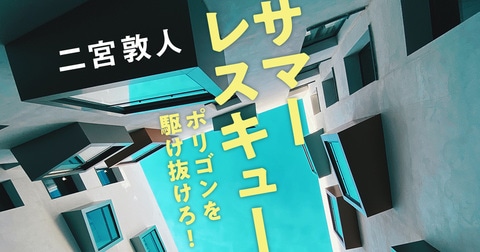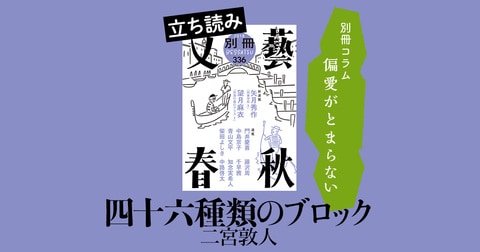第一章
「千香ーっ。巧己君、来たよーっ」
玄関からお母さんの声。千香は雑誌の山を抱え上げながら、声を張り上げる。
「ちょっと、あと五分でいいから、時間稼いで!」
「何言ってんだか、あの子は中学二年生にもなって。ごめんなさいね、朝から部屋の掃除してるらしくって……」
ああもう、余計なことは言わなくていいのに。おっと。
雪崩を起こしかけた漫画本を背中で受け止める。危ない、危ない。ほっとしたのも束の間、脇をすり抜けて、せっかく押し入れに詰め込んだガラクタたちが転げ出てきた。
「ああ、ああ」
キャラクターもののぬいぐるみ。小学校の頃、わけもなく集めていたペットボトルの蓋。ちょっと背伸びして買ってみたファッション雑誌に、一度も着ずじまいのフリルがついたオフショルダーのブラウス。見るだけで顔が赤くなりそうだ。こんなもの、絶対に巧己に見られるわけにはいかない。
「お母さん、時間稼ぎ、もう五分追加で!」
しまう順番とか、並べ方とか、もうどうでもいい。とにかく視界から消し去らなくては。散らばったものをひっつかみ、次々に押し入れに放り込んでいく。その時だった。ブラウスの下から思いがけずスマイリーフェイスが現われて、手が止まった。
黄色い丸ににっこり笑った顔のシールが表紙に貼られたノート。使い込まれてすっかり色褪せ、ところどころ破れてテープで補強してある。「おひさまおうこく、けんこくけいかく。その①」と下手な字で題されていた。
ぱっと思い出が蘇ってくる。昔大好きだったコンピュータゲーム、「ランドクラフト」のために作ったノートだ。何十冊も作ったっけ。あの頃はいつも、ゲームの世界のことを考えていた。どうしたら住みやすい王国になるのか。どこに道を作って、どこに建物を建てようか。何日かゲームをしていないと、「王様早く帰ってきてください」と声が聞こえるような気すらした。
あの頃はいつでも、胸を張って言えたんだ。
――私が得意なものはゲームです。
ぱらぱらとページをめくると、「おしろのせっけいず」や「おうこくのちず」がいくつも現われた。拙い絵と字だったが、隅から隅までびっしりと、細かく書き込まれていた。
「こんなものに夢中になっていたなんて、バカみたい」
ノートを閉じる。
まだスマイリーフェイスはこちらににっこり笑いかけてくる。なぜか心の奥がちくりと痛んで、千香はしばらく動けずにいた。
「おーい、千香」
すぐ背後からノックの音がして、飛び上がらんばかりに驚いた。そうだった。巧己が来るんだった。まずい、まずい。
「片付けなんかいいからさ、それより大事な相談があるんだよ。入っていいか?」
「だめ! あと三分、いや三十秒」
「あ。悪い、開けちゃった」
扉が開いていくのが、スローモーションのように感じた。追い詰められた千香の体は、しかし最も合理的な行動を取った。右手で座布団を敷き、左手でノートをその下に滑り込ませる。ほぼ同時に足を蹴り出して押し入れの襖を閉じ、何事もなかったような顔で足を揃えて座ると、にっこり微笑んだ。
「いらっしゃい。ごめんね、待たせて」
巧己は、ぽかんとした顔でこちらを見下ろしている。
「今……ブレイクダンスみたいな動きしてた?」
「別に。まあ座って、座って」
「そっか」
巧己はすらりと長い足を邪魔そうに折りたたみ、腰を下ろす。目線が合うと、思わず見とれた。日焼けした肌は精悍で、顔つきも男らしく、自信に満ちあふれていた。昔は転んで泣きべそかいてたのを、手を引いて家まで連れて帰ってやったこともあったのに。
今は彼がただそこに座っているだけで、ちょっと緊張してしまう。
「急に会いたいって、何?」
つい、尖った口の利き方をしてしまった。
「夏休みの宿題が終わらないなんて言わないでよね」
「いやあ、まさか」
「祥一と一緒に夜中まで手伝わされたの、忘れてないから」
「小二の時じゃん、いい加減許してくれよ。あ、おばさん、すみません」
お母さんがコーヒーを持ってきてくれた。
「巧己君、本当に大きくなったねえ。それにずいぶん男前になって。バスケットボール部はどう?」
「突き指しまくりですけど、楽しいです」
「女の子にきゃあきゃあ言われるでしょう」
「あ、言われますね」
「へえ、どんな気分? そういうの」
「嬉しいです、へへ。見られてると、シュートもよく入るんですよ」
お母さんにも爽やかに笑いかける巧己。そんなところがずるい。
千香は黙って角砂糖を二粒取り、黒い水面に放り込んでかき混ぜた。
巧己にかけっこで初めて負けたのは、小学校の四年生だったろうか。その時はまだ、頑張れば次は追い越せると信じていた。だけど巧己はみるみるうちに運動の才能を開花させていき、今ではどんな競技でもかなわない。クラスではぶっちぎりの一番、学年でも一、二を争うようなスポーツマンになってしまった。一方の千香は、マラソンでも徒競走でも下から数えた方が早い始末。近頃では野呂、という名字までバカにされているような気がする。
お母さんが階下に降りていった音を確かめると、巧己は座り直してまっすぐに千香を見つめた。
「なんか、久しぶりだな。千香とこうやって話すのも」
「そうだね」
巧己はいつも部活の仲間や女の子たちに囲まれているので、近づきづらくなってしまった。
「まあ特に話すこともないもんな」
「うん。だから、急に連絡貰って驚いたよ」
下手したら存在すら、忘れられているかと思ってたもの。
「あのさ。もしかしたらなんだけど、祥一の奴から連絡来てないか」
「祥一から? いや、ないけど」
巧己は困ったように顎をかいた。
「うーん。やっぱりそうか。だよな」
祥一なんて、巧己よりもっとひどい。彼の目には千香はおろか、クラスメイトは誰一人映っていないのではなかろうか。一緒に遊んだ記憶は小学校五年生くらいまで。だんだんと疎遠になり、今では口も利かなくなった。喧嘩をしているわけではない。いつも難しそうな本を読んでいて、話しかけても気づいてくれないのだ。千香が祥一の動向について知るのは、もっぱら校内の掲示板でだけ。試験で学年一位になっていたり、文芸部でもないくせに文学評論コンクールでしれっと優秀賞を取っていたり。
孤高の存在だった。
どの科目も平均点ぎりぎりで、小説一つ最後まで読めない千香からすると、巧己以上に遠く感じられる。
「何か祥一に関係した話なの」
「ま、な」
そこで巧己はきょろきょろと室内を見回した。
何か探しているのかな。大丈夫。見られてまずいものは、全部隠したはず。
「千香って最近、何してんの」
「何って」
「ゲームは? 相変わらずやってるんだろ」
座布団の下で、四角い角がお尻にちくりと突き刺さる。
自分でもびっくりするくらい低い声が出た。
「やらないよ、ゲームは。もう」
「えっ」
巧己は驚いたように目を丸くした。慌てて千香は取り繕う。
「いや。だって、ちょっと子供っぽいもん」
「そっか。まあ、うん。でも意外だな、千香と言えばゲームだと思ってたから」
「小学校まではね。でもゲームなんて、どれだけやり込んでもただのデータでしょ。馬鹿らしくなっちゃって。私はもっと自分のためになることをしたいんだ」
巧己や祥一がどんどん自分の世界を広げて、みんなに評価されているように。
「へえ?」
「たとえばそうだな、語学とか。見て、英会話始めたんだ」
机の上に広げておいた教材を指さして、さりげなく巧己の様子を窺った。まだ最初の方しかやってないけれど。
「絶対無駄にならないでしょ。将来は世界を舞台に仕事ができるような人になりたくて」
「そっか、ふうん」
しかし巧己はちらりと机を見ただけで、あまり興味がなさそうだった。
「じゃあこんな相談をしに来たのは、迷惑だったかもしれないな」
困ったように目を伏せている。
「何なの。一応、言ってみてよ」
しばらく巧己はコーヒーを見つめて逡巡しているようだったが、やがて顔を上げた。
「これさ、冗談でもなんでもなくて、真面目な話なんだけど。祥一がゲームの世界に行ったまま行方不明、って言ったら……お前、信じる?」
この続きは、「別冊文藝春秋」3月号に掲載されています。
2022年2月1日に誕生した小説好きのためのコミュニティ「WEB別冊文藝春秋」はこちら!