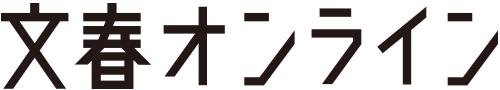『ルポ 誰が国語力を殺すのか』が話題を呼ぶ石井光太氏と、中学校の国語教科書の代表編者や高校生直木賞実行委員会代表を務める、明治大学教授・伊藤氏貴氏による特別対談。学校現場での実例を交えながら、国語力と人間形成をテーマに語り合った。

◆◆◆
何でも「やばい」で済ませる若者言葉
伊藤 今日は高校生直木賞のイベントなので、会場には高校生の皆さんや現場の先生方がいらしてくださっていますね。
石井さんの新著『ルポ 誰が国語力を殺すのか』はかなり刺激的なタイトルですが、ひとつ希望があるとすれば、「殺したのか」という過去形にはなっていない。ほとんど瀕死状態じゃないかという実情は描かれていますが、まだ救える希望も感じました。
石井さんは、文科省の定義に沿った「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」の4つの中核からなる、生きる力と密接に結びついた国語力について掘り下げていますが、そもそもこのテーマに挑むきっかけは何だったのでしょう。
石井 僕は10代の終わり頃から、海外の貧困の人たち、ストリートチルドレンを取材することが多くありました。例えばインドの最下層のストリートチルドレンは学校に行っていないので、語彙が非常に少なく、およそ100単語くらいで、ほとんどの日常会話が成り立っています。
何でも「やばい」で済ませる日本の若者言葉じゃないですが、少ない語彙で日常を回しているストリートチルドレンは、自分が今どういう状況に置かれているのか、自分はどう思っているのか、何がしたいのか、言葉で考えられません。過酷な児童労働で搾取されても、どうしていいのか考えられないので、思考停止し、窮状を受け入れてしまう。自分がどうしたいのかということさえ言葉で考えることができないのです。
「なぜ売春したのか」「なぜ殺したのか」を言語化できない結果…
海外取材で感じていた「言葉の脆弱性」の問題を、その後、国内の少年犯罪や虐待家庭の子供たちを取材するなかでも、同じように痛感するようになりました。彼らの多くは言葉を持っておらず、たとえば、女子少年院で取材しても、「なんで売春したんですか?」「先輩に言われたから」「辛くなかったんですか」「わかんない」。男子に話を聞いても、「なんで暴力をふるったの?」「むかついたから」「なんでむかついたの?」「わかんない」といった具合です。
ずっと虐待を受け、施設にたらいまわしにされて、はては人を殺めてしまった子とかにインタビューをすると、全く言葉を持っていないんですね。「なぜ殺してしまったのか」をうまく言語化できないし、言葉がないから、自分の心の動きを捉えられない。
重大な罪を犯した少年たちと接していて一番感じたのは、「ぶっ殺す」といった言葉を使う前に、自分のこの感情はなんなのか? 本当に殺したいと思っているのか? といったように感情を言葉で細分化して考えることができる力があれば、その行動は思いとどまれたのではないか? ということです。
言葉は社会で生きていく力に深く結びついていると痛感するなかで、近年多くの教職員の方から子どもたちの国語力低下を嘆く声を聞いたのが、このテーマに取り組むきっかけとなりました。
現場で教えている先生の実感としてどうでしょうか?
“国語力低下”の一因だと感じるのは若者が使いこなす、あのツールです
伊藤 私は今、主に大学生を相手に教えていますが、文学部なのでそれなりに本を読んだり、書きたいと思っている子が多くいます。ただそれでも最近強く感じるのは、「読書で背伸びをしなくなった」ということ。自分が読みやすい本ばかり読んで、ちょっと難しいけど読んでみようというチャレンジをしない。だから、大学1年と2年で、読めるものの水準がさっぱり上がらないんです。
昔は、まわりの友達から難しい本の話題が出ると、その場では知ったかぶりして合わせて、帰ったらすぐその本を読むとか、次に会う日までに理論武装していくような教養文化が大学生の間にありました。それは見栄ではありましたが、相手についていこうということでもあった。こういう「知的な見栄」など張らない方が楽なのかもしれませんが、難しい書物に手をつけないのは、作者が掘り下げた複雑な思考を最初からわからなくていいやと手放してしまっているんですね。

これはもっと手前の段階でいうと、普段から「別に友達が何を考えているかわからなくてもいいや」という、非常に浅いコミュニケーションのなかで人間関係が成立していることにも繋がっている気がします。わからない所があったら突っ込んで話し合う――そんな人間関係のベースとなる経験が失われているのかもしれません。
希薄なコミュニケーションが主流になってしまったのは、SNSもひとつの要因ではないでしょうか。
日常のコミュニケーションがSNSの言葉遣いに浸食されている
石井 若い子たちほど、SNSを使いこなしている自信があると思うんです。ただ、SNS上の言語は、非常に短くて、感情を極端な単語で一括りにして、パッと吐き出す傾向にあります。きちんと思考して論理だった説明をしていたら、「長文ウザっ」てなりますよね。だから、その瞬間の感情をわかりやすく極端な単語やスタンプで吐き出しがち。
でもリアルのコミュニケーションはもっと複雑で、人と付き合ったり信頼し合うためには考えて行動しないといけない。うまくいかない時にこそ、言葉をよく考えて、いかに関係性を築くかが問われます。日常のコミュニケーションが知らず知らずのうちにSNSの言葉の使い方に侵食されているような今、深い人間関係を構築するのが苦手な傾向があると思います。
伊藤 相手がどう自分の言葉を受け取るか、人とどうやって付き合っていくかは人として生きていくうえでのスタートラインです。本書に出てくる国語力の乏しい子どもたちは社会のなかでの自分をわかっていないし、相手のことも理解できない。
私はいわゆるFランクと呼ばれる大学の非常勤講師もやってきましたが、日本語表現の授業がありました。小説を書かせたりするような創作の授業ではなく、大学からのオーダーは「半年で履歴書を書けるようにしてほしい」というものでした。
履歴書の志望動機に「給料が高くてラクそうだから」
どういうことだろう?と思って最初の授業で、空欄の履歴書をコピーして配り、学生たちにアルバイトの応募をする想定で書いてもらったら、もうびっくりするほど書けないんですね。そもそも左のものを右に写せずに書く欄がズレていたり、志望動機には「給料が高くてラクそうだから」などと平気で記述してある。素直と言えばあまりに素直ですが。

「バイトを審査する側に立ったら、この履歴書を見てどう思うか?」と想像できないんです。
石井 僕が取材に行ったある高校は、卒業生の多くが就職するので、高3の1学期から就職指導がはじまるのですが、まさに履歴書の書き方であり、面接の仕方が問題になっていました。
本書にも書きましたが、入社試験の面接官が志望動機を確認しようと「なんでうちに来たの?」と聞くと、生徒は平然と「電車で来た」と一言で答える。あるいは、面接官がその子のやる気やスキルを確認しようと自己アピールを促すと、「俺はAB型で、身長173センチ、体重は65キロです」と答える。だから、高校は何カ月もかけて生徒に面接の特訓をするのですが、そこまでしてもみんなができるようになるわけではないそうです。
なぜこうしたことが起こるのか。生徒が面接の会話の文脈を読み取れていないのです。状況を把握し、相手の質問意図を想像し、話の流れを踏まえた上で、適切な返答をするという基本的なことができない。
これは面接のやり方がわかっていないということではなく、日々のコミュニケーションの中でそうした経験を積み重ねてこなかったため起きていることなのです。こうした子供たちが面接に合格して社会に出たとしても、様々なところで生きづらさを感じるのは当たり前です。
一方で今の生徒たちにも同情すべき点がある
ただ、生徒たちに同情すべき点もあります。社会がグローバル化し複雑化するなかで、いわゆる常識というものが階層やコミュニティによって細分化されてしまっています。昔は日本人全体で共有されていたような常識が、家庭によってバラバラになってしまっています。
例えば、ラーメン屋の店員がある家族にラーメンと箸を出したところ、クレームになったそうです。その家庭はコンビニでカップ麺を買って、プラスチックのフォークで食べているのが日常だったそうです。だから、ラーメンはフォークで食べるものだと思い込んでおり、箸を出されて怒ったのだとか。その家族にしてみれば、寿司屋に行って寿司とフォークを出されたような感覚だったのでしょう。
現代は、ラーメン一つとっても、これくらい常識にギャップが生まれる時代なのです。さらにそこに教育格差で「国語力カースト」とでもいうべき、言葉の理解力・発信力の差が加わってきますから、コミュニケーション上の齟齬も生まれやすい。よほど言葉で状況を熟慮し、想像し、表現する力がないと、トラブルになりかねないのです。僕は能力の基盤こそが、言葉をもとにした情緒力、想像力、論理的思考、表現力の集合体である「国語力」だと思うのです。

伊藤 相手の立場に立ち、なぜこの言葉がいま必要なのか、どう書けば相手に伝わるかを考える――それがコミュニケーションの基本であり、国語力を育むには、ある程度の長さのある文を読むことが肝心だと思っています。
どのように“国語力”を育めばよいのだろうか
石井 小学校低学年くらいまでは、国語力は主に家庭の中で育まれていきます。それ以降の年齢になると、今度は読み書きなどを通して能動的に身につけていかなければならなくなる。たとえば、10代の頃に長い文を読むことによってでしか感じられないものって確かにありますよね。取材したある私立中学校では、国語のテキストとして、丸1学期間かけて『アンネの日記』を精読しますが、14歳のアンネが書いた長い日記を読み込むことで、同じ世代の人間が、戦争の中で日々何をどう感じたのか深く考えられる。
無論長ければいいわけではありませんが、やはり1冊の本の中で細やかな心の動きをきちんと読み取っていくことで育まれる「他者へのリアルな想像力を伴った」国語力というものは大きいと思います。
伊藤 もう一つ、『ルポ 誰が国語力を殺すのか』で紹介されていた哲学対話の授業も非常に興味深く感じました。じつはかつて私が通っていた高校では、校長先生が哲学の先生で、総合の時間に「一緒にモノを考える」っていう授業をしておられました。話題もその都度自分たちで決めて、ただ「考えて、話す」だけの時間があった。そういう答えが出ない問いをめぐる対話って、どうせ答えがでないなら、無駄じゃないかと思われがち。
でも、そのなかで、相手に伝えるための言葉について考えることは、実は自分自身を知ることに繋がってくるんですね。高校生直木賞における私のひとつの目論見は、自分の考えをどうやって人に説得力ある言葉で伝えられるのか?にあります。ある作品が面白かったら「じゃあ、どこがどう面白いのか」を生徒たちがどんどん掘り下げていくきっかけにしたいんです。

石井 高校生が主体的に小説を読み込んで自分たちで直木賞を選出するって、素晴らしい試みですよね(笑)。
「生きやすい自分」をつくるために求められること、それは…
哲学対話に関していうと、これはいろいろな人種や階級の入り乱れるアメリカ社会で、異なる思考を持った人たちとどう共生するかという切実な問いから生まれた教育法です。他者の考えをじっくり聞くと、「こんな別の目線があるんだ」「当事者はこんな感じ方をするんだ」と、初めて得られる気づきがたくさんあります。
自分の思い込みが壊され、視点が多様化していく。僕がノンフィクションをやっている理由もそこにあって、最初にこうだろうと思っていた固定観念は、取材のたびに裏切られます。実際に会って、話を聞くと必ず新しい発見があるんですね。
若い人たちにはそういう他者と向き合ったとき面白さをどんどん発見してほしいし、そこから、互いに分かり合うためにどう建設的な話をしていくか、自分のなかの言葉を探ってほしい。それは困難な状況に直面したときに、言葉でもって状況を打開できる「生きやすい自分」をつくることに必ず繋がってきますから。
伊藤 まさにおっしゃる通りで、言葉は他者と出会って更新し続けていくものです。本を読むのも、自分の考えが壊されたときの快感があります。新しい本はもちろん、同じ本を繰り返し読むなかでも発見がある。
石井 学生たちにはそうやって自分のなかで発見し、育まれた言葉をどんどんリアルな体験のなかで膨らませていってほしいと思っています。自分の経験と言葉が結びつき、思考がどんどん広がっていく快感は、生きる楽しさそのものですから。
伊藤 今日は刺激的なお話をありがとうございました。
プロフィール
石井光太(いしい・こうた)
1977年東京生まれ。作家。国内外の貧困、災害、事件などをテーマに取材・執筆活動をおこなう。著書に『物乞う仏陀』『絶対貧困 世界リアル貧困学講義』『遺体 震災、津波の果てに』『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』『原爆 広島を復興させた人びと』『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』『本当の貧困の話をしよう 未来を変える方程式』『格差と分断の社会地図 16歳からの〈日本のリアル〉』など多数。2021年『こどもホスピスの奇跡 短い人生の「最期」をつくる』で新潮ドキュメント賞を受賞。
伊藤氏貴(いとう・うじたか)
1968年生まれ。文芸評論家、明治大学文学部教授。麻布中学校・高等学校卒業後、早稲田大学第一文学部を経て日本大学大学院藝術学研究科修了。博士(藝術学)。2002年「他者の在処」で群像新人文学賞(評論部門)受賞。主な著書に『告白の文学』『奇跡の教室』『美の日本』『国語読解力「奇跡のドリル」小学校1・2年』、翻訳に『ジョージ・セル ―音楽の生涯―』など。専攻分野(研究分野)は文芸メディアおよび現代における文藝思潮。第1回目から高校生直木賞実行委員会代表を務めている。


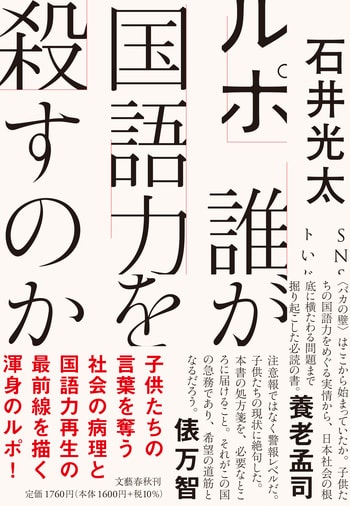
![[第9回 高校生直木賞全国大会レポート]“危機の時代”の高校生直木賞](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/6/e/480wm/img_6ed6d81bf0949403459618605ff4c19b220191.jpg)


![[第8回 高校生直木賞全国大会レポート]四時間かけた議論の末“同票”で史上初の二作受賞](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/8/e/480wm/img_8ecbfa907f82de0fc58fac5476017aaf219466.jpg)