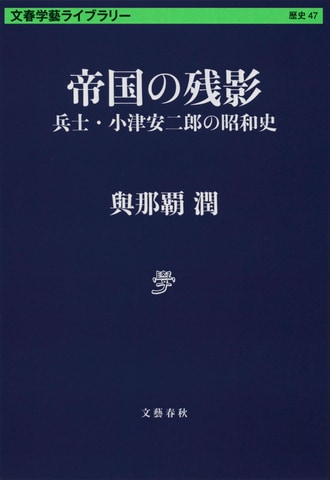だが、その後作られた小津映画には「戦場」描写が欠如している。戦中・戦後に発表した全17作の家族映画のうち、一作を例外として「家族」と「戦争」のつながりが仄めかされているにもかかわらず、戦場それ自体の光景が描かれることはなかった。さらに暴力描写までもが減っている。
本書で與那覇さんがこだわるのは、この「欠如」や「不在」である。なぜ小津は自身で経験した戦争ではなく、経験しなかった家族を描き続けたのか。今や「リアルな昭和」そのものに思えてしまうその家族には何が潜んでいるのか。
この「大謎」に対して與那覇さんがどんな名回答を提示するのかは本書を読んでもらうのがいいが、興味深いのは小津の『東京物語』と同じ1953年に公開された、木下惠介監督の『日本の悲劇』という作品である(本書177ページ)。
家族の映画であるのだが、特徴的なのは実際のニュース・フィルムが挿入され、敗戦後の貧困が「リアル」に描かれた点だ。松竹で試写会が行われた際には、万雷の拍手が送られたというが、その中で小津は黙って席を立ったのだという。
なぜ小津は『日本の悲劇』を否定したのか。
クリエーターの間では時折話題になるのだが、物語は大きく「現実直視型」と「ファンタジー型」の二つに分けることができる。
「現実直視型」とは、『日本の悲劇』のように、社会問題をありのまま描いた作品群である。自称知識人が褒めそやし、映画賞や文学賞の候補になるのはもっぱらこの「現実直視型」だ。なぜなら彼らは、社会問題をある種のエンターテインメントとして受容できるだけの余裕があるからである。
しかし大ヒットしたり、歴史を越えて残る可能性があるのは、いつの時代も「ファンタジー型」である。批評家たちに「社会に対する問題提起がない」「都合のよすぎる展開に辟易」などと批判されることの多い「ファンタジー型」だが、それは批評家が自らが特権的な階級に所属していることを忘れているからだ。
多くの人類が食糧に困っていた時代から、無数のファンタジーが生まれ、それは神話という形で後世に伝えられた。現代でも、苦しい生活を送る人が、物語に求めるのは、一瞬でも現実を忘れさせてくれる作品ではないのか。
実際、1953年の日本映画興行収入で『東京物語』は1億3165万円で年間8位を記録している(6)。現代の金額に換算すると25億円から40億円並みのヒットということになる。『日本の悲劇』はそれに及ばなかったし、今や言及される機会もほとんどない。
やがて小津安二郎は「いちばん日本的だと日本人が思っている映画監督」と評されるようになる(本書214ページ)。実際の日本や日本国籍保有者が多様である以上、「日本的」というのは、ある種のファンタジーに過ぎないわけだが、なぜそれを小津映画が担うことができたのか。本書の中でも、第4章から終章にいたる議論は、「日本」論としても出色の出来だと思う。
「いちばん日本的」と思われているものの中心に、大いなる「欠如」や「不在」を指摘できるというのも、ある意味で非常に「日本的」と言える。
安田武と與那覇潤
2022年、「あの戦争」の終わりから77年が経過した。77年というのは、1868年の明治元年から1945年の敗戦までと同じ長さだ。
その77年の中で、当然ながら記憶の「風化」が進んできた。たとえば2015年にNHKが実施した世論調査によると、「原爆投下の日」の正答率は3割にとどまったという(7)。「若者」に限った結果ではない。全世代において、あの戦争は遠いものになっている。
もしかしたら「あの戦争」という呼称さえ、注釈が必要な時代なのかも知れない。実際、今や「戦時下の日本」という言葉が過去に対してではなく、未来予測に使われることもある(8)。
だが視点を変えれば、あの戦争は社会に溢れてもいる。今でも夏になればテレビや新聞は戦争特集を組むし、『永遠の0』や『この世界の片隅に』のように、繰り返しフィクションの題材になってきた。NHKの連続テレビ小説でも戦争は定番のテーマで、近作『カムカムエヴリバディ』では松村北斗(SixTONES)演じる雉真稔(きじまみのる)が、学徒出陣によって戦地に赴くエピソードが、大きな話題を呼んだ。
(6)『東京物語』は、キネマ旬報ベスト・テンでも2位にランクインしている(キネマ旬報社編『キネマ旬報ベスト・テン95回全史』2022年)。評論家に評価されながら、きちんと興行収入も確保したということになる。近年の例では、是枝裕和監督『万引き家族』(2018年)や、ポン・ジュノ監督『パラサイト 半地下の家族』(2019年)が思い浮かぶ。
(7)政木みき「原爆投下から70年 薄れる記憶、どう語り継ぐ」『放送研究と調査』2015年11月号。
(8)東浩紀・小泉悠「ロシアは絶対悪なのか」『文藝春秋』2022年7月号。福島第一原発の事故の際、住民の避難に国家による全体避難計画があったわけではなく、地方自治体任せだったことを指摘した東浩紀に対して、小泉悠は「そうした事態は戦時下の日本においてもありえる」と応答している。