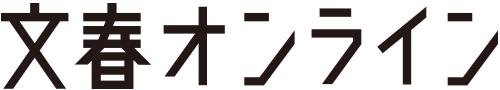いまや年末の風物詩である「M-1グランプリ」。一夜にして富と人気を手にすることができるこのビッグイベントに、「ちゃっちゃっと優勝して、天下を獲ったるわい」と乗り込んだコンビがいる。2002年から9年連続で決勝に進出し、「ミスターM-1」「M-1の申し子」と呼ばれた笑い飯である。
ここでは、笑い飯、千鳥、フットボールアワーなどの現役芸人やスタッフの証言をもとに、漫才とM-1の20年を活写した中村計氏のノンフィクション『笑い神 M-1、その純情と狂気』(文藝春秋)から一部を抜粋してお届けする。(全2回の1回目/2回目に続く)

◆◆◆
関東生まれの私が漫才の世界にどっぷりと浸かる“きっかけ”
漫才の本場は関西だ。大学時代を除いて関東で生まれ育った私は、正直に告白すれば、これまでの人生でほとんどと言っていいほど漫才に触れる機会がなかったし、興味を持ったこともなかった。
そんな私が今、漫才の世界に、どっぷりと浸かっている。
きっかけは、はっきりしている。2017年夏、『週刊プレイボーイ』誌上で、オール阪神・巨人の大きい方、オール巨人による「オール巨人の劇場漫才師の流儀」という連載が始まった。私はその取材と構成を担当していて、月一回、オール巨人に話を聞く機会に恵まれた。
私は漫才に興味はなかったが、オール阪神・巨人は好きだった。心地のいい声。心地のいいリズム。心地のいい語り口。もともと落語は大好きだったのだが、オール阪神・巨人の漫才は、好きな噺家の落語を聴いているような、あるいは音楽を聴いているような感覚に近かった。
オール巨人の取材は、私にとって、初心者向けの漫才講座でもあった。漫才には、日常会話を装う「しゃべくり漫才」と、コンビニの客と店員などの役柄に入る「コント漫才」に大別される。前者はしゃべくり(会話)が中心、後者は「おれが客をやるから、おまえは店員をやって」という前振りから入るのが常道だった。
また、誘い笑い(意図的に自らが笑うこと)や、客をいらう(イジる)行為は、漫才として行儀のいいものではないということなども初めて知った。
私はオール巨人にすっかり弟子入りしたような気分になり、「漫才とは」と自問自答するようになった。そして、わが「師」が審査員を務めていたM-1グランプリの決勝をスタジオで観覧するのも毎年の恒例行事となっていく。
ここで漫才の中のもう1つの扉が開いた。M-1である。
M-1とは漫才日本一を決めるコンテストのことだ。もちろん、名前ぐらいは聞いたことがあったし、何度か観たこともあった。私の周囲にもM-1を熱っぽく語る人がたくさんいた。しかし、そんな人たちをどこか冷めた目で見ていた。いい大人が、と。たかがバラエティ番組ではないか、と。
ところが、漫才のにわか知識を携えてM-1を見始めた途端、まるで濁流に飲み込まれたかのごとく、体ごと一気に持っていかれてしまった。
富も、名声も、人気も、一度に手に入れることができる「M-1」
M-1は2001年に始まった。その後、2010年を最後に歴史の幕をいったん下ろしたものの、2015年に復活し、現在に至っている。
今や、そのエントリー総数は7000組を超え、国内最大のお笑いイベントに成長した。
創設前、漫才は衰退期の中で喘(あえ)いでいた。ところが、今や漫才は、大衆演芸のど真ん中に君臨している。それもこれもM-1の存在を抜きには語れない。
M-1に優勝すれば、一夜にして世界が変わる。富も、名声も、人気も、一度に手に入れることができる。現代の芸能界で、これ以上のシンデレラストーリーはそうはない。
私が漫才にどっぷり浸かるようになった最大の要因。それも、このM-1であることは間違いない。
私はことあるごとに過去のM-1を見返した。最近こそやや傾向が変わってきたものの、歴代王者を俯瞰すると、M-1は関西弁でまくし立てるしゃべくり漫才系のコンビが圧倒的に強かった。
大学時代を関西で過ごした私には、その理由がおぼろげながらも見えた。
学生時代、私は私なりに関西弁を操っていた。そして、驚嘆した。関西弁とは、なんと感情を乗せやすく、テンポのいい話し言葉なのか、と。
「しばくぞ、こら!」
「やっぱ、好きやねん」
関東に戻ってきて30年近くになる。使ったことはなかったが、これらの言葉を超える怒りの言葉、愛の言葉を私は未だに知らない。
ラップは英語がいちばんフィットするように、演歌は日本語がもっともしっくりくるように、漫才における最強の話し言葉は関西弁である。そんな確信があった。

その仮説を、関東を代表する漫才コンビ、ナイツの塙宣之にぶつけてまとめた『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』(著・塙宣之、聞き手・中村計)は、10万部のベストセラーになった。このあたりから、芸人関係、漫才関係の仕事が急増し、私はより一層、この界隈の取材にのめり込んでいくことになる。
漫才とは何か。笑いとは何か。その核心を、その神髄を、覗き見たくなった。
ただ、厳密に言えば、私は、漫才を好きになっただけではなかった。それ以上に、漫才に、そしてM-1に青春を賭けた芸人たちの姿に、たまらなく惹かれたのだ。
彼や彼女たちの人生に触れるたびに、やはり人は神に祝福されているのではないかと思った。号泣しながら大笑いしたくなるような、生きることを1%の疑いもなく肯定したくなるような幸福な気分に満たされた。
漫才師とは、なんとバカな生き物なのだろう、と。
M-1グランプリ決勝の敗者復活戦で起きたこと
忘れられない漫才がある。
2018年12月2日。場所は、東京港区のテレビ朝日の隣に設置された屋外ステージ。そこでは午後2時半から、M-1グランプリ決勝の最後の一枠をかけた敗者復活戦が始まっていた。出場者は準決勝で敗れた16組だ。ネタの時間は3分だった。
会場は、何よりもまず寒かった。客の身体が凍え、笑いが起きにくくなる。また野外ゆえ声が拡散しやすく、つぶやくように話す芸風の漫才師の声はほとんど後ろまで届かなかった。
寒空の下、客の笑いは一度も爆発しないまま、最後から2番目、15組目のプラス・マイナスの出番になった。
プラス・マイナスは身長167センチ、体重90キロ超の岩橋良昌と、中肉中背で「もともと顔とかもよくないし……」と控えめに話す兼光タカシからなるコンビだ。

2015年にM-1が復活してからのエントリー資格は結成15年以内。リミットいっぱいのプラス・マイナスは、この回も含めれば5度、準決勝まで勝ち進んだものの、決勝の舞台は未経験だった。
2人はステージに登場したときから、他のコンビとは明らかに雰囲気が違った。いかにも楽しげで、自分も含め、観る側の肩の力がふっと抜けるのがわかった。
漫才は、繊細な芸である。同じネタであっても、そのときの順番、演者のテンション、ステージ環境、あるいは客層などによって、まるで別物のように色や形が変わる。
そして、あらゆる大衆演芸の中で、漫才ほど怖い芸はないのではないか。漫才は人を笑わせるだけでは足りない。笑わせ続けなければならないのだ。成功不成功が一目でわかる。
2020年のM-1決勝で、私はその瞬間を目の当たりにした。
関西の中堅どころで、抜群の人気を誇るアキナは準々決勝、準決勝と大爆笑を巻き起こしていた。坊主頭でボケの山名文和と、おしゃれで包容力のあるツッコミの秋山賢太からなるコンビは優勝候補の一角に挙げられていたほどだった。
ところが決勝では一転、さざ波のような笑いしか起きなかった。プレスルームの大画面を通し、2人の顔がみるみるうちに青ざめていくのがわかった。秋山が声を震わせる。
「めちゃめちゃ怖かったです。あっ、お客さんがついてきてない、って。全員、今すぐテレビを消してくれ! って思いましたもん。コントならウケなくてもそんなに焦らないんです。役に入ってるし、お客さんの方もあんま見ないので。
ただ、漫才はどうしてもお客さんの顔が視界に入るので、笑ってないと早く終わらしたいっていう気持ちになる。なので、やばい、やばい、でも、逃げたらあかん、って。最後までしっかりやらなと言い聞かせながらやってましたね。あんなに恥ずかしい思いをしたの、初めてでしたね」

「M-1は日本全国の前でスベってるのと同じ」
一方、山名は「真っ白な中でやっているような感覚だった」と回想する。
「一生懸命、笑いをすくおうとしてるんですよ。でも、すくっても、すくっても、指の間からこぼれ落ちていくみたいな感じでした。M-1は日本全国の前でスベってるのと同じですもんね。地獄です。まさか、あんなことが自分の人生で起こるとは思っていませんでした」
そんなデリケートな芸だけに客の心をがっちりつかんだネタには、必ずと言っていいほど「奇跡の物語」が潜んでいた。プラス・マイナスの場合もそうだった。のちに岩橋は、あのときの心境をこう振り返っている。
「僕、すごく細かい性格なんで、普段は、出る直前まで相方に『あそこゆっくりな』とか『あそこはテンション高く』とかグダグダ、グダグダ言ってるんです。でも、あの日だけは、なんか知らんけど『もう最後やし、楽しむだけやな』って言うただけで、すっと出ていけた。あんな感覚になれたんは初めてでしたね」
「トランス状態でしたね。動きキレキレでした」M-1敗者復活戦で“無名のコンビ”が大爆笑を起こし…“笑いの神”が降臨したかのような3分間 へ続く