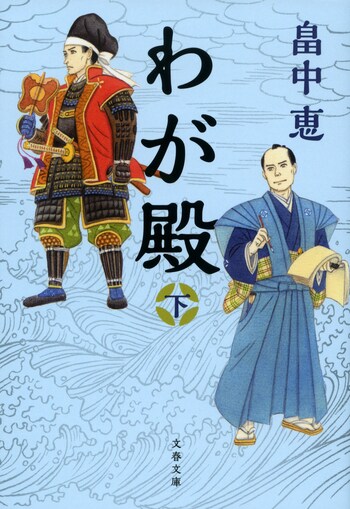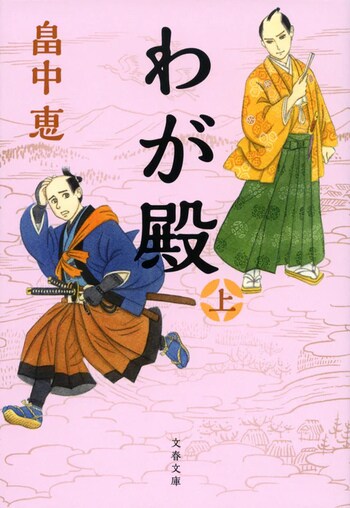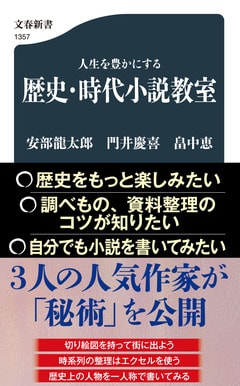それから十二年後。ひそかに利忠に見込まれていた七郎右衛門は、藩の借財の返済という、大役を命じられる。大野藩は四万石だが、実際の実入りは二万八千石。毎年、藩に入るのは一万二千両に満たない。それなのに積もり積もった借財は十万両で、一年の利息が一万両。ようやく天保の飢饉が収まったばかりの大野藩に、金などあるわけがない。八十石の、藩では中くらいの地位の自分に、いったい何ができるのか。“わが殿”の無茶な命に困った七郎右衛門が目をつけたのが、藩にある面谷銅山である。利忠に頼んで幕府から三万両を借りてもらい、それを使って新たな鉱脈を発見しようというのだ。七郎右衛門は見事に賭けに勝つ。鉱脈が見つかり、藩の財政は上向いた。だが、そこから彼の、長い長い苦闘が始まるのである。
大野藩第七代藩主の土井利忠は、英邁な人物である。しかしその器は、四万石の大名に収まりきれぬほどに大きかった。才ある者を積極的に登用し、やるべきだと思ったことは断固として実行する。三年間の面扶持で藩士に節約を強いる一方で、藩校の明倫館を作ってしまう。教育に力を入れるのは、為政者として誠に正しい。とはいえ先立つものがなくては、どうにもならぬ。そこで藩の打ち出の小槌となった七郎右衛門が苦労することになるのだ。“わが殿”に振り回されながら、あの手この手で金をひねり出す、主人公の奮闘にワクワクしてしまうのである。また、七郎右衛門の私生活の絡め方も巧み。特に、藩校の件で揉めたことが、いつの間にか妻との離婚話に変わっていく展開には感心した。物語を構築する作者の手練に脱帽するしかない。
さて、人間臭い面も見せてくれる七郎右衛門だが、主君とは違った方向で、とんでもない器の持ち主だ。彼は生真面目な自分より、文武両道の弟の隆佐(りゅうすけ)の方が優秀だと思っている。しかし、その隆佐に、
「兄者はいたって生真面目な顔をしておるが、割と……いや、大いに融通の利く人柄ゆえ」
といわれるではないか。まったくその通り。火事により江戸の上屋敷と中屋敷が焼けたとき、藩に御庭番が潜入しているという噂(本当にいたようだが)を使い幕府を動かすなど、大胆不敵なことをやってのけるのである。
さらに借財を返し終り、一息ついたと思ったら、時代は幕末に突入。利忠は藩士に洋式の訓練をさせるが、当然、金がかかる。しかしこの頃になると、七郎右衛門も落ち着いたもの。なんなく金を作り出す。そんなことをやっているうちに、七郎右衛門にある決意が生まれる。小藩ゆえに身動きが取れないが、さりとて藩は捨てられぬ。ならば自分のいる場所を大きくすれば、自由に動けるのではないか。当時の武士としては桁外れの発想で彼は、ある事業を始めるのだ。これが事実だというのだから驚くしかない。
そんな七郎右衛門を通じて、作者は何を表現したのか。作中で彼がいう「明日へゆかねばなりませぬ」であろう。大野藩にだって、時代の変化についていけず、悲劇的な死を迎えた人がいる。七郎右衛門が上手くやっていると思い、彼を憎む人もいる。だが、どんなに目を逸らしても、未来は必ずやってくるのだ。だから真剣に“今”と向き合う。混迷の時代となった現代を生きる私たちが、七郎右衛門から学ぶことは多い。
もっとも七郎右衛門が必死に頑張れたのは、“わが殿”がいたからである。ここであらためて、木原敏江の『あーら わが殿!』について触れたい。この作品は、明治の末期を舞台にしたラブコメである。当然、ハッピーエンドである。その物語を締めくくるモノローグの冒頭が“あーら わがとの いとしの きみよ”であった。七郎右衛門にとって利忠は、尊敬すると同時に怖れを抱かずにはいられない人、無理難題を常に押し付ける困った人であった。しかし長い歳月の中で彼は、利忠との出会いが自分の人生そのものであり、侍としての幸福だと思うのである。だから彼は、大野藩という器に収まりきれない行動を取りながら、武士であり続けた。“わが殿”こそが、敬慕せずにはいられない“いとしの きみ”であったからだろう。主従という垣根を超えて響きあった、ふたりの男の魂。その音色は、どこまでも美しい。