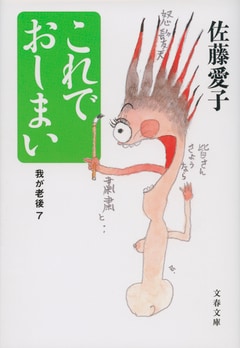その時の私の担当記者は朝比奈くんという青年で、彼は野坂さんの担当でもありました。野坂さんといえば都合が悪くなるとすぐに姿をくらますので有名でした。どの出版社の人も野坂さんには手を焼いていましたが、雑誌と違って新聞は毎日のことで、しかも野坂さんの小説は夕刊の連載でしたから、朝比奈くんの苦労は筆舌に盡し難いものだったと思います。
私の家の玄関につっ立っている朝比奈くんが、
「掴まらないんです。奥さんにもわからない。どこにもいないんです。今日の夕刊の原稿なんです……」
といって、殆ど涙目になっていた姿は、九十八歳の呆けた私の頭にもありありと残っています。せめてもの慰めに、と私は貰い物の清酒を進呈して激励したのでしたが、朝比奈くんにしてみれば、「酒どころか!」という気持だったでしょう。
その後のことはわかりません。野坂さんの小説はどうなったのか。そのうち私の連載も終り、自然に朝比奈くんとは疎遠になりました。野坂さんとはその後、何かのきっかけで親しくなり、一緒に共通の故郷である神戸へ行ったこともありましたが、締切が来ると行方不明になることについて、訊きたいと思いながら訊くことが出来ませんでした。あまりに繊細で極度に小心な人であるような気がしたからだったと思います。
それから何年か、何十年か経った頃のことです。それ以来毎日新聞とはずっと縁がなかったのですが、ある日突然、毎日新聞の朝比奈豊と墨書された手紙が来ました。朝比奈豊とはあの朝比奈青年のことであるとはすぐ気がつきましたが、あの、我が家の玄関に呆然とつっ立って、「どこにもいないんです、野坂さんは」と訴えていた青年は、今は「毎日新聞社長」に出世していたのでした。手紙は晩餐への招待でした。私たちは豪華な宴席で感慨無量の再会を楽しみました。その宴席が感慨無量なのは野坂さんの存在があったからです。私と朝比奈社長は野坂さんを懐かしんで、大いに悪口をいったのでした。その時野坂さんはもう亡くなっていたと思いますが、もしかしたら闘病中だったかもしれません。そのへんのことになると濃霧の中に迷い込んだようで、もう右も左もわからんという迷い子の気分になります。
私の文章の師であった北原武夫先生、親友だった川上宗薫(「女と見れば美醜年齢問わず口説きまくるのに、佐藤愛子だけは手を出さなかったのは本当か?」とよく訊かれましたが、川上さんは私を女ではなく仲間と見ていたのでしょう)、川上さんとおみき徳利のように毎夜、銀座通いをしていた菊村到(お酒は一滴ものめないのにいつもトマトジュースだけで最後まで川上さんにつきあっているような珍しい人でした)。会うと必ず「困ったことがあったらオレに相談せえ。一人で勝手に考えてつっ走るなよ」といばっていうのが口癖だった遠藤周作。……思い出を辿れば際限がありません。みんないなくなってしまって、もう思い出の中にしかいないのです。女学校時代のグループも、ナガボンという親友を一人残してみんないなくなりました。ナガボンは大阪から時々電話をかけて来て、
「アイ公、元気?」
といい、
「うん、元気よ」
というと、
「そうか、よかった。そんならネ」
といって電話を切る。私は単にアイコと呼び捨てにされるだけでなく、アイ公と公をつけて呼ばれていました。落語に出てくるクマ公、ハチ公の公です。アイ公と呼んでくれるのもナガボン一人しかもういません。
「どうしてみんな、こう早く死んでしまうんだろう」
とぼやいていると、孫は、
「自分が死ななすぎるんだよ」
といいます。
「なるほど、そういうことか」と私は素直にいって頷くほかないのです。