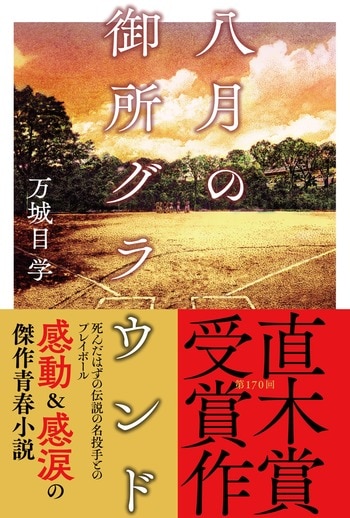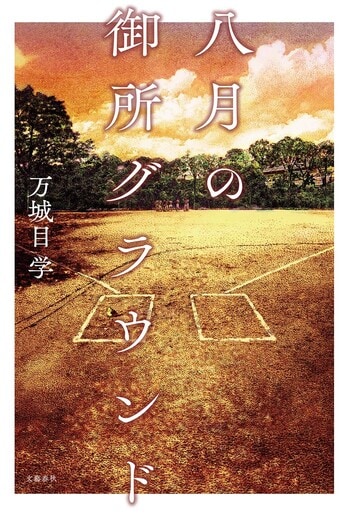「ホルモー」シリーズなどで知られる万城目学さんが約16年ぶりに原点・京都を舞台に紡いだ最新作『八月の御所グラウンド』が8月3日(木)、ついに刊行になります。
死者と生者の奇跡のような邂逅を描いた、感動の青春小説となった本作。
刊行に先立ち、本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、本書収録の第1話「十二月の都大路上下ル」の冒頭を先行無料公開します。
ピンチランナーとして、女子全国高校駅伝(通称「都大路」)に出場することとなった坂東が京都で体験した不思議で心温まる2日間――。ワクワク、ドキドキの冒頭をお楽しみください。
はじめて京都でいただく夕食なのだから、何て言うのかな、日本料理っぽい? 京都っぽい? そういうみやびやかなものが出てくるかも、と期待していた。
でも、旅館の食堂のテーブルに並んだ料理は、白身魚フライに味噌汁、サラダ、ごはん、漬物といういわゆる定食屋さんと変わらぬメニューで、ちょっとがっかりきていると、隣のテーブルに座っていた柚那(ゆずな)キャプテンが立ち上がり、
「いよいよ、明日が本番です。もう緊張している人がいるかもしれないけど、たくさん食べて、いっぱい寝て、万全の体調で挑みましょう」
と明らかに誰よりも緊張している表情で告げてから、「いただきます」と音頭を取った。
「いただきまーす」
残る十人の部員が続き、それからはいつもの和気あいあいの食事タイムが始まった。午前中から京都のあちこちを移動し、腹ペコになっていた私は、一枚目の白身魚フライをあっという間に平らげた。
ちなみに現在、私の辞書に「緊張」の二文字はない。
なぜなら、私は補欠だから。
ウソ。もちろん多少の緊張はある。何しろ、私たちの高校は実に二十七年ぶりに都大路を走る切符――、すなわち女子全国高校駅伝のエントリー権を獲得した。駅伝を志す高校生たちにとって、野球における甲子園と同じ存在感を持つ、超ビッグな大会である。わざわざ、全校生徒を集めた壮行会まで体育館で開いてもらってから、意気揚々、京都に乗りこんできたのだ。
ただし、明日の本番を走るのは三年生と二年生のレギュラーメンバーの五人。私たち一年生は全員がスタジアムやコースの途中に散らばって、センパイたちの応援に回る予定だ。
ゆえに、第一走者である柚那センパイと同じ緊張を共有できないのが、もどかしくもあり、一方で走るプレッシャーとは無縁であることにどこか安心している自分もいる。さらに、それに対する罪悪感めいたものも混ざってくるから、お気楽な一年生なりになかなか複雑なのだ。
「本番で走る人も、走らない人も、みんなでいっしょに戦う。それが、駅伝だから」
陸上部の顧問である「鉄のヒシコ」こと、菱夕子(ひし・ゆうこ)先生はことあるごとにそう言うけれど、実際に走るセンパイたちとは、求められる覚悟にも雲泥の差があるよなあ――。なんてことを考えつつ、二枚目の白身魚フライに齧(かじ)りついていると、その菱先生から「坂東(さかとう)」という鋭い声が飛んできて、
「は、はいッ」
とびっくりして顔を上げた。
「食べ終わったら、私の部屋に来て。部屋の名前は――、『山茶花(さざんか)』。三階だから」
部屋の鍵からぶら下がった木の札を確認しながら、菱先生が席から立ち上がるところだった。私たちよりも先に、同行している教頭先生たちと離れたテーブルで食事を始めていた菱先生は、厨房のほうに「ごちそうさまでしたー」とよく通る声で告げてから、ぱたぱたとスリッパの音を響かせ、食堂から出ていった。
「何だろうね」
向かいの席に座る、同じ一年生の咲桜莉(さおり)が味噌汁のお椀をすすりながら、先生の後ろ姿を目で見送る。
「応援ポイントの話じゃないかな。スタジアムからひとりを最終区の途中に回したい――、みたいなこと、下見の帰りに先生、言っていたから」
なるへそ、と咲桜莉は味噌汁のお椀を置き、
「そう言えば、明日、雪が降るかもだって」
と漬物の皿に箸を伸ばした。
「そうなの? 嫌だなあ、私、寒いの苦手なんだって」
おいしい、これ、何ていう漬物だろう、と細かく刻んだ緑色の野菜の漬物をぽりぽりと齧っていた咲桜莉が「あ、忘れてた」と急に声のトーンを上げた。
「お母さんから、お土産に千枚漬を買ってきて、って言われてたんだ――。どこのお漬物屋で買うのがいいのかな? だいたい、不思議だよね。京野菜って言うけど、別に京都だけで育つ野菜じゃないでしょ? それなのに、『京』と頭につけるだけで高級感出るから、これぞ京都マジック」
すると、いつもはうるさいくらいにおしゃべりなのに、席についてからまったく言葉を発していなかった心弓(ここみ)センパイが、急にスイッチが入ったかのように「私もだ」と顔を向けてきた。
「おじいちゃんに甘栗、頼まれてるの。商店街のアーケードを出たところに、おいしい甘栗屋があるらしいんだけど、どっちの出口だろ? アーケードだって、二本あるみたいだし。新京極と寺町だっけ?」
そこから話題が伝播して、お隣のテーブルを巻きこんでの、各自が託されたお土産リストを紹介し合うコーナーが始まり、固い雰囲気が一変、思わずリラックスした空気が流れた。
「サカトゥーは何か、頼まれたの?」
柚那キャプテンからの質問に、
「お香です。有名なお香屋さんがあるみたいで――。でも、たどり着けるかどうか心配です」
と私が答えた途端、「ああ」という声にならぬ声が一同から発せられるのを聞いた気がした。
「咲桜莉、いっしょについていってあげな」
柚那キャプテンの声に、「了解であります」と咲桜莉がうなずき、「面目ねえっす」と私は半笑いで頭を下げた。
*
咲桜莉と並んでエレベーターの到着を待っていたら、柚那キャプテンの咲桜莉を呼ぶ声が食堂から聞こえてきた。
「何だろう、行ってくる」
別れ際、咲桜莉から鍵についた木札を見せられ、
「ウチらの部屋が『秋桜(こすもす)』だから、先生の『さざんか』も漢字かも。確か、どっかに『茶』が入っていた気がする」
というアドバイスを受けておいてよかった。
エレベーターで三階に移動し、「山茶花」の表札を確かめてから、ドアをノックして「坂東です」と告げると、
「入って」
という菱先生の声が返ってきた。
やけに声がはっきり聞こえると思ったら、扉の内側にロックを嚙ませて、開いた状態になっていた。
失礼します、とドアを開けると、正面に座っていた先生が、
「上がって。そこに、座って」
とうつむいたまま、手にしたペンで座卓を挟んで向かい側を示した。
スリッパを脱いで、そそくさと部屋に上がる。
私たちの部屋とほぼ同じ間取りの和室で、座卓の上には書類が並んでいる。私が部屋に入ったときから、先生は難しい顔で紙を眺めていたが、ようやく顔を上げると、
「そこの座布団、使っていいから。みんな、どう? 緊張してた?」
と部屋の隅の座布団を視線で示した。
「最初は緊張していましたけど、お土産の話で盛り上がって、結構、リラックスした感じになったように思います」
そう、とうなずいて、先生は私が座布団を敷くのを待っていたが、腰を下ろすなり、
「ダメダメ。正座は膝に負担がかかるから」
とさっそく注意が飛んできて、慌てて正座の姿勢を崩す。
「ココミは、どんな様子だった?」
座卓の上の書類を整理しながら、先生が訊ねてきた。
「心弓センパイですか?」
「ちゃんとごはん食べてた?」
隣に座っていた心弓センパイのトレーの様子を思い出そうとするが、記憶にない。気にならなかったということは、しっかり食べていたのだろう。
「たぶん……、食べていたと思います。そうだ、いつもと違って全然しゃべらなくて、でも、途中からは普通に戻って、お土産に甘栗を頼まれてる、って言ってました」
そっか、と先生は肘をついた姿勢で、こめかみのあたりにペンのお尻の部分を当て、ぐりぐりと押しつけた。あの陽気な心弓センパイでも本番を前にして無口になってしまうのだ、と改めて選ばれし走者の重責に思いを馳せていたら、
「ココミね。明日、欠場することになった」
といきなり先生の声が飛びこんできた。
「え、ウソ」
そう発音したつもりが、色を抜かれて声自体が透明になってしまったかのように、息だけが唇から漏れた。
「貧血の症状が収まらなくてね。ギリギリまで様子を見ようと粘ったけど、今日、午前中の試走のあとで、彼女のほうから出走を辞退する、って申し出があった」
「そ、そんな――」
心弓センパイが貧血に悩んでいることは知っていたけど、毎日一生懸命練習して、奇跡の大逆転で地区大会を優勝して、夢のまた夢だと思っていた「都大路を走る」チケットをゲットしたのに、大会前日にエントリーを取りやめることになるなんて、そんなのって。
改めて、食堂で隣に座っていたセンパイの様子を思い返す。きっと、とんでもないショックを抱えていただろうに、そんな気配はおくびにも出していなかった。確かに、咲桜莉がお土産の話を始めるまで無口ではあったが、話が盛り上がり始めると率先して、心弓センパイは各自のお土産事情を順に訊ねていた。みんなの緊張をほぐそうとしていたのだ。ああ、何て健気なんだろう、と涙腺が緩みそうになるのをグッとこらえる。
「わかりました」
気がつくと、私は座卓の上に両肘を置き、身体を乗り出していた。
「明日は、私たち一年生でちゃんと心弓センパイをフォローします!」
「違うって」
「え?」
「ココミじゃなくて、アンタの話」
ひっつめた髪のおかげで、あらわになっている額にしわが寄り、先生は何だか怖い顔になって、こちらを睨みつけた。
「ココミのことフォローするのは当たり前だし、一年生だけじゃなく、部員みんなでやることだから。それより、ココミの代わりに誰が走るのかって話。夕食の前にね、キャプテンとココミと三人で相談したの。代走に誰を立てるか――」
先生はひと呼吸置くと、こめかみにあてていたペンの尻を私の鼻先に向けた。
「坂東、アンタに決まったから」
一瞬、視界がぼんやりとして、それから自分に突きつけられた、ペンの尻に焦点が合った。
やわらかそうなゴムがくっついている。これ、文字が消えるボールペンだ、と素早く見極めると同時に、
「無理です」
と考えるよりも先に、声が飛び出していた。
「無理じゃない。そもそも、坂東は補欠で登録してるんだから。交替で出走しても、何もおかしくない」
先生は書類の下から、『全国高校駅伝』と大きく赤字で記された大会パンフレットを取り出した。付箋(ふせん)がつけられたページを開くと、そこに私たちの県の代表として、男子チームと女子チームがそれぞれ上下に分かれて紹介されていた。
確かに我が校の欄には、レギュラーメンバー五人のほかに、補欠三人の名前が並び、咲桜莉といっしょに私の名前も印字されている。でも、これはいわゆる「名前を貸しただけ」ってやつで、まさか本当に走ることになるなんて、夢にも思わないじゃない。
「む、無理です。だいたい、補欠には二年生のセンパイがいるんだし、一年生の私が出るのはおかしいです」
「普通ならそうなるわよね。でも、一年生を入れようというのは、ココミの希望だから。わかる? ココミは来年絶対に、ここへ戻ってくるつもりなの。来年のことまで考えて、一年生をメンバーにひとり入れて、本番を経験させるべきだ――、って。なかなか、言えないわよ、そんなこと。私もそこまで思いきったオーダー、ひとりじゃ、決めきれなかった。でも、ココミが言ってくれて、私も腹をくくった」
しゃべりながら、まるで一秒ごとに決意のほどが固まっていくかのように、部屋に入ったときは猫背気味だった先生の背筋が次第に伸びてきた。
「そ、それなら、咲桜莉が出るべきです。一年生でいちばんいい記録を持ってるし、十月の三千メートル走チェックでも、私より十秒以上、速かったし――」
「私は顧問よ。アンタたちの数字なんて、百も承知のうえで判断してるに決まってんでしょ。アンタ気づいてる? 一学期のときは咲桜莉に二十秒近く離されていた。それが夏休みでは十五秒差になって、十月の計測で十秒差まで縮めてきた。そこから二カ月経った今は?」
あとは自分で考えろ、とばかりに、先生はボールペンの尻で座卓の表面をコンコンと叩いた。
「そ、それに、私は超絶方向音痴なんです。いきなり、試走もしていないコースを走れといわれても――。先生、知ってますよね? 今日の下見でも、思いきり間違えたし」
「あれね……。アンタ、ワザとやったわけじゃないのよね?」
今日の午前中、レギュラー組が本番のコース確認を兼ね、試走している間、私たち一年生はスタートの西京極総合運動公園陸上競技場から烏丸鞍馬口にある折返点まで、菱先生といっしょにバスを乗り継ぎ、応援ポイントを決めて回った。
「きたおおじどーり、ほりかわどーり、むらさきあかるい? どーり、とりまるどーり、そこで折り返して、また、むらさきあかるいどーり、ほりかわどーり、きたおおじどーり。ああ、ややこしい」
折り返し地点を目指しながら、本番のコースを地図でたどるが、自分が歩いている場所も、通りの名前も、すべてがちんぷんかんぷんだった。
「とりまるじゃないよ、からすまる。よく、見なよ」
と隣を歩く咲桜莉から訂正の声が入り、「え?」と地図をのぞきこんだ。確かに「鳥丸通」ではなく「烏丸通」と表記されている。
「『烏』って字、『鳥』より横棒が一本、少なくて簡単なはずなのに、何でこっちのほうが難しい漢字に思えるんだろうね」
何気なしに私がつぶやくと、
「カラスは目が黒くて見えないから、『鳥』から目玉の部分を表す横棒が消えて、『烏』って文字になったらしいよ」
と咲桜莉が思わぬ豆知識を披露してきた。
「それ、本当?」
ちょっと、出来過ぎてる話じゃない? と遠足気分を隠せない私たちに、
「物見遊山に来てるんじゃない。それに『からすまる』じゃなくて『からすま』って読むから。それに紫明(しめい)通。むらさきあかるい、なわけないでしょ」
と先頭を進む菱先生から鋭い声が飛んできて、二人して「ヒエッ」と肩をすくめた。
「いい? 2区の後半と折り返してからの3区の前半、何度も角を曲がるから、ちゃんと応援ポイントの場所を覚えておくこと。これから担当決めるけど、アンタたち、明日は自力でここまで来るんだからね」
ほとんどの部員が小学校か中学校のときに、修学旅行で京都を訪れてはいるが、はっきり言って見知らぬ街である。明日はコースの途中じゃなくて、スタジアム組だったらいいな、それならば、センパイたちにくっついて旅館からいっしょに出発すればいいから、ゴールの瞬間も見ることができるし――、などとズボラなことを考えていたところへ事件は起きた。
「さっきの場所とこっちだと、どちらが視界、開けてるかな?」
折返点の前に声がけポイントを作るか、あとに作るか。前後のレースの流れをより見通しやすい場所を選ぶべく、
「ちょっと、坂東。さっきの場所に行って、チェックしてきて」
と菱先生からお役目を授けられ、私は「さっきの場所」を目指し、さっそくランニングで向かった。
そして、そのまま迷子になった。
十五分後、自分のいる場所がわからず途方に暮れているところを咲桜莉に発見され、菱先生から、
「何で一回曲がった道を戻るだけなのに、迷子になるのよ?」
と心底呆れられた。
「先生、サカトゥーは絶望的なくらい方向音痴なんです」
と咲桜莉がフォローになっているのか、いないのかわからぬ解説を挟んでくる。
そう、咲桜莉は正しい。
私は自他ともに認める「絶望的なくらい方向音痴」だった。
迷子になった理由は承知している。大きな通りを進んで、どちらかに曲がればよいとは知っていた。正解は左だった。しかし、右に曲がった。私は賭けに負けたのだ。
「こんな場所、通ったっけ?」
ほのかな疑いの念を抱きながらも、ずんずんとそのままランニングで邁進し、見覚えのない街並みに迷いこんでしまった。
もっとも、怪我の功名と言うべきか、後方から、
「違う、そっちじゃないッ」
と叫んでいたらしき咲桜莉の声は、烏丸通の車の往来の音に搔き消され、私の耳にまったく届かなかった。結果、道路幅の狭いほうが応援の声も通りやすいだろう、という気づきを先生が得て、声がけポイントがその後、正式に決まった。
そんな午前中の出来事を反芻(はんすう)しつつ、
「私、コースをちゃんと走れるかどうか、自信、ありません」
と改めて座卓に上体を乗り出し、菱先生に正直な気持ちをぶつけた。
地方予選大会のコースを部員全員で試走したときも、ところどころにある道路の分岐点を見るたびに、「もしも、自分が選手だったら、ゼッタイ道を間違える」と人知れずビビっていた私である。
「まだ誰にも言っていないですけど、昨日も迷子になりかけました。旅館にいちばん近いコンビニに行ったら、自分がどこにいるかわからなくなって――」
「いちばん近いコンビニって……。旅館の玄関から、見えてるやつだよね?」
「夜になると道が意外と暗くて、コンビニ側から旅館が見えなかったんです」
先生はひとつ、大きくため息をついてから、
「あのさ、本番で迷子になるとか、あり得ないから。沿道には人が大勢観戦しているし、他校の選手も走っている。だいたい、まっすぐ進んで、一回だけ右に曲がる。それだけのコースだから」
と手にしたペンの先で、宙に「L」の字を描いて見せた。
「え?」
「アンタの走るコースの話。2区や3区は何度もコーナーがあるから、曲がるときのテクニックもいるし、アンタは集中して走れないかもしれないでしょ? 4区は前半が上りだから、ここは上りに強い美莉(みり)をあてたい。1区はキャプテンが最初に気合を入れるから、柚那で固定。てことで、アンタが走るのは、ここ」
菱先生は手元の書類から、明日のコースが記された地図を引き抜くと、「第4中継所(西大路下立売)」と書かれた地点から、
「まっすぐ進んで、一回だけ右。迷いたくても、迷えない」
とペン先で競技場のイラストまで進めた。
「先生、これって……」
「坂東。5区、任せたから」
信じられない言葉に地図から視線を上げると、そこには部員からのいっさいの異論を認めぬときの「鉄のヒシコ」の顔が待っていた。
全国高校駅伝は男子が42・195キロを七人で走るのに対し、女子は半分の21・0975キロを五人でつなぐ。
つまり、私はタスキリレーのアンカーを託されたのだ。