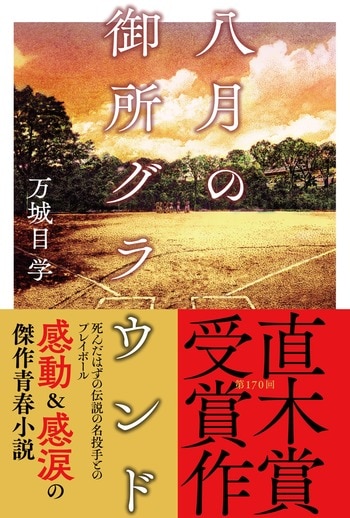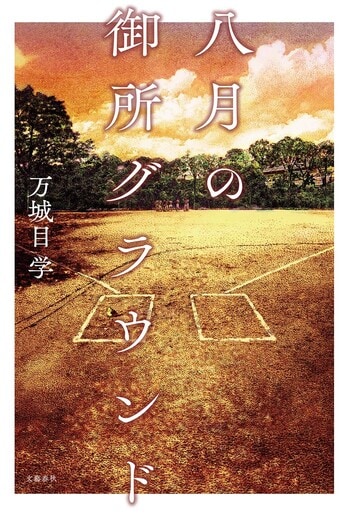「ホルモー」シリーズなどで知られる万城目学さんが約16年ぶりに原点・京都を舞台に紡いだ最新作『八月の御所グラウンド』が8月3日(木)、ついに刊行になります。
死者と生者の奇跡のような邂逅を描いた、感動の青春小説となった本作。
刊行に先立ち、本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、表題作「八月の御所グラウンド」の冒頭を先行無料公開します。
彼女にフラれ上、借金3万円のカタに、早朝の御所G(グラウンド)で謎の草野球大会に参加する羽目になった京都の大学生・朽木が出会った、“出会えるはずのない彼ら”とは――。
マキメ節全開の可笑しさでスタートする冒頭部分をお楽しみください。
八月の敗者になってしまった。
蟬の鳴き声がしゃあしゃあとやかましく降り注ぐ鴨川の河原沿いの道を、自転車に揺られて下(くだ)りながら、俺は痛感した。
本当ならば、川は川でも、四国にある四万十川で涼しげにカヌーを漕いでいるはずだった。
でも、俺は京都にいる。
なぜか。
彼女にフラれたからだ。
二人の関係が途絶した。彼女の実家がある高知に遊びに行く理由がなくなった。自然、楽しみにしていた四万十川の清流に浮かぶリクリエーションの機会も消滅してしまった。
かくして、俺は京都に取り残された。
気がつけば、まわりから人が消えていた。多くの者は実家に帰った。残りの者はフェリーにバイクを積み、北海道を目指した。就職前の最後のチャンスだからと、自動車教習所の合宿へ向かった。カンボジアにアンコール・ワットを見に行った。企業のインターンに参加すると東京に連れていかれた。
誰もが京都から脱出した。
賢明な判断だと思う。
八月を迎え、京都盆地は丸ごと地獄の釜となって、大地を茹で上がらせていた。百万遍(ひゃくまんべん)の交差点に立つと、あまりの暑さに信号が、大学のキャンパスを囲む石垣が、コンビニの看板が、ゆらゆらと揺れていた。学食で中華丼をかきこんでいたら、後ろの席で女子学生が、鴨川べりで座っていたら蜃気楼が下流のほうに見えた、京都タワーが浮かんでいた、と語っていた。
八月の京都の暑さに勝てる者などいない。
すべての者は平等に、ただ敗者となるのみ。
連日の炎暑にやられ、身体から力が抜けていく。脳みそからあらゆる前向きな意思や意欲が溶け出し、コンクリートに焼きついた影といっしょに蒸発していく。
誰かが、「京都は毒沼のようなものだ」と言っていた。そのとおりかもしれない。「ようこそどすえ」の笑顔に釣られ、碁盤の目の町に引きこまれたが最後、初々(ういうい)しかったはずの若者の心は、曖昧に、確実に蝕(むしば)まれていく。ただでさえ物理的サウナの如き町に暮らしながら、さらに瘴気(しょうき)が立ちこめる精神的サウナで心を整えること三年と四カ月と一週間。俺もすっかり毒気に当てられてしまったということか。四回生の夏休み、本来ならば目の色を変えて就職活動に励まなくては、いや、あがかないといけない時期なのに、すべてを諦め、バイトもせずにただ怠惰に日々を暮らしていても、へっちゃらな人間に成り下がってしまった。
夕方の六時が近いというのに、いっこうに暑さは落ち着く気配を見せない。町の空気は絶望的なくらいに粘っこく、Tシャツが背中にべたりと貼りつく。
八月の暑さに負け、京都という町にも負け、なぜ俺は額に汗かき、三条木屋町(きやまち)を目指して自転車のペダルを漕いでいるのか。
それは、多聞(たもん)が焼肉を奢ってやる、という連絡を急に寄越してきたからだ。
多聞は金を持っている。本人のアルバイトの稼ぎによるものなのか、それとも彼がボーイとして働いている祇園(ぎおん)のクラブのママさんからの小遣いなのかは、よくわからない。しかし、タダで肉を食わせてやるという誘いを断る手はない。
高瀬川に面した雑居ビルに入っている、指定された焼肉屋に到着すると、「おう、朽木(くちき)」と名前を呼ばれた。すでに多聞はひとり丸テーブルに陣取り、キムチをぽりぽりと齧りながらビールを飲んでいた。
「焦げたな」
それが俺の第一声だった。
記憶をたどるに、多聞と会うのは五月の終わりに百万遍の串カツ屋で飲んで以来、およそ二カ月半ぶりということになる。
坊主頭よりは少し伸びた短髪に、ほのかに無精ひげを生やす多聞の大きな顔は真っ黒であった。
「最近、毎日、プールに通っている」
Tシャツの袖からのぞく、ムラなく日に焼けた太い腕を多聞はさすった。
「プール? ひとりで?」
「いや、彼女と」
多聞はバイト先のクラブのママさんと付き合っている。確か、ママさんの年齢は二十九歳だ。ママさんには、形式上付き合っている金持ちの男性がいるのだという。でも、多聞とも付き合っているのだという。
「今日って、お前の奢りだよな」
席に着く前に改めて確認すると、「朽木に相談がある」と多聞はうなずきつつ、メニューを広げた。
「彼女がらみの話か?」
妙な関係だとは思いつつ、何だか祇園のおっかないところに触れてしまいそうで、彼女の話は深く掘り下げることなく、前回の串カツ屋会談は終了していた。
「教授がらみの話だ。研究室のことで、ちょっと聞いてほしいことがある」
「俺は文系だから、理系のことなんて全然わからんが」
多聞は理系学部に所属する五回生だ。学年は俺よりもひとつ上だが、年は同じ。つまり、彼は現役で、俺は一浪したのち、同じ大学に合格した。
「ビールでいいよな」
俺が向かいに座ると、多聞は手を挙げて店員を呼び、矢継ぎ早に飲み物と肉を注文した。
「そう言えばお前、四国に行くって言ってなかったか? ダメ元で連絡したら、京都にいたから驚いた。彼女にフラれたか?」
おそろしいほど核心を突いた指摘に、クーラーが利いた店内に入り、やっと引いてきた汗がまたじわりと滲(にじ)んでくる。
その後、運ばれてきたうまそうな肉を焼きながら、相手の相談を受けるはずが、なぜか俺が彼女にフラれた顚末(てんまつ)を語ることになった。多聞は大きな目をぱちくりさせつつ、要所要所で「おうっ」「おうっ」と妙な合いの手を入れ、俺の話を聞いた。
塩タンをロースターに押しつけ、己語りを続けていると、まるで自分のしみったれた話がそのまま肉の焦げ跡へと炭化していくような錯覚に陥った。「焼けろや、焼けろや」と自虐的な気分に浸りながら、端がカリカリになった塩タンを口に放りこみ、ビールで腹へと流し去った。十日前に彼女にフラれてから、栄養を摂取したらそれでよいとばかりに、納豆ごはんに生卵を投入したものばかりを食べていたので、ひさびさのちゃんと肉の味がする肉は、心底うまかった。まるで竜宮城に招かれた気分で、俺はプライベートの話を垂れ流す代わりに、ひたすら舌鼓を打ち続けた。
あらかたの話が終わったところで、
「なるほど」
と二杯目のビールジョッキを飲み干し、多聞はぷふうと上気した頰を膨らませた。
「何が、なるほどだ」
「お前のスケジュールはわかった。お盆のあたりまで何の予定もない。八月はずっと京都にいるということだ」
「何の話をしている」
「俺の話だよ。研究室のことで相談があると言っただろう」
多聞は店員を呼び止め、「おかわり」とジョッキを掲げて見せた。
「俺は五回生だ。留年野郎だ」
多聞はおもむろに自己紹介を始めた。
「知ってる」
「お前にはまだ言っていなかったけど、企業の内定をもらった」
「え、そうなの?」
いつの間に、と完全に虚を突かれた俺に、多聞は耳にしたことがあるような、ないような、カタカナの会社の名前を告げた。外資系のコンサルティング会社だという。
「よく、受かったな――。五月に飲んだとき、ひと言もそんな話なかっただろ」
破戒僧の如き野性的な顔に、ムフフと不敵な笑みを浮かべ、多聞はロースターの上に新しい肉をじゅうと並べた。
「そういうわけで、来年、俺は卒業しなくてはいけない。でも、今のままだと卒業できない」
「卒業式まで、まだたっぷり時間はあるぞ」
「問題は研究室だ」
多聞が説明するところによると、文系とは異なり、理系の学生は四回生の時点で研究室に所属することが必須なのだという。なぜなら、研究室にある機材を使って実験を重ね、そこで得たデータを元に卒業論文を作成し、それが教授に認められてはじめて卒業への扉が開かれるからだ。
しかし、多聞は五回生の留年野郎だ。四回生までほとんど学校に行かず、祇園バイトに精を出しつつ、ふらふらと過ごしてきた。いちおう研究室に所属してはいるが、実質、幽霊学生をこれまで続けてきた。
卒業するためには、幽霊から人間に戻り、卒業論文を書かなくてはならない。卒論の完成には、実験をサポートしたり、助言を与えたりしてくれる、研究室のメンバーの協力が不可欠だ。されど、頼りになるはずの同期の友人たちは軒並み卒業し、まわりは知らない後輩の四回生ばかり。そこで多聞、内定ゲット後は足繁く研究室に通い、後輩や院生たちの実験機材の清掃を進んで手伝い、心を入れ替えたことをアピールし、ひたすら周囲からの好感度をアップさせることに努めた。
すると、その働きぶりが目についたのか、教授から「おい、多聞君、メシに行くか」とじきじきに声をかけられた。
これは好機と、多聞は学生食堂にて企業の内定をもらったこと、ついては何としても来年卒業したい旨を直訴した。
きしめんをすすりながら、黙って話を聞いていた教授だったが、
「君のような男が、三年か四年にひとり、決まってウチに入ってくる。はっきり言って、僕は嫌いなんだ。君みたいな、勉強しないくせに、いいところだけ取っていこうとする怠け者が。この時期になって研究室に現れ、得点稼ぎに励むところまで、皆いっしょだよ――」
すべてお見通しとばかりに器を置き、ため息とともに口元を拭いた。
指紋でベタベタに曇った面の広いメガネのレンズの奥から放たれる、曇りなき眼差しの、その鋭さと冷たさに、思わず多聞は箸に挟んだチーズカツを取り落としそうになったが、そこで教授は急に表情を柔らかくした。
「ところで、多聞君、僕のお願いをひとつ聞いてくれないか――」
ふたたび器を手に取り、きしめんの残り汁を飲み干してから、教授は多聞に向かって、「お願い」なるものの中身について説明した。
「これは交換条件というやつだよ。もしも、僕のお願いを聞いてくれたなら、君に卒論の材料をプレゼントしよう。どうせ君は、卒論のテーマも決めかねているんだろ?」
限りなく図星の指摘だった。
「僕がやっている研究のなかで、データを揃えてほしい部分がある。道筋はほとんどできているから、あとは君が実験をこなせば、何とか君の卒論の体裁は整うだろう」
新たに運ばれてきた上ハラミ肉をトングでロースターの上に並べながら、
「いいのか? そんなやり方で卒論を書いても」
と俺は多聞の話を中断して、眉間(みけん)にしわを寄せた。
「ウチの研究室は、外部に卒論を公開しないからな。教授がそれでいいと言うなら、ルール違反じゃない。結果のめどはついているが、ちゃんと実験はするし、論文も書く」
「なるほど。で、何だったんだ? 教授のお願いって」
多聞はロースターの隅に見捨てられていたピーマンを引っくり返し、
「朽木は、野球できるよな?」
と低い声で訊ねてきた。
「はい?」
「野球だよ、野球」
「まあ、できると言えばできるけど……」
大学に入学したての頃、学部のクラス対抗野球大会があった。そのとき買った安いグローブがまだ下宿のどこかに眠っているかも――、とあやふやな記憶を口にすると、「十分だ」と多聞は満足そうにピーマンをタレ皿に運んだ。
「何で、急に野球が出てくるんだ?」
焦げ跡たっぷりのピーマンを「マズい」と顔をしかめながら食べ終えると、
「お前に三万円貸していたよな」
とまたもや話の矛先を変えてきた。
ほほう、と思わずおちょぼ口になる俺の前で、多聞は座禅中の坊さんのような凪の表情を浮かべ、「人間、借りた金は忘れるが、貸した金は忘れない」と穏やかに世の真理を説いた。
「あさってだ」
「無理だ。そんな急に用意できない」
「違う。あさってに試合がある」
「試合? 何の?」
「野球に決まってるだろ。お前は俺のチームの一員として試合に出る。まさか、三万円を借りっぱなしで、俺のお願いを断るなんてあり得ないよな」
ほら、俺は焦げた野菜を食うから、お前はもっと肉を食え。今日は俺の奢りだから――、と多聞は焼けたばかりの上ハラミを一枚、俺のタレ皿に運び、
「タダより高いものはないのだよ、朽木君」
と本日二つ目の世の真理を告げた。
*
教授のお願い、すなわち卒業との交換条件とは、
「たまひで杯で優勝すること」
だった。
たまひで杯とは何ぞや。
それは野球大会の名称である。
「野球? こんな溶けそうなくらい暑い盛りに、外で野球? 頭おかしいだろ。俺は絶対に嫌だ」
大丈夫だ、と多聞はやけに凜々しい顔でうなずいて見せた。
「朝六時にプレイボールだから、まだそれほど暑くなっていない」
「六時? 冗談やめてくれ。起きられるわけないだろ、そんな時間」
非常識極まりない話に猛烈な拒絶反応を示したのは当然の成り行きだったが、同じくらい当然の理(ことわり)として、俺に選択の余地はなかった。
三万円の借財に、豪勢な奢り焼肉の恩。
焼肉屋が入った雑居ビルから出ると、澱(よど)んだ夜の熱気に包まれ、高瀬川はいつも以上に存在感薄く、限りなく低い水位でもって日々の営みを続けていた。不意に彼女の、いや、元彼女のスマホで見せてもらった、四万十川のなみなみと水をたたえた風景が蘇った。青い空をバックに、川を左右から挟みこむ山々が鏡のように川面に映りこみ、そこに色鮮やかなカヌーが浮かんでいた。トレッキング帽子をかぶり、パドルを握っているはずの女性が、なぜかバットを構えている絵にチェンジしたとき、
「じゃ、あさって、御所G(ごしょジー)で」
と多聞に笑顔で肩を叩かれた。
目的を完遂した満足感からか、口笛などを吹きながら、バイト先の祇園へと向かう多聞の厚みのある背中を見送ってから、俺は帰路に就いた。
三条大橋から鴨川べりに降りて、川沿いに自転車を漕ぎ続けた。
人気のない道を川音に耳を浸されながらペダルを踏んでいると、妙にしんみりとした気持ちが寄せてくるから、夜の鴨川は苦手だ。
案の定、欄干の照明を受けて闇に浮かぶ賀茂大橋が見えてきたあたりで十日前、彼女に別れを告げられたときのことを思い出した。
思い出すも何も、そこが「現場」だった。
いつもなら、大阪から京阪電車に乗って出町柳(でまちやなぎ)で下り、叡山電鉄に乗り換えて下宿まで来てくれる彼女から、「出町柳まで出て来てほしい」と連絡があった。
予感がなかったわけではない。
それなりの兆しはあった。
けれども、これまで何度も遭遇してはやり過ごしてきた、いわば渋滞のような衝突のひとつであり、今度も知らぬうちにいつもの流れに戻るものだと思っていた。
でも、戻らなかった。
雨の土曜日だった。
出町柳の駅を出てすぐの場所にある、賀茂大橋のたもとで、傘を差した彼女が待っていた。
その場で別れを告げられた。
理由を教えてほしいと頼む俺に、彼女は長い沈黙を挟んだのち、
「あなたには、火がないから」
と暗い表情で俺の胸のあたりを指差した。
「燃えて灰になったものもない。最初から、ただの真っ暗。いや、真っ暗という色すらないかも」
彼女は俺と同い年だった。現役で大学に合格していたため、すでに卒業し、春から大阪で働いていた。社会人になって、好むと好まざるとにかかわらず鎧のようなものを少しずつまとっていく彼女と、就職活動を早々に諦め、何もかもが剝がれ落ちていく自分との間に、溝のようなものが生まれているのは感じていた。
たとえば、時間への感覚。彼女が休日に計画していたことが、俺の寝坊でご破算になったときの、彼女の全部をあきらめたような暗い眼差し――。
橋の欄干に手を置くと、雨に濡れた冷たい石の感触が伝わってきた。雨雲を映して不愛想な表情になっている鴨川の流れを見下ろし、四万十川に行く日程はなくなったのだな、とそこではなかろう、ということをぼんやりと考えた。
「嫌いになる前に別れる」
目をそらさずに告げた彼女から、逃げるように先に目をそらしたのは俺のほうだった。
聴覚にも、視覚にも、まだ生々しく蘇る記憶をたどりながら、河原から賀茂大橋に上ったが、別れを告げられた場所を通るのが嫌で、道路を隔てて反対側の道を選択して橋を渡った。
あの日から、彼女からの連絡はない。俺も連絡していない。彼女が口にした別れの理由を、俺は正確に理解できないままでいる。言わんとするところは何となくわかる気もするが、ならばどうしたらよいのか、と考えると、すぐに袋小路に迷いこんでしまう。今の自分の状態をもちろん肯定はしないが、「火がないから」と言われても、自分では確認のしようがない。
焼肉屋で、どういう意味なのか、と多聞に意見を求めてみても、
「わからん」
とけんもほろろに返された。
「でも、俺にもその火はないのだろうなと薄々感じる。お前が俺に質問すること自体、間違っているよな、とも感じる。ま、焦ったところで、すぐには点(つ)くもんじゃないだろうな」
下宿に帰るなり、玄関脇の靴箱を開けてみた。
照明の光が届かない隅に、影と一体化したように黒いグローブが突っこんであった。三年ぶりだろうか。引っ張り出して左手を入れてみる。意外なくらい、指に馴染んだ。グローブの内側には、土に汚れた軟球がいっしょに挟まっていた。
社会人になってはじめての夏休みを俺と過ごす、という選択肢を彼女は拒絶した。
その結果、俺は京都に残され、四万十川を気持ちよくカヌーで漕ぎ回る代わりに、野球をする羽目になりそうである。
ボールを指と手のひらを使って回しながら、早朝の六時から多聞と野球をやっている自分を想像してみた。
掛け値なしに最悪だと思った。