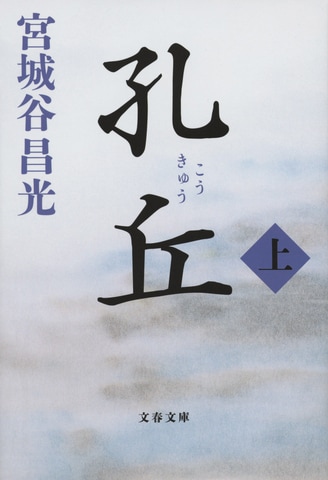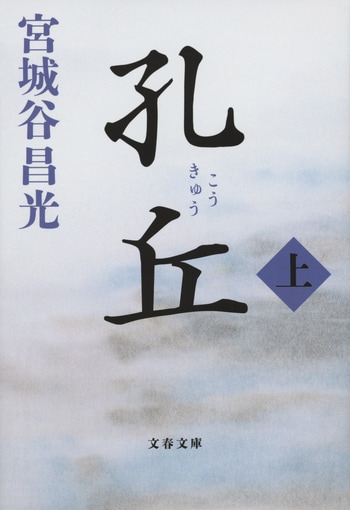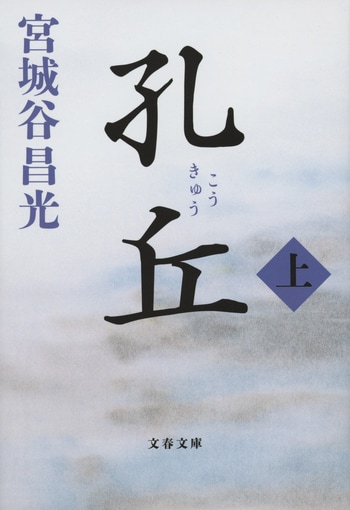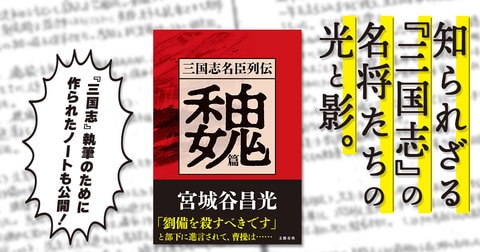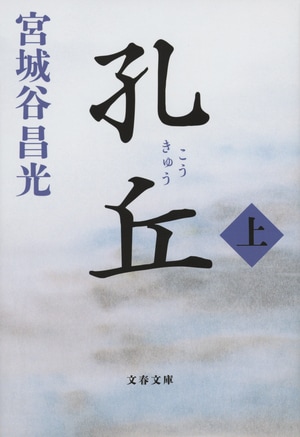

《もし、どなたか、孔子の伝記を材料にして小説でも書かれるような時、いままでのように六十になって、七十になって、ますます徳が盛んになったという超人間では、小説になるまいと思います。(略)孔子には先覚者に免れえない孤独感があった。そこを摑まなければ、孔子は生きてこないと思います》(「論語の新しい読み方」一九六九年)――東洋史学の泰斗・宮崎市定が書き遺した言葉だ。以来半世紀余が過ぎ、ようやくこの期待に応える作品が出現した。本書『孔丘』である。著者は「あとがき」に《神格化された孔子を書こうとするから、書けなくなってしまうのであり、失言があり失敗もあった孔丘という人間を書くのであれば、なんとかなるのではないか》と記している。書名は孔子(尊称)でも仲尼(字)でもない。通常避けられる孔丘(本名の呼び捨て)を用いたところに、素の孔子と向きあう著者の覚悟のほどが窺える。
孔丘(紀元前五五一年~紀元前四七九年)が生きた春秋時代末期は、大混乱の時代だった。周王朝の権威は地に落ち、晋、斉、楚、秦などの大国が主導権争いを繰り返す。多くの国で、国王は名目のみの存在となり、大夫(上級貴族)が実権を握っている。母国魯では、国君(昭公)が大夫に追われ亡命七年のあげく客死した。が、大夫とて盤石ではない。「陽虎の乱」に描かれるように、大夫を支えるはずの士(下級貴族)が独裁政治をほしいままにしている。この下剋上の実態を知らずして、孔丘はとうてい理解できない。古代中国を描き続け、春秋戦国に通暁する著者は、簡にして要を得た筆致で時代背景を活写する。結果、孔丘がなぜ「礼」を説いたか、なぜそれが人々の心を揺さぶったか、なぜ孔丘は挫折し亡命せざるをえなかったか、時代の必然が生んだ孔丘の像が鮮やかに浮かび上がってくる。
人間孔丘を描きだすことは、聖人孔子を描くよりずっとむずかしいだろう。何しろ人生の事跡そのものが不確定なのだ。出生ひとつとっても、専門家のあいだで、「農民の子」(加地伸行)「下級士族の子」(木村英一他)説が対立し、「父なし子として母の手で貧賤のうちに育てられた」(金谷治)、「母と別れ父方で過ごした」(加地伸行)と見解が違っている。最初の伝記である『史記 孔子世家』は「出色の出来栄え」(貝塚茂樹)という称賛と、「『史記』のうちでも最も杜撰なもの」(白川静)とする見方に分かれるし、いつどこで語られたかが定かでない『論語』の語録は、後世の潤色や創作も多い。孔子本人の言葉かどうか、その意味をどう解すべきか、諸説入り乱れ異なった解釈が無数にある。
宮城谷氏は、蓄積してきた知見を総動員しつつ、孔丘の事跡を確定してゆく。いつ、どこで、何をしたか? それを明らかにすることと孔丘を知ることとは相同じ。一例をあげよう。本書における孔丘は、成周(周の都)に留学、老子の塾に入門し六年余にわたって教えを乞うている。『史記』に記された成周への留学は「道家が流行してからのちに、孔子と老子とを結びつけるために作り出した一場の作り話にすぎない」(貝塚茂樹)、「老子を持ちあげるためにあとから作られたことで、事実ではない」(金谷治)と断ずる説がある。しかし著者は孔丘にとって留学こそが不可欠な体験だったと考える。老子は老先生の意で後年の書『老子』とは無関係であり、この老子は元・周王室文庫の司書だった、と。留学先で四十歳を迎えた孔丘は、老子の教えによって「周文化がもっともすぐれている」と惑わず確信する。孔丘の周文化へのゆるぎない信頼は、こうしてその根拠を示される。それ以上にハッとさせられるのは、留学先で孔丘が《かつて得たことのないものを得たのである。/それは学友である》という指摘だ。『論語』冒頭「朋あり遠方より来たる また楽しからずや」の「朋」は学友を指している。孔丘に弟子はいても友人を持つ機会はなかったはず。いったいどこで学友を得たのか。それは老子に学んだ成周以外考えられない。かくして留学の叙述はリアルに生き生きと訴えかけてくる。
本書の比重は、老境以前の孔丘に置かれている。やがて孔子になる孔丘にぴったり寄り添うように。いきおい、仲由(子路)を除けばあまり知られていない最初期の弟子が多数登場する。閔損(子騫)、秦商(子丕)、顔無繇、漆雕啓(子開)……なかでも、特筆に値するのは漆雕啓の存在である。七章「儒冠と儒服」から現れ、最終三十六章まで常に顔を出す(最多登場)。漆雕啓の存在によって、孔丘も読者もどれほど救われていることか。あの愛すべき快男児、仲由(子路)――「われらはどこにいても、どんな境遇になっても、楽しむ、ということを先生から教えられた」と賛嘆を惜しまなかった仲由ですら、十四年におよぶ多難な亡命生活において、「なあ、子開よ、あんな先生でも、これからもわれらは守っていかねばならないのか」と不満を口にしている。漆雕啓は違う。「死人とかわりがない」ように見える孔丘に寄り添い、人間孔丘の深い悲しみを察している。漆雕啓は著者の分身であり、孔丘の孤独の最も良き理解者だといえよう。
孔丘には、一貫して変わらないものがあった。冒頭「盛り土」の章に書かれた《すべての人が師であった。どのような境遇にあろうとも、死ぬまで学びつづけるという心構えは、まさしく死ぬまでくずれなかった》という姿勢である。これに類した表現は、最終章に至るまで何度も何度も繰り返される。これこそが人間孔丘を凡人から隔てるものであって、本書を貫く軸はここにある。作者は孔丘に伴走しながら、「学びて厭わず、人を誨えて倦まず」(『論語』述而篇)といった姿勢に出会い、そのつど、作家としてのわが身をかえりみたのかもしれない。
孔丘の結婚生活を直視しているのも本書ならでは。孔丘は離別する妻に「あなたには、弱い者の悲しみが、わからないのです」と言われ、息子孔鯉には「父は母をいたわりもせず、いびりだした」「女と子どもをいたわらない者が説く礼は、本物か」と不信を抱かれる。父母の愛にも妻との愛にも恵まれなかった孔丘は、家庭人としては失格者だった。著者は《妻の悲しみも、鯉の悲しみもわからぬはずがない孔丘の悲しみを、たれがわかってくれるのか》と記している。このとき孔丘三十歳、『論語』にいう而立の年だ。彼がせっかく得た官途の職を辞し、自らの教場(私塾)開設を決意した年に当たっている。従って、「三十にして立つ」は、ふつう「学問的に自立し」(桑原武夫)と解される。だが、光があれば影がある。《ひとつの大事がはじまろうとしているのに、いまひとつの大事が竟わろうとしている》――学問的自立は、家庭生活への生涯にわたる訣別の告知でもあった。
誰もが驚くのは「仁」をめぐる陽虎とのやり取りであろう。この挿話は『論語』陽貨篇(陽貨と陽虎は同一人物)冒頭にあるのだが、解釈は他の注釈書と天と地ほど違っている。
『論語』の書き下し文を見てみよう。岩波文庫版(金谷治訳注)の陽虎とのくだりは「曰わく、其の宝を懐きて其の邦を迷わす、仁と謂うべきか。曰わく、不可なり。事に従うを好みて亟〻時を失う、知と謂うべきか。曰わく、不可なり」である。本書では、この問答を以下のように描いている。
《陽虎の目は孔丘をとらえて、はなさない。
「宝をいだいていながら邦を迷わせたままにしておくのは、仁と謂うべきであろうか。もちろん、仁とはいえない。政治に参加したいのに、たびたびその機会を失うのは、知というべきであろうか。もちろん、知とはいえない。月日は逝き、歳はとどまらない」(略)
孔丘は衝撃をうけた。ただひとつ、
「仁」
ということばに、である。陽虎はどこでそのことばをみつけたのか》
続いて《仁の意味がわからない孔丘は、陽虎におくれをとったおもいで、くやしさがこみあげてきたが、あえて冷静に、
「いつかお仕えするでしょう」
と、答え、仲由の腕を軽くたたいて馬車をださせた》
とある。
「人として正しい在りかた」「人としての本分」(本書)を意味する「仁」。吉川幸次郎(『中国の知恵』)によれば、『論語』の「全四百九十二章のうち、五十八の章に百五度この字が現われる(略)この書物の最も重要なトピックは、やはり『仁』である」とされ、この見方は諸家も一致している。「仁というのは、孔子が発明した語であるらしい」と白川静は指摘しているし、孔子の「基本理念」(井波律子)、「最高の徳目」(金谷治)といった「仁」の位置づけは変わらない。ところが、本書における孔丘は、人もあろうに陽虎から、はじめて「仁」の言葉を聞き、その意味がわからなかったというのだ。孔丘はすでに四十代後半になっている。それまで「仁」を知らず、その後、専売特許のように「仁」を標榜することなど、ありうるだろうか。
一見、荒唐無稽に映るこの挿話は、読者の心に強く残るにちがいない。ここに本書のもうひとつの鍵がある。
「曰わく、其の宝を懐きて其の邦を迷わす、仁と謂うべきか。曰わく、不可なり」――二度繰り返される「曰わく」は、本書では陽虎の自問自答とされている。それは金谷治をはじめ、木村英一、宮崎市定等の解釈と同じだ。けれど、現代語訳には別解がある。たとえば井波律子訳(カッコ内表記は井波訳・原文のママ)。
《「(あなたは)宝のような才能を持ちながら、(それを活用せず)国を混迷させている。それは仁といえますか」。(先生は)言われた。「いえませんな」。》《「政治にたずさわることを希望しながら、しばしば時機を失しておられる。それは知といえますか」。(先生は)言われた。「いえませんな」》と、陽虎と孔子とが問答をかわすかたちだ。井波訳(吉川幸次郎、貝塚茂樹、加地伸行の現代語訳も同様)のほうが通説のようで、この場合、陽虎が孔子に、「あなたは日頃しきりに『仁』を説いておられる。しかしあなた自身はどうなんですか」と問いかけ、孔子は一本取られたことになる。
が、どちらの解釈を取るにせよ、陽虎と孔丘とのあいだで「仁」は「すでにあるもの」であって、お互いの了解事項とされてきた。それでは「仁」が生きてこない、作者はそう考えたのではないだろうか。「仁」を既成の概念から解き放ち、孔丘の肉声のように響かせることはできないか、と。本書の独創はここにきわまる。宮城谷氏は、「仁」を陽虎に語らせることで、これまで誰も想像しえなかった、孔丘の内面のドラマを描き出した。「仁」を小説化し、「仁」に生命を与えたのである。
こうして、「仁」は聖人の抽象的な言葉から、人間孔丘のリアルな言葉に変貌する。たとえば「仁」の一面とされる有言実行、言行一致は、「過ち」に向かう孔丘の言行によって、きわめて具体的な様相をおびてくる。陽虎に「やられた」「またしても侮辱された」と自ら認めているように、孔丘は陽虎に対しぶざまな失態を演じ、やがて失態を挽回する。『論語』里仁篇「過ちを観て斯に仁を知る」は、通常「他人の過ちを見ればその人の仁の程度がわかる」と解されている。しかし、本書の叙述をふまえれば、「過ち」を犯したのは孔丘自身であり、陽虎に「仁」を教えられたと読みかえることができる。そして、『論語』における「過ち」の語録は、すべて、孔丘の失態と内省と努力と実践に裏打ちされる。「過ちあれば、人必らずこれを知る」(述而篇)、「過てば則ち改むるに憚ること勿かれ」(学而篇)、「過ちて改めざる、是れを過ちと謂う」(衛霊公篇)等々、孔丘の体験談を聞いている気分になる。
陽虎と「仁」の関係はさらに重要である。著者は、初版刊行後、朝日新聞のインタビューに答え「下卑た言葉で言うと、孔子は(陽虎から仁を)パクったわけです」と韜晦気味に語っている。だが「パクリ」の語を決して軽く見てはいけない。「パクリ」こそが孔丘の真髄であり、「述べて作らず」も「温故知新」も、きわめて高度な「パクリ」の表明といえるのだ。
本書によれば、《徳を利害からはなして、個人の倫理的あるいは人格的成熟として示した》のは孔丘であった。葬儀の手続きにとどまる「礼」(小人の儒)を高次の「礼」へと引き上げたのも孔丘。族長と同義だった「君子」の語を、理想的人格者を指す意にしたのも孔丘。《陽虎が考えている仁よりもはるかに抽象度が高いことばとして仁をすえなおす》(本書)こと、まさしくそれは「パクリ」の発展型、完成型であり、到達点を指しているではないか。
孔丘と陽虎は宿命の対立関係にあった。本書に詳述され、白川静が「自己の理想態に対する否定態としての、堕落した姿を、孔子は陽虎のうちに認めていた」(『孔子伝』)と書いているように。そもそもの出会いは、母の喪中だった二十四歳、孔丘の仕官の契機を陽虎が奪ったときだ。孔丘は陽虎を怨み、「あの男を超えてやる」と心に誓う。《あの男を超える、ということは、あの男に詆辱された自身を超えることにほかならない》とも書かれている。はるかな歳月を経て、孔丘はこの思いをみごとに成就した。「仁」の換骨奪胎によって。胸のすく、何という鮮やかな逆転劇であろう。
後年の書『孟子』には、「陽虎曰く、『富を為せば仁ならず。仁を為せば富まず』と」という言葉が残されている。いかにも陽虎が言いそうなセリフで、陽虎は当然のごとく「仁」よりも富と権力の座を選んだ。孔丘は陽虎から「仁」を奪い、「仁」の意味を最大限拡張した。至上の価値を与えた「仁」によって、孔丘は「怨み」を超え、陽虎を超え、自身を超えた。