飛行機事故での逝去から今年で40年。今なお向田邦子の作品は愛され続けている。
脚本から小説へと進んだ向田作品の原点は、いったいどこにあったのか――
お礼状でもう一回椿餅が
伊吹 今日はお目にかかることができ、とても光栄です。自宅から向田先生の御本も何冊か持ってきました。
向田 うちの姉は「先生」っていうタイプではないから、「向田」にしてください。きっと居心地悪いって言いますよ(笑)。
伊吹 それじゃあ「邦子さん」ってお呼びしちゃおうか……いや、それも恐れ多いので、「邦子先生」では?
向田 いいんですよ、「邦子さん」でも「お姉さん」でも。
伊吹 かえって緊張するので、せめて「向田さん」にします(笑)。私と向田さんの初めての出会いは、小学生時代にテレビで偶然にみた、『阿修羅のごとく』(一九七九年/NHK)でした。パート1の「虞美人草」の回で、母親が夫の愛人のアパートの前に立っているところを娘に見られ、倒れてしまうという場面だったんですが、その母親の買い物かごに入っていた卵が割れて、黄身がどろっと流れ出すというのが、子供心にもすごく強く残って。あのシーンでは有名なトルコの軍楽曲が鳴っていたイメージをずっと持っていました。
向田 『阿修羅のごとく』というと、皆さんトルコ軍楽曲(ジェッディン・デデン)が頭に鳴っちゃうんですよ。

伊吹 ところが今回、対談にあたってアーカイブで見直してきたら、あそこで音楽は入っていなかったんです(笑)。大人になって改めて見ると、その後で母親が亡くなり、ラストシーンで喪服姿の四姉妹が振り返る場面が印象的で、まさに「女は阿修羅だ」と唸らされました。もちろん子供の頃はそんなことは考えず、ただ、ビックリさせられたことだけはずっと覚えていて。飛行機事故で亡くなられた時の衝撃も大きかったです。活字で初めて向田作品に出逢ったのは、高校時代、友人が誕生日に贈ってくれた『寺内貫太郎一家』(新潮文庫)でした。
向田 『阿修羅』と『寺貫』とは、ずいぶん対照的ですね。
伊吹 その差にとても惹かれまして。さらにもう一回、夢中になって拝読するようになったのが、就職して出版社に勤め出してからです。
向田 姉も若い頃は出版社(雄鶏社)に勤めていました。基本的には編み物の本がメインで、唯一の映画雑誌の編集に携わっていたんですが、作家になるきっかけがそこにあったのかどうか、私にはよく分からないんです。ただ、昔から文章を書くのはうまくて、保険会社に勤めていた父のところへ届く盆暮れの贈り物へのお礼状を、代わりに書いたこともありました。食べ物のことだったから、私はよく覚えているんですけれど、ある時、送られてきたお菓子が椿餅で、届いた時には箱の中で偏って、形がペシャンコになっていたんです。それでも美味しくて、姉がお礼状を返したところ、その内容に感動した送り主が、もう一回、今度は完璧な形の椿餅を送ってきてくれました。その時に「お姉ちゃん、手紙を書くのがうまいんだな」と(笑)。
伊吹 想像するに椿餅のおいしさや、葉のつやつやした感じとお餅の組み合わせの妙をお書きになったうえで、「残念ながら傾いていたのもまた一興」みたいな感じで書かれたのかな。

向田 父は筆まめなほうで手紙を代筆させるようなことはあまりなかったんですが、とにかく姉はそういうところは機転が利くんです。あとは小学校の夏休みの日記なんかも、私が何も書いていないのにへっちゃらでいるのを知ると、嬉々として代わりに書いてくれました。
伊吹 あまりに上手すぎて、逆に困ることはなかったですか。
向田 中学に入ってからも私の作文を代わりに書きたがって、それを提出したところ随分褒められたので、さすがにまずいと思って止めました。だけど、中学三年生の三学期に私が入院し、試験と宿題の作文が重なってしまった時だけは、姉に作文を頼みました。出来上がったものを一読して「私にはこれは書けない」と、はっきり分かりました。特に難しい言葉は何も使われていないのに、そこには色彩があって、本当に胸に詰まる作文でした。それ以来、姉に代わりに書いてもらうのは、一切止めたんですが、懲りもせずに書きたがるんですよ。私の就職試験の時に出された課題にさえ、「私が書いてあげる」と嬉しそうに言うんです。
伊吹 向田さんはそれを楽しんでいらっしゃったんだと思うし、私だったらお願いしてしまいそう(笑)。
向田 そもそも就職試験自体を姉のコネで受けさせてもらっているわけで、さすがにそこまで呑気ではいられません。丁重にお断りしました(笑)。
作家になるまでの修業時代
伊吹 私は文字を書くのが昔から好きで、父の持っていたインク壺につけて書くタイプのペンが、ずっと欲しかったんです。十歳になる頃、それを譲り受けてからは、そのペンで文字を書くことが、とにかく嬉しくて。読書も好きでしたが、ペンをもらってからは、読むだけにとどまらず、音の響きやリズムの好きな文章をまねて、他愛のないことを書くのに熱中しました。ペンで文章を書いていると、大人になれた気がしたんです。
向田 同じ作家でも全然違います。私は家で姉が本を読んでいるところを、一回も見たことがない。
伊吹 こそっと大人の本を、読まれていたのでしょう(笑)。
向田 高校時代、真夜中に起きると、姉の部屋の欄間から光が漏れてきて、「まだ勉強しているんだ」と思ったことはありましたが、本を読んでいる姉の姿は想像できないですね。家に帰ってくるといつも働いていて、そうでなければ父に付き合って、トランプをやったり麻雀をやったり、花札をやったり(笑)。当時を思い起こすと、やはり将来物書きになるというイメージは全くなかった。
伊吹 私は小学校二年生の頃の文章を見ると、「絶対に小説家になります」と書いているんです。作家はものすごく憧れの職業だったんですが、私の周りには、東京や大阪や京都などの大都市と違って、プロの文筆家はいませんでした。それこそ作家になるのは、「ハリウッド女優になる」とか「宇宙飛行士になる」くらい縁遠いことだと思っていまして。そんな雲をつかむようなことを考えていないで、手に職をつけなきゃ、と。弁護士資格を目指すことを決心し、法律の勉強をするために上京したんです。ところが大学に入学して、法律を学び始めたらそれは向いていないことが、すぐに分かりました。
向田 変な言い方ですけれど、「向いていないこと」が分かったのは、伊吹さんにとってラッキーだったかも(笑)。
伊吹 そうなんです。民法の離婚や相続の問題を扱う分野は興味深かったし、刑事ドラマが好きだったので刑事訴訟法や刑法ならしっかり勉強できるかとも思ったんですけど、法律の議論に参加しても、たいした意見も言えず、場の雰囲気を味わっているだけになってしまう(笑)。在学中の司法試験は全然で、名古屋の法律事務所で働きながら司法試験にチャレンジしようと一度は決めました。
でもやっぱり本や雑誌に関わる仕事がしたくて、駄目でもともとで出版社を受けたところ、採用してくれる会社があったんです。そこで、自分は出版の世界に入って編集者になるんだと思っていたら、最初は販売促進関係の部署に配属されまして。現在でも交流が続いているほど人には恵まれたものの、やはり色々と迷うこともあり、脚本の勉強をはじめました。この時期に、向田さんのシナリオと改めて向き合うことになったんです。やはり『阿修羅のごとく』はすべての要素が入った、緊張感のあるもので圧倒されました。







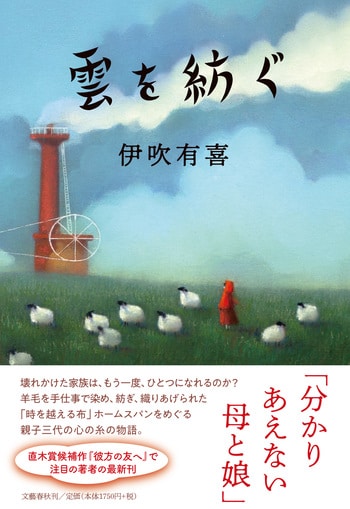




![[第8回 高校生直木賞全国大会レポート]四時間かけた議論の末“同票”で史上初の二作受賞](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/8/e/480wm/img_8ecbfa907f82de0fc58fac5476017aaf219466.jpg)










