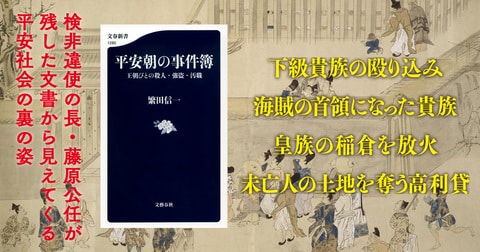世界初の女性作家による小説
『源氏物語』は世界で最も早く書かれた本格小説作品である。世界の文学史をみるとき、最初期に出てくるのは、韻文形式の叙事詩やギリシャ悲劇などの演劇であり、私たちが小説と呼ぶようなものはヨーロッパでは十八世紀から十九世紀になってようやく成立するのである。しかも作家はもっぱら男性が占めており、たとえば、イギリスでジェーン・オースティンなどの女性小説家が出てくるのは十九世紀になってからだった。
世界的な文学状況がこのようなものであったなかで、『源氏物語』は、十一世紀初頭という非常に早い段階で、しかも女性作家の手によって書かれた小説だというので、一九二五年に『源氏物語』がアーサー・ウェイリーの手によって翻訳されると、女性作家のヴァージニア・ウルフなどは、こんなにも昔にこんなにも素晴らしい小説を書いた女性がいるなんて! とびっくり仰天してイギリスの雑誌『Vogue』に感想を寄せたのだった。
『源氏物語』は説教のための説話や子供だましのおとぎ話でもなく、歴史物語や戦記でもない。男女の恋愛を中心に置き、細やかな心理描写のもとに、人々の生活の機微、季節の美しさやうつろいが語られる人間ドラマで、主人公光源氏の生まれる前から、死後の孫の代までの長大な時間を描いた宮廷ロマンである。
優れた作品は、こうしたものを楽しみに読むような読者層の存在なしには成り立たない。囲炉裏端で誰かが話す昔話や役者が演じる演劇などと違って、書記言語による小説が成立するには、書き言葉を解する読者の成立が必須であり、読み書きの教育が行き渡る必要がある。
とすると、平安宮廷は、多くの人々が読み書きができ、作品を作り、読むことができるような教養のある文化的社会であったということになる。平安宮廷の大学寮などの学問所は、男性官人しか学ぶことができなかったのだが、どの国の貴族社会もそうであるように、貴族たちは学校というシステムに依らず、家庭教師によって学問や和歌を詠むこと、楽器の演奏などの素養を身につけていた。そのようにして『源氏物語』が生まれた平安宮廷社会には、たいへん豊かに成熟した文化基盤が築かれていたのである。
物語のあたらしい文体
平安宮廷社会は中国を範としていたので、学問とは漢学すなわち漢文で書かれた文献の読み書きができ、漢詩文をつくることができるようになることだった。したがって書記言語として第一には漢文があり、平安宮廷の公式文書は漢文で書かれていたのである。それは男性官人の職務であり、公式文書ではない私的な日記においても男性が書く文書は漢文で書かれていた。たとえば藤原道長が残した日記『御堂関白記』も、同時代に活躍した官人藤原行成の日記『権記』などであっても、すべて漢文体で書かれているのである。漢学は男性官人だけに入学の許された大学寮などで勉強するものだったので、女性には学習機会がないかというと、そういうわけでもない。
紫式部の父親は漢学を専門とする文人で、宮廷社会で漢文を教える立場にいる人だった。紫式部の家にはたくさんの漢文の本があり、大学寮などに通わずとも多くのことを学べる環境にあった。それは紫式部に限った話ではない。当時の貴族階級の女たちには程度の差はあったにせよ、そのようにして家庭で漢学を学ぶことが可能だった。宮廷では宴会の余興として、男性官人たちが漢詩文を作ったりしていたが、そこに女性の作もあることが知られている。
天皇の勅命によって作られた和歌集を勅撰和歌集と呼ぶが、実は、最初に作られた勅撰集は漢詩文集だったのである。それに対して、やまと言葉によるやまとうたである和歌をまとめようという気運が起こり、最初に作られたのが『古今和歌集』だった。以後、勅撰集といえば和歌集をさし、連綿と勅撰和歌集がまとめられるようになっていく。このようにそれまで漢文という書き言葉で行われてきた漢詩という文学活動が、いわば口語であるやまと言葉による和歌に置き換わっていく波に並行して、やまと言葉で書かれた物語作品が陸続と現れるようになるのである。
ただし公式文書が漢文で書かれること自体が廃れたわけではなかったので、平安宮廷社会は、書記言語として、漢文の文体と和歌や『源氏物語』などの物語を書くためのやまと言葉の文体との二様の文体を使い分けていた。
この漢文調の書き言葉は話し言葉とは関わりがない。したがって時代による変化を受けることがない。時代に影響されないという意味で書き言葉としての漢文訓読調の文体は息が長く、近くは戦後になるまで用いられていた。昭和時代の法律の文章、聖書の訳文などをみてみると相変わらず漢文訓読調で書かれていたことに気づくはずだ。
私たちがいま明治時代の森鴎外や夏目漱石などの小説を読めるのは、言文一致運動があったおかげである。明治時代になって西洋文学に学んだ知識人たちは、江戸時代の戯作調の文体や文語と呼ばれる漢文訓読調の文体とは異なる、もっと日常語に近い、いわゆる口語体の文体を模索し、それによって新しい小説を生み出していった。
同じようにして平安宮廷社会では、書き言葉の漢文体ではなく口語体にあたるやまと言葉による文体をつくりあげたわけである。言文一致をめざす運動それ自体はたしかに明治時代のものではあるが、平安時代にも口語体による物語の文体があらたにつくられたのであり、言うなれば平安時代にすでに一度言文一致の動きがあったのである。口語体だからこそ、物語には、平安貴族たちの日常の声の調子、会話文などが取り込まれており、私たちはいまなお平安時代の人々の声の残響を聞くことができる。
女の名前
ところで紫式部については、名前も生没年もわかっていない。紫式部というのは宮中での女房名で、和泉式部などと呼ぶのと同様、父親か兄弟が式部省(1)の役人だったことから付けられている。紫は『源氏物語』の登場人物の紫の上にちなんでいるらしい。『栄花物語』には「紫」と言及されている。
当時は貴族であっても、天皇の后や母にでもならないと女の名前が記録されることはなかった。たとえば『蜻蛉日記』の作者が藤原道綱母と呼ばれ、『更級日記』の作者が菅原孝標女と呼ばれているのは、息子や父親の名前しか記録に残っていないためである。記録に残らないというだけで、むろん女たちにも名前はあった。男女ともに幼名と成人してからの名前と二つ持っていることが多かったらしい。『落窪物語』で継母にいじめられている女主人公を助ける女童(2)があこきと呼ばれ、『源氏物語』で紫の上の幼い頃の遊び相手となっているのがいぬきと呼ばれているように、あこき、いぬきなどは童名である。その後、成人の際に新たな名がついたはずだが、女房として仕えたときには、親兄弟の役職に由来して中将の君、中務の君などと呼ばれて、結局、どのような名前がつけられたのかはわからない。
ただし天皇に入内(3)した女たちの名前はわかっていて、たとえば一条天皇の后である定子や彰子というのがその名である。皇后の例からみると子のつく名前が主流であったように想像されるが、たとえば『源氏物語』で玉鬘と通称される女君は藤原瑠璃という名だと書かれており、瑠璃という名もあったようである。
ただし現在でも漢字の名をどのように読ませるかにはさまざまな可能性があるように、定子、彰子などの漢字名をどのように読んだかはわかっていない。いずれにせよ女たちの名が実際にどういうものであったのかについては不明な点が多い。
物語の作者
少なくとも『源氏物語』の作者は紫式部だと確定しているが、そのようにして物語の作者が明らかになっている例は非常に少ない。どうやら物語を読む側は、それが誰によって書かれた作品かということをほとんど重視していなかったようである。かぐや姫の物語である『竹取物語』の作者も継子いじめを描いた『落窪物語』も、多くの女性読者を魅了したらしい『夜の寝覚』も作者が誰だかわかっていない。
ではなぜ紫式部が『源氏物語』の作者だとわかるかというと、紫式部は別に『紫式部日記』と呼ばれる日記を残しているからである。一条天皇が『源氏物語』を読み聞かせられたとき、「この人は日本紀をこそ読みたるべけれ。真に才あるべし」(この人は『日本書紀』などの歴史書を読んでいるにちがいない。たいそう学識があるようだね)と言ったので、意地悪な女房に、あの人は学識をひけらかしていると吹聴されて「日本紀の御局」とあだ名をつけられたと書いてある。紫式部は、実家でだって学識をひけらかすようなことはしていないのに、ましてや宮中でそんなことをするはずがないじゃないかと自らの憤りも書きつけている。
もともと『紫式部日記』は、日記といっても紫式部個人の雑感を書くようなものではなく、紫式部が仕えた一条天皇后の彰子の皇子出産を記録する目的で書かれたものらしい。ともあれ日記作品が残されたことで、『源氏物語』のような架空の登場人物によるフィクションでは知り得ない作者自身の声を知ることができるわけである。
紫式部とはどのような人だったのだろうか。いったいどういうわけで『源氏物語』のような大作が生まれたのだろうか。『源氏物語』と照らし合わせながら、紫式部の生きた時代をみてみよう。
「はじめに」より
註
(1)式部省 律令制における八省のひとつで、朝廷の儀式、官吏の試験、大学寮などを管理した。紫式部の名の式部は父、藤原為時の官位(式部省の官僚)に由来するという説がある。
(2)女童 日常のこまごまとしたことをさせる成人前の女の従者。
(3)入内 天皇の后候補として内裏(天皇の住まう場所)に入ること。摂関政治期には有力貴族たちがこぞって娘を入内させたが、后の位にのぼるためには男子を産み次代の天皇の母となる必要があった。