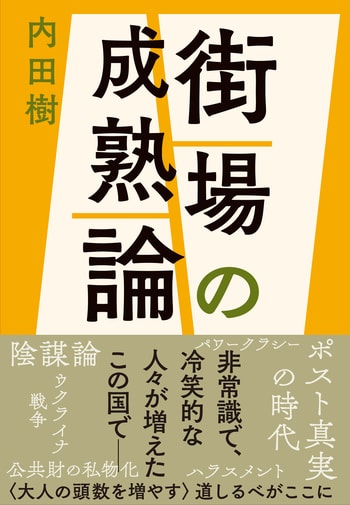〈「強硬派に対しても“境界線”を引かないほうがいい」イスラエル・ハマス戦争をめぐって内田樹が考える“暴力を制御する知恵”〉から続く
「ハラスメント」を理由とした離職は年間約87万人(2021年、パーソル総合研究所調査)とも言われるなか、会社組織から政界まで、日本社会にはびこる「他者に屈辱感を与える」病理の本質とは何か? 『街場の成熟論』が話題の思想家・内田樹が斬る。

◆◆◆
「屈辱感を与える」暴力性に対する警戒心が足りない社会
――最近でも、自見英子・万博担当相のパワハラや三宅伸吾・防衛政務官のセクハラ報道など、政治家の不祥事が相次いでいます。某パワハラ大臣の“対策マニュアル”の流出も近年話題になっていましたが、なぜこうした人権侵害が権力者のあいだでたびたび起こっているのでしょうか。
内田 「人に屈辱感を与えることをおのれの『得点』にカウントする習慣が日本社会に瀰漫した」ということだと思います。
キーワードは「屈辱感」です。ご質問は「人権侵害」についてですけれども、実際に例示として挙げられていたのは、不当逮捕とか令状なしの拘禁とか拷問とかいう人間の身体や市民的自由に対する侵害ではありません(さいわい、日本はまだそこまで未開国になっていません)。そうではなく、どれも相手に不要の屈辱感を与える行為です。
見た目には身体に傷がついているわけではないし、何か財貨を奪われたわけでもないし、市民的自由が侵害されたわけではない。でも、あきらかに自尊感情を損なわれ、生きる意欲を奪われている。人によってはそれが原因で精神的に病み、職場に行けなくなり、自殺する人さえいます。
今の日本社会は「屈辱感を与える」というふるまいが含むシリアスな暴力性に対する警戒心が足りないと僕は思います。

メディアに登場するコメンテイターたちの中には、あらゆる討論で「相手に屈辱感を与えることだけ」を目標にして発言する人たちがいます(誰とはいいませんが、わかりますよね)。この人たちの目標は「議論に勝つ」ことではありません。公開の席で「議論に敗けた」人を屈辱感のうちに追い込むことです。議論の中味なんか、ある意味どうでもいいのです。だから、このタイプの人たちは平気で食言します。虚偽を述べることも厭わない。別に面と向かっている相手と知的誠実さを競っているわけではないからです。彼らは自分に反対する人間には必ず屈辱感を与えるという断固たる決意によって論争に勝ち抜き、「メディアの寵児」となっている。
そういうことが可能になったのは、「他人に与えた屈辱感・敗北感」は与えた側の「得点」になるという思想が広く日本社会に根づいたからです。これがあらゆる「ハラスメント」の生まれる土壌をかたちづくっています。
政治家たちが「人に屈辱感を与えるテクニック」に長じるようになったのも、このような風潮のせいです。
「お前は私の前ではまったく無力なのだ」というメッセージ
――確かに屈辱を与えた側が「格上」に見えてしまう風潮があります。
内田 歴代の官房長官はある時期から記者会見で政府にとって不都合な質問には決して答えないようになりました。「それは当たらない」とか「個別の事案についてはお答えを差し控える」とかいう定型句を駆使する人間を一部のジャーナリストは「鉄壁」と称賛しさえしました。
でも、彼らはただ質問に答えていないだけではありません。同時に、質問した記者に屈辱感を与えてもいるのです。彼らは無言のうちに「お前が何を質問しようと、私は自分の言いたいことしか言わない。お前は私を論難することも、絶句させることもできない。お前は私の前ではまったく無力なのだ」というメッセージを発信しているからです。
そして、このメッセージを10年間にわたって浴び続けているうちに、政治記者たちは「生きる知恵と力」を深く傷つけられて、いつの間にか死んだようになってしまいました。
ですから、政治記者たちの「不甲斐なさ」「腰砕け」はもちろん彼ら自身の責任もあるのですが、日常的に彼らに浴びせかけられた「呪詛」の効果でもあると僕は思います。
――パワハラを生みやすい組織にはどんな特徴があると思われますか?

内田 パワハラを生み出しやすい組織の典型は、一言で言えばトップダウンの組織です。というのは、トップダウンの組織の多くでは、「どうやって組織のパフォーマンスを上げるか」よりも「どうやって組織をマネジメントするか」の方が優先されるからです。
組織が何を生み出すかよりも、組織がどう管理されているかが優先的な問いであるような組織では、上位者の命令が遅滞なく末端まで示達されることが重視されます。上位者のいかなる命令にも「イエス」と即答する忠誠心が最も高く評価されます。能力よりも忠誠心が優先的に評価されます。構成員全員に「イエスマンシップ」が求められます。あらゆる指示が途中でまったく抵抗に遭わずに現場まで届き、ただちに物質化する組織が「よい組織」だということになる。
そういうふうに言うと、なんだかすごく効率的な組織のように思えますけれど、そうでもありません。
なによりも、上意下達的組織では、すべての職位のすべてのメンバーが「上にはおもねり、下には威圧的」という人間に造形されてしまうからです。個人の資質とはかかわりなく、そういう「鋳型」にはめられてしまう。仕方がありません。上位者に「忠誠心」を誇示することが能力を発揮することよりも勤務考課上優先するんですから。
上司は、自分が上にへつらっている以上、下に対しても同じ態度を要求します。「私にへつらうこと」を当然の権利として求めるようになる。その結果、上司に阿諛追従し、下僚に阿諛追従を求めることがこの組織では「デフォルト」となる。かつての日本の軍隊と同じです。
繰り返し言いますけれど、これは個人の責任ではありません。組織原理がそう命じるのです。その「鋳型」にはまり切らなければ、「異物」としてはじき出されてしまう。
――なるほど。
「どちらがボスか」を部下に思い知らせる行為
内田 パワーハラスメントというのは、この定型化したふるまいのうちの「上司が部下に向かって、当然の権利として、自分にへつらうことを求める」ことで下僚が受ける精神的な傷のことだと僕は思います。
上司としては、当然の権利を行使しているつもりでいるわけですから容赦がない。単にきちんと挨拶をするとか、敬語を使って話すくらいでは物足りない。すり寄り、おもねり、へつらい、尻尾を振って来ることを求める。それができないという人間は「この組織のルールがわかっていない人間」ですから教化しなければならない。「どちらがボスか」ということをきっちり教え込まなければならない。
そして、今の日本社会では(もう軍隊じゃないので)殴りつけたり、外に立たせたり、営倉に放り込んだりという直接的な暴力は禁じられていますから、できることは限られている。だから「屈辱感を与えること」が拷問の代わりに採用される。

上司から理不尽なことを言われても、意味のないタスクを命じられても、部下は抗命できません。抗命すれば「業務命令違反」「就業規則違反」として咎められる。だから、黙って従うしかない。その屈辱の経験を通じて「どちらがボスか」を部下に思い知らせる。
そういうやり方が上意下達的組織では日常的に行われるようになります。パワーハラスメントがこれだけ横行するのは、別に日本人が全体として意地悪になったわけではありません。そうではなく、「組織はトップダウンで編制されなければならない」という信憑が広まったせいです。その方が効率的で、生産的だと誰かが言い出した。でも、それは端的に嘘ですよ。
「やまとことば」にない3つの言葉
――確かにトップダウンの組織は生産性が高いと広く信じられています。
内田 歪んだトップダウンの組織というのは、「やりたくないことをやらせる」ための組織です。上位者の命令に対して「それ、ちょっとおかしくないですか」とか「悪いけど、その指示まったく無意味です」とか言って「常識的に抗命する人間」を一人も存在させない組織です。「私はそれをやりたくない」という個人的反抗を決して許さない組織です。
でも、そういう組織ではトップが誤った指示を出した場合に、誰もそれを止めることができません。トップが致命的な誤りを犯した場合に、誰もそれを途中で補正できない。だから、壊滅するときは一気に壊滅します。「フェイルセーフ」も「リスクヘッジ」も「レジリエンス」もそういう組織には存在しない。
現に、僕が今挙げた三つの単語はどれも日本語訳がありません。それぞれ「装置が正しく作動しなくても安全を保障する機構」、「すべてを失わないように両方に賭けること」、「一度崩れた機構を復元する力」という意味です。どれも「プランAがうまくゆかなかった場合に最悪の事態を回避するためにプランBを用意しておく」というふるまいにかかわる言葉です。これに対応する「やまとことば」がないのはもちろんですが、「略語」さえありません。
日本社会は外来の概念であっても、理解できて、日常の風景の中にあって、具体的に「これ」と指し示すことができるようになると、それを「カタカナ四文字の略語」にします。必ず、そうします。パソコン、ワープロ、デジカメから始まって、コンサル、ポリコレ、パワハラ、セクハラに至るまで。でも、フェイルセーフとリスクヘッジとレジリエンスについてはかたくなにこれを翻訳することも略語を作ることも日本人は拒んでいる。そんなものは日本社会にはなかったし、今もないし、これからもあってはならないと無意識のうちに日本の組織人たちが信じているからです。
トップが最初に命じたことは何があっても(それが明らかに間違いであることがわかっても)完遂されねばならない。日本の組織人がそう信じています。そうやって東京五輪も、リニア新幹線も、大阪万博も、始めた以上は続けなければならないということになった。途中で「これ、意味ないですよ」というかたちで遮られることを上意下達組織は決して許さない。そうやって破滅的な失敗に向かって雪崩れ込んでゆく……たぶん日本はそういうふうに滅びてゆくと思います。

パワハラを生み出しやすい組織とはどんなものかというご質問でした。「今の日本社会そのもの」がそうです、というのが僕の答えです。
暴力性・攻撃性を抑制するための唯一の方法
――ハラスメントのような暴力に抗する道筋とはなんでしょうか。
内田 暴力性・攻撃性はあらゆる人間に内在しています(程度差はありますけれど)。そして抑圧するといずれどこかで「症状として回帰」します。多くの場合は、物理的な暴力としてより自分より下位の人間に不要の屈辱感を与えるというかたちで噴出します。家庭でも、学校でも、職場でもそうです。あらゆる「ハラスメント」はそういう意味で抑圧された暴力がもたらす症状です。ハラスメントは「政治的に正しくない暴力」(いきなり人を殴りつけるとか、銃で撃つとか、刀で斬りかかるとか)が禁圧された「文明化された社会」において、暴力性と攻撃性が行き場を失って漏洩しているものだと思います。
「ハラスメント」は「猟犬を駆り立てる叫び」を意味する古仏語が語源です。そこから「猟犬が獲物をどこまでも追い続けて、息も絶え絶えな状態にすること」を意味する動詞harasser ができました。harassmentはその名詞形です。長い距離、長い時間、猟犬に駆り立てられて息も絶え絶えになった獲物が感じる絶望的な疲労感のことを「ハラスメント」と言うのです。
ですから、「ハラスメント」を単なる「いやがらせ」と訳すのは言葉があまりに足りません。生きる意欲が失われるほどの絶望的な疲労感を長期にわたって、執拗に、繰り返し与えることが「ハラスメント」だからです。
今の日本社会では、抑圧された暴力はしばしば「ハラスメント」という病的なかたちを迂回して発動している。僕にはそのように見えます。「獲物」の生きる力を損なうという点については、harasser は実は「殺す」とそれほど変わるわけではないのです。
暴力性・攻撃性を抑制するための唯一の方法は、自分のうちにそのような邪悪な欲動が存在するということを認めることです。自分のうちには暴力的な欲動があり、それがさまざまな「迂回路」をたどり、さまざまな「偽装」の下に、無意識のうちに他人を傷つけ、その生きる意欲を損なう機会を狙っているという事実をまず認めることです。
そして、それを何とかして自力で解除する。
自分の暴力性を「飼い慣らす」方法を模索する
――具体的にはどうしたらよいのでしょう?
内田 方法はいろいろあると思います。「作品として外在化する」というやり方もあるでしょうし、宗教的な実践を通じて心身を浄化するというやり方もあるでしょうし、ルールの決まったスポーツを通じて発散するというやり方もあるでしょう。僕自身は武道の修行を通じて自分の暴力性を「飼い慣らす」というやり方を採用しました。
誰にでもできる標準的な「暴力の制御法」はありません。でも、どんな場合でも「自分には人を傷つけることができるし、無意識のうちにそれを望んでいる」という原事実から目を逸らしてはいけません。
注意すべきことは、暴力が発動するときには、必ず「大義名分」を要求するということです。なまの暴力がそのまま無言で発動するということはありません。何か言葉にできるような「名分」が要る。ふつうは「正義の実現」とか「教化的な叱責」とか「教育的指導」とかいう「言い訳」が採用されます。
ですからもし自分の脳裏に「正義」や「教化」というような言葉が浮かび、それに基づいて、人を叱責したり、処罰や屈辱感を与えたりしたくなったら、それはどのような大義名分を掲げていても、実は「この人を傷つけ、生きる意欲を失わせたい」という邪悪な衝動に支配されているということです。
この衝動からは誰も逃れられません。できるだけ人を傷つけないように個人的に努力すること以上のことはできません。でも、それはどれほどささやかであっても尊敬に値する努力だと僕は思います。
――「倫理」や「道徳心」に無力感を感じやすい時代に、子供たちの成熟への動機づけをどうはぐくんだらよいのでしょうか。
心身の自由へのあこがれが「成熟」を動機づける
内田 人を「未熟である」という理由で処罰することはできません。成熟というのは処罰に対する恐怖によってではなく、成熟がもたらす心身の自由へのあこがれによって動機づけられるものだからです。
今の日本社会で成熟への動機づけが弱まっているのは、子どもたちが身近に「成熟した大人」が愉快に暮らしている様子を見る機会がほとんどないからです。まわりには「むすっと不機嫌な顔をした大人」と「人を傷つけたり、屈辱感を与えては高笑いしている大人」しかいないんですから、「成熟することへのあこがれ」が生まれる余地がない。
でも、子どもを大人にするためには、「大人を見せる」以外に手はないんです。ひとりずつ「大人の頭数」を増やしてゆくこと。できるのは、それだけです。
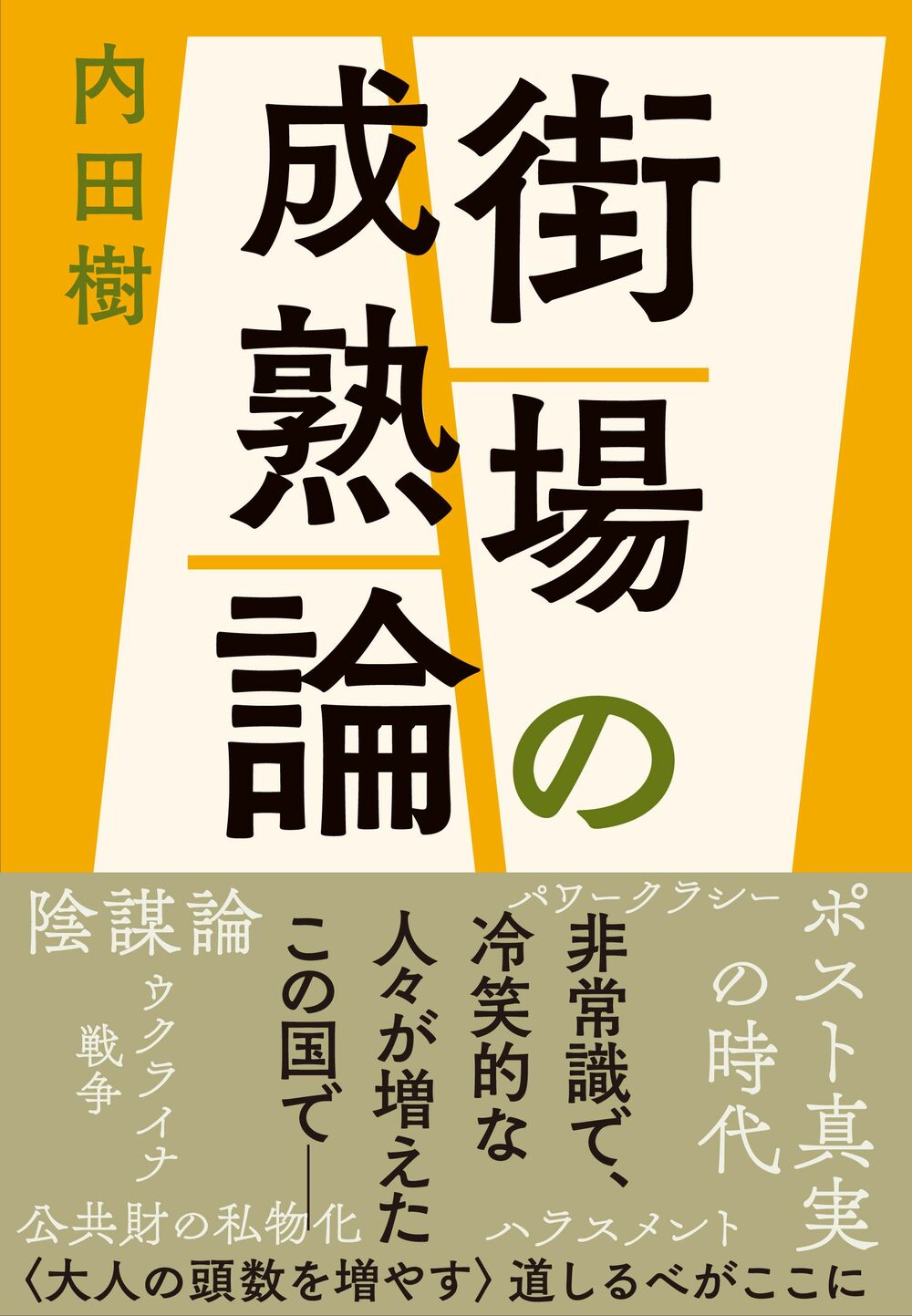
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。『私家版・ユダヤ文化論』で小林秀雄賞、『日本辺境論』で新書大賞を受賞。他の著書に、『ためらいの倫理学』『レヴィナスと愛の現象学』『サル化する世界』『日本習合論』『コモンの再生』『コロナ後の世界』、編著に『人口減少社会の未来学』などがある。