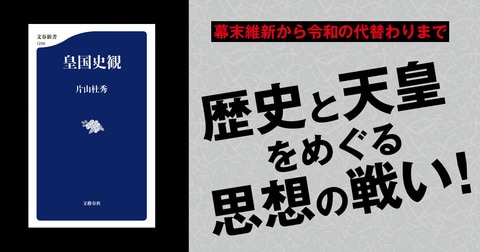他愛もない感想から始めることを許していただきたい。私は、昔から、内田樹の本を、あるいはその論考を読むと、なにかしらすっきりと頭がよくなったような気がしてきた。すぐれた著作には、多かれ少なかれそのような気分にさせてくれる何かがあるのだろうが、相性というか、内田さんのものには特にその感が深い。
それは分厚い哲学書や思想の本を読んで感じる、圧倒されるような思考の量(マス)によるといったものとは違うようだ。個々の社会的な出来事や、政治の各論的な報道、それらすでに馴染み深い事象への、個別的な感想の断片の数々を私たちは抱え込んでいる。通常、それらは個々ばらばらに存在し、時々刻々濃淡の差をもって思考の表面に現われてくるのだが、内田さんの手にかかると、そのような個々ばらばらの世界が、思いがけない補助線によって、それぞれに新たな関係性を付与されて、一つの体系にすとんと収まってしまう。そんな腑に落ち方とその快感、体験の鮮烈さが、読者たる私にちょっと頭がよくなったと思わせ、いっぽうで敵わねえなと頭を掻かせる理由でもあるのだろう。漠然とそんなことを思ってきた。
本書『街場の天皇論』を読みつつ、やっぱりそうだよなと今回も思い、蛍光ペンで線など引きながら読んできたのだが、その終りに近く、まさに私が感じている内田樹の文章の魅力を、著者自らがまったく無意識のうちに語っている部分に出会って、はたと膝を打つことになった。
本書は、天皇について、天皇制について、あるいはそれに関連する話題について、これまで多く書かれてきた文章を整理し収めたものだが、その最終章に単行本書きおろしの「[特別篇]海民と天皇」という章がある。この「特別篇」は「さしたる史料的な根拠のない、妄想に類する思弁であるが」としながら、自分にとって思弁とはいかなるものかについて短く語られる。
私の思弁は一見するとまったく無関係に見えることがらの間に何らかの共通点を発見してしまうこと(太字、内田)である。そういう学術的方法を意図的に採用しているわけではなくて、気が付くと「発見してしまう」のである。「あ、これって、あれじゃない」。 (「[特別篇]海民と天皇」)
エビデンスベースの論考とは違って、ちょっとした思いつきなのだと、やや言い訳めいて語られる著者の「思弁」は、その文章に私がいつも抱いていた魅力を、これまたすとんと納得させてくれるものであった。まさに「一見するとまったく無関係に見えることがらの間に何らかの共通点を発見してしまう」ことこそが、世界を見ることに他ならず、そんな風に世界を見透せる人こそが、ポアンカレの言う「洞察」力のある思想家なのに違いない。