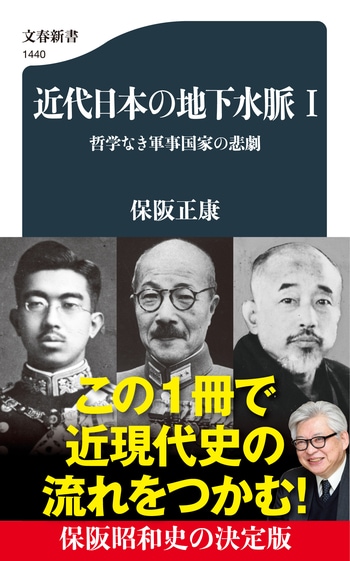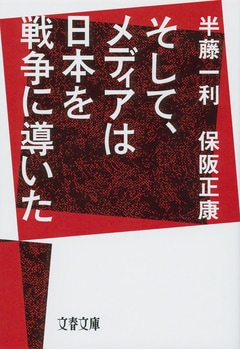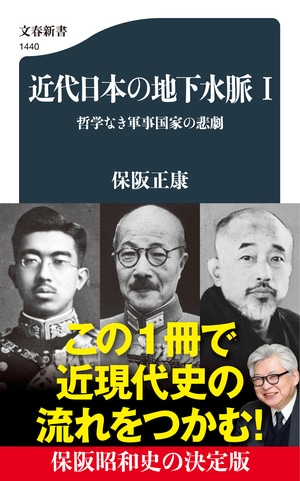
なぜ日本は太平洋戦争を始め、敗戦に至ったのか。なぜ「玉砕」「特攻」といった無謀な作戦で多くの人命を失ってしまったのか?──
私が昭和史の研究に携わるようになったのは、こうした謎を解明したいとの強い動機からであった。
そして、実際に敗戦に至る道筋を調べれば調べるほど、明治維新以降の歴史をもう一度つぶさに検証しなければならないとの思いを、私は抱くようになった。
明治以降、日本の国家体制の構築は、すべてが「軍事」に収斂するプロセスの中でおこなわれてきた。たとえば経済・産業の発展は、軍と密接に結びついた政商によって主導され、日清戦争以降は戦争そのものが国家的ビジネスとしての性質を色濃く持つようになった。戦争で得た賠償金は、さらに軍を強化するために投じられた。欧米列強に少しでも早く追いつくために、そのような道を選択せざるをえなかったという事情もある。
しかし、すべてが軍事に収斂する国家体制において、政治と軍事の関係性には矛盾が内在するようになった。欧米列強のようなシビリアン・コントロール(文民統制)の歴史がなかった日本は、軍事の下に政治が隷属するという、いびつな状況が進んだ。すると必然的に、個人の自由が制限された窮屈な、市民意識が希薄な社会となっていく。
その行きついた先は、まさに「人間性喪失」の世界そのものだった。
「人命軽視」の答えを探す旅
厚生省(現在の厚生労働省)の調べによると、太平洋戦争での戦死者は、軍人、軍属などが約二百四十万人(そのうち大正生まれが約八四%)とされている。民間人の死者数は約七十万人といわれており、合計で約三百十万人にものぼる。
しかし、これは概数にすぎない。実際には戦後の戦病死を含めて五百万人は超えるのではないかと、私は見積もっている。当時、日本の人口は約七千五百万人とされていた。つまり、総人口の一割近くが戦争に関連して命を落としていると推察できる。
軍人、軍属の戦死者については、彼らが実際の戦闘で亡くなったのか、飢えや疫病などで亡くなったのかなど、はっきりした死因がわかっていない。ただ私自身、戦地にあって指揮を執った将校や下士官、そして現実に戦った兵士たちに数多く話を聞いてきたが、栄養失調による餓死と、それに伴う体力の低下と消耗の結果、マラリアなどに感染して病死した広義の戦死が、死因の大部分を占めたことは間違いないといえる。実際に軍医たちが残した記録を読むと、「デング熱患者次第ニ増加シ、終ニ本部将校二名罹患ス」(麻生徹男『ラバウル日記』)などといった記述が容易に見つかる。
日本軍の兵士たちが、いかに悲惨な状況に置かれていたかを示す文献は、ほかにも多くある。たとえば佐世保鎮守府第六特別陸戦隊の部隊史は、栄養失調とマラリアで兵士たちが続々と倒れ行くありさまを生々しく記している。
〈(昭和)十九年の四月ごろから急に栄養失調症が増えてき、栄養失調による死者、すなわち餓死者が出始めた。マラリアにかかると四〇度の高熱が出てそれが一週間ぐらいつづく。それで体力が弱まったところへ食糧がなく、極度の栄養失調に陥って、その後は、薬も食事も、ぜんぜん受け付けない状態になって死んでゆく──それが典型的な餓死のコースだった〉(『ソロモンの陸戦隊 佐世保鎮守府第六特別陸戦隊戦記』)
この陸戦隊は、昭和十七(一九四二)年八月に編制されてソロモン諸島のブーゲンビル島の守備にあたり、十八年末からは補給が完全に途絶えていた。こんな地獄のような状況を招いたのは、当時の軍事エリートたちが兵站を軽視し、「補給は現地調達せよ」と、現場に責任を丸投げした結果である。彼らは兵士の命の重さを考えずに戦略・戦術を組み立てていった。これが、先の戦争で起きていた「人間性喪失」の実態なのである。
私は長年、なぜ当時の軍首脳がこれほど兵士の命を軽視できたのかが疑問であった。餓死や疫病死だけではない。「特攻」や「玉砕」といった無謀な戦術、さらには昭和十六年に東條英機陸軍大臣が全陸軍軍人に布達した『戦陣訓』では、「生きて虜囚の辱を受けず」と、捕虜になるぐらいなら自決せよと命令している。こうした軍の方針からは、まったくといっていいほど「国民の命」を重んずるという発想が感じられない。それはいったいなぜなのか?──
私は今まで五千人近くの昭和史関係者にインタビューを重ねてきたが、その作業は、この根源的な問いに対する答えを探す旅でもあった。
戦争が「ビジネス」であった戦前の日本
そして、私はひとつの結論にたどり着いた。結局のところ、軍事指導者にとって戦争とは「賠償金を得るための経済活動」にすぎず、一種のビジネスであったということである。つまり、兵士の命はカネを稼ぐために戦場で使い捨てにされたのである。
近代日本は、明治二十七(一八九四)年に始まった日清戦争以降、ほぼ十年ごとに戦争を繰り返してきた。日清戦争では、日本は清国から当時の国家予算の四倍にもあたる莫大な賠償金を獲得した。その賠償金を元手に、明治三十年代から富国強兵政策を進めた。さらに日露戦争(明治三十七~三十八年)では、満鉄の利権をはじめロシアがもっていた権益を確保し、樺太の南半分も日本の領土にした。そして大正三(一九一四)年に始まった第一次世界大戦では、日英同盟を口実に参戦し、ドイツが中国や南洋諸島に有していた権益をどさくさ紛れに手に入れた。
日本は戦争に勝つことによって列強の仲間入りを果たし、その賠償金によって富国強兵を実現してきた。戦争は“国家的利益”を上げる最大の事業だったのである。
軍人の仕事は「戦争に勝って、賠償金を得ること」につきる。彼らの根本的な発想は、以下のように整理できる。
〈われわれ軍人は、戦に勝つことによって、天皇陛下、そしてお国に奉公する存在である。多くの賠償金や権益を確保できれば、国が富む。その獲得した富でさらに軍備を充実させることができる。だから、絶対に戦争に負けるわけにはいかない。戦争に勝って利益をあげるためであれば、戦場の兵士の人命など惜しくはない〉
こうした「ビジネス」としての戦争という側面については、戦場で散った兵士の苦衷を十分に理解したうえで、さらに具体的に検証していかなければならない。
日本が模索した「五つの国家像」
日本の近代はすべてが「軍事」に収斂していく過程だった。それは、欧米列強型の帝国主義国家を目指し、それに少しでも早く追いつくために、やむをえない選択だったとも考えられる。
しかし、本当に日本には欧米型の帝国主義を目指す道しか存在していなかったのか?
私は、そうではない別の道があったと考えている。よりかみ砕いて言えば、明治維新後の日本は、欧米型の帝国主義国家以外の国家体制を作り上げる可能性があったということである。
近代日本の始まりである明治の初期に遡ろう。
徳川幕府が倒れて明治新政府が誕生したものの、新政府内の指導者には、日本が進むべき「国家ビジョン」が明確にあったわけではない。明治二十二(一八八九)年に大日本帝国憲法ができるまでのほぼ二十年間は、「日本という国をこれからどのように作り変えていくか?」をめぐって、さまざまな勢力の“主導権争い”がおこなわれた時期だった。
私はこの間に、次の五つの国家像が模索されたと考えている。
(1)欧米列強にならう帝国主義国家
(2)欧米とは異なる道義的帝国主義国家
(3)自由民権を軸にした民権国家
(4)アメリカにならう連邦制国家
(5)攘夷を貫く小日本国家
詳しくは第1章で説明するが、概略を記しておこう。
(1)は軍事主導の国家体制を固め、周辺諸国を圧倒して権益を奪い取って繁栄を目指す国家像である。
(2)は帝国主義という形態ではあるが、軍部が主導するのではなく、市民社会の道義をその軸にすえた国家像である。
(3)は明治十年代、板垣退助らが取り組んだ自由民権運動の延長線上にある、国民主権の国家像である。
(4)は南北戦争後に連邦制国家に移行しつつあったアメリカにならい、地方分権を主軸とする国家像である。
(5)は鎖国下の江戸時代に培われた日本独自の価値観を生かし、海外進出の野望を封印して「小国家」として生きてゆくという国家像である。
現実には、明治新政府は(1)の道を進み、欧米列強に伍するためにすべてを軍事に収斂させていった。そしてその結末として、第二次大戦の悲惨な敗北を迎えたのである。
「地下水脈化」した国家像
では、残る(2)~(5)の国家像は、そのまま消えてしまったのか?
私は、そうは考えていない。四つのそれぞれの思想やビジョンは、いったん日本社会の地下に潜りながら、いまも脈々と流れ続けている。そして近代日本が歴史の重要なターニングポイントを迎えるたびに、地下水脈が噴出してくるのである。
歴史とは、いつの時代も単線的に動いている訳ではない。そこには必ず人間の対立、論争、生き方の違いが存在する。近代日本について言うならば、それは表を流れる(1)の国家像に対する(2)~(5)の地下水脈の思想のぶつかり合いが絶えず起きていたと表現することができる。そして、地下水脈のぶつかり合いは、軍部が全面的支配を狙う昭和初期のころにも確かに続いていたのだ。
西南戦争と民権運動
こうした地下水脈のぶつかり合いの例として、明治十(一八七七)年に勃発した西南戦争を見てみよう。
西南戦争は、不平士族が中心になって維新の立役者の西郷隆盛を担いだ武力反乱で、近代日本最後の内乱であった。政府軍には明治六年の「徴兵令」によって集められた平民出身の兵士が多かった。彼らの登場によって、戦を生業とする士族の時代は完全に終わりを告げ、日本は欧米列強の軍事制度に範をとり、近代的な軍隊を整備していくことになった。
それと同時に、西南戦争には別の側面もあった。
たとえば「日本赤十字社」は西南戦争が生んだ組織である。西南戦争の際、佐野常民、大給恒両元老院議官らが傷病者救護活動等のため設立した博愛社が前身である。
西南戦争では、官軍と薩摩軍の間での激しい戦闘により多数の死傷者を出した。この悲惨な状況を知った佐野と大給が、救護団体による戦争時の傷病者救護の必要性を痛感し、欧州でおこなわれている赤十字と同様の救護団体を作ろうとした。賊軍の手当てなどしなくていいと反対した政府軍の指導者もいたが、彼らは反対勢力を説得してゆく。そうして政府によって活動が許可されたのが博愛社である。同社は西南戦争全体で千四百二十九人の患者を敵味方の区別なく収容したという。
また、西南戦争下において、「日本初の民権政治」が営まれた点も無視することはできない。これには熊本県北部の山鹿の戦線に参加した「熊本協同隊」が関与している。同隊には、孫文の辛亥革命を支援したことで知られる宮崎滔天の長兄、宮崎八郎が中心人物として参戦していた。山鹿を一時占拠した協同隊は、この地を円滑に統治するために、人民の代表を選挙で選んだ。滔天は「熊本協同隊」という文章にこう書き記している。
〈彼等は同時に一大紀念を此地に残せり。民政を敷きたる事是なり。乃ち野満長太郎を民政官に任じその年来の主張たる自由民権の旨趣に基き、人民を集めて自治政の要旨を説明し、普通選挙法を以て人民総代なるものを選ばしむ。選に当るもの大森総作以下数人、乃ち野満長太郎之を監督して自治の政を行ふ。蓋し我国未曾有の事たるなり〉
滔天自身が自由民権主義者で、兄も参加していた隊のこともあり、やや誇張した可能性も否めない。しかし、普通選挙を実施したことは間違いない。政府による初の選挙がおこなわれるのは明治二十三年であり、それより十三年早いことになる。
この運動の中心人物となった宮崎八郎は熊本で育ち、明治三年に上京し、中江兆民の薫陶を受けて、民権運動に目覚めた。明治八年に熊本に戻り、学校を設立。この学校で学んだ者たちが中心になって結成されたのが熊本協同隊である。
このように西南戦争の周辺を検証していくと、そこには先の分類でいう(3)、つまり自由民権を軸とした国家思想の流れが見られる。一方で、決起前の西郷が薩摩でおこなっていた私学校支配は地方分権のさきがけとも言え、(4)の国家像の流れに通じている。もっとも、西郷自身はもともと欧米列強とは一線を画した東洋的な「道徳」を軸とした国家を目指しており、これは上記の(2)の流れに通じる。
地下水脈化したのは、五つの国家像だけではない。戦争を一種の「営利事業」とみなし、現場の兵士たちの人命を軽視してきた軍事エリートの発想や、「いかに国を守るか?」という軍事哲学を持たないまま富国強兵を進めた国家指導者らのあり方も、地下水脈化している。戦後、その水脈は伏流水となって表面上は見えなくなったが、令和のこの時代も脈々と流れ続けているのである。
このシリーズでは、さまざまな歴史の場面で顔を出す「地下水脈」をあらためて見つめることで、日本の近現代が歩んだ百五十年を再検証する歴史観を考えていきたい。
<はじめに 失敗の本質は「軍事主導」にあった>より