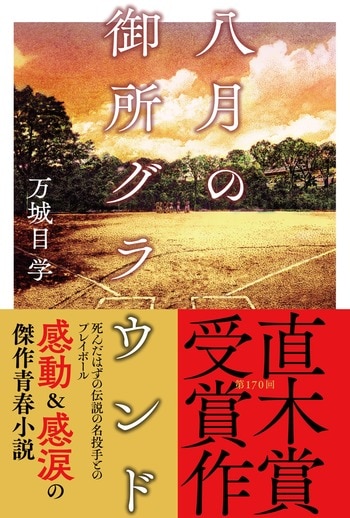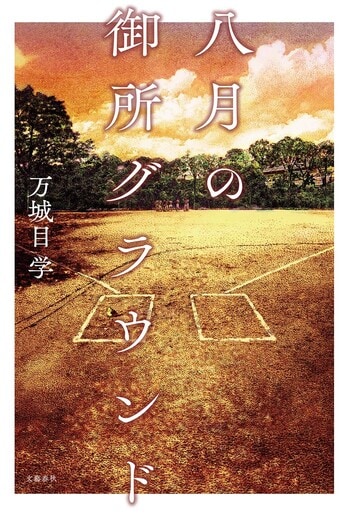1月17日、第170回直木三十五賞の選考会が開催された。受賞作は、万城目学さんの『八月の御所グラウンド』(文藝春秋)、河﨑秋子さんの『ともぐい』(新潮社)に決定。
受賞発表の翌日、万城目学さんに話を聞いた。

◆◆◆
――このたびは『八月の御所グラウンド』での第170回直木賞受賞、おめでとうございます。昨日の記者会見でも「受賞するとは思っていなかった」と、意外そうでしたね。
万城目 自分が獲ることはないなと、完全に他人事のような気持ちでいました。昨日は待ち会のあと会見して、めっちゃ疲れたはずなのに、脳が興奮しているのか、ほとんど寝れなかったです。戦場からの帰還兵って、家に帰ったその日は寝られへんやろうなとか思いました。
森見さんのポジティブマインド
――発表前の待ち会には編集者の方の他に、森見登美彦さん、綿矢りささん、ヨーロッパ企画の上田誠さんがいらしたそうですね。どういう繫がりなのでしょうか。
万城目 10年くらい前、綿矢さんもまだ京都に住んでらっしゃった頃、僕が京都に行った際には森見さんと綿矢さんと3人でご飯を食べていたんです。上田さんも京都の方なので、時々そこに加わるようになって。
森見さんと上田さんとは毎年忘年会もしています。『八月の御所グラウンド』に収録された「十二月の都大路上下ル」は京都で開催される高校生の駅伝大会の話ですが、あれは基本的に12月の最終日曜日に開催されるんです。僕は2017年から取材のために大会を見に行っていて、ついでに忘年会をやるようになりました。

去年の忘年会で直木賞ノミネートの話になった時、僕が「どうせあかんから」とか「落選回数の日本記録を作るんや」とかネガティブなことをひたすら言っていたら、森見さんに叱られまして。「直木賞というのはお祭りであるから、楽しまないと損なんだ」と。
僕は、森見さんは執筆まわりの物事に対し、得てして後ろ向きになりがちやと思ってたんですけれど、そのときはめっちゃポジティブで。「これから数十分後に電話がかかってきて、自分の人生がどちらかに分かれる。そう思うと面白いじゃないですか」とか。なんて前向きなとらえ方やろうと、ちょっと感動しました。
森見さんが「東京行くから待ち会しましょうよ」と言いだし、「ほんまかいな。それなら、綿矢さんもお誘いしますか」「ボードゲームしましょう。あかんかったら朝までボドゲ大会ですよ」という流れになった次第です。
あの建物は何?
――会見では脱出ゲームと、地獄のUNOもなさったとおっしゃっていましたよね。
万城目 綿矢さんに連絡したら「脱出ゲームはしなくて大丈夫でしょうか?」という返事が来て。「綿矢さんは脱出ゲームとか好きなんですか?」と訊いたら、「やったことありません」って。何やそれと思いつつ、僕が全部予約しました。
脱出ゲームの場所が、選考会が行われる築地の新喜楽の近所やったんです。僕が「さて、あそこは何でしょうか?」って料亭の建物を指さしたつもりが、綿矢さんは最初、新喜楽の隣の「すしざんまい」のほうを見ていて。なかなか噛み合わなかったです。
――面白すぎます。
万城目 その後、上田さんが遅れて合流して、ルノアールの個室で綿矢さんが持ってきた「UNOアタック」を使って永遠に終わらない地獄のUNOをやり、疲れ果てたら夜の7時でした。時間が経つのが早いというか、直木賞の存在を忘れるというか。あれはお薦めの待ち方です。

――昨日の会見で、最後に「次は森見さんだと、バトンを渡したいと思います」と言って会場の後ろに視線を送られたので振り返ったら、森見さんがニコニコして見守ってらして。盟友同士の交流にちょっと胸が熱くなりました。
万城目 森見さんは会見で質問したかったらしいですよ。「僕もいつか獲れるでしょうか」って。僕は「あと3回くらい無理じゃないですか」と答えたでしょうけど。
「険しき直木賞マウンテン」
――森見さんと万城目さんはそれぞれ、ユーモアと空想力を炸裂させた独自の世界を書かれてきましたよね。万城目さんは最初に直木賞にノミネートされたのが2007年の『鹿男あをによし』(幻冬舎)の時で、今回が6回目でした。
万城目 2007年に森見さんも『夜は短し歩けよ乙女』(KADOKAWA)で初ノミネートされているんです。そんな因縁で、森見さんとは直木賞について「自分たちはカテゴリーエラーなんだろう」とよく話していました。「険しき直木賞マウンテン」と、山にたとえて、みんなが登っていく正規の登攀ルートがあるにもかかわらず、自分たちはわざわざ未踏破の「面白ルート」にトライしては毎回滑落しているんじゃないか、って。

――すでに独自の作品世界と読者を獲得されているけれど、やはり賞って意識しますか。
万城目 直木賞に受け入れてもらえるように作風を変える、といった発想は全然なかったんですけれど、でもノミネートされて無視できるかと言うと、それはできないわけですよ。で、「どうせあかんやろ」と言っていじけるんです。だから、作風には影響を及ぼさなかったけれど、メンタルの面でとらわれていたかもしれません。
昨日、会見の後、編集者さんたちが集まってくれて一言ずつお祝いの言葉をくれたんですけれど、ことごとく「ノミネートされてから、どうせあかんわ、とネガティブなことばかり言っていた」という入り方で、僕は自分が思っていた以上にいじけていたみたいです。「今回でそれがなくなるので本当によかった」ってみんなに言われました。
生者と死者が交差する物語
――『八月の御所グラウンド』は表題作と「十二月の都大路上下ル」の2作が収録されています。どちらも日常に非日常が紛れ込み、生者と死者とが交錯する話ですが、同じコンセプトの中編をすでに書き上げているそうですね。
万城目 最初に構想したのは「六月のぶりぶりぎっちょう」という作品で、歴史教師がホテルに泊まったら殺人事件が起き、その謎を解きがてら「本能寺の変」の秘密に迫るというミステリーのようなコメディのような中編でした。
それが「生者と死者がすれ違う」という話だったので、このコンセプトを中心にすえて、あと2本書いて、一冊の本にまとめようというのが初期構想です。「六月~」は生者の真横に死者がいるというイメージ。ならば、「十二月の都大路上下ル」は死者が自分たちよりちょっと後ろにいるイメージ、「八月の御所グラウンド」はちょっと前にいるイメージで、3パターンを考えていこうと。
『オール讀物』に連載物のような感覚で、「十二月~」「六月~」「八月~」の順に書いていったのですが、真ん中の「六月~」のテイストがあまりに他の2編と違うということで、単行本にするときは外すことにしました。結構、イレギュラーな本づくりだったと思います。
埼玉県予選で見た「涙」
――さきほど、2017年から高校駅伝を見に行っていたとのことでしたが、すいぶん前から取材されていたんですね。
万城目 毎年定点観測として年末の京都の本戦を見て、その1カ月前に地方予選を1か所見に行っていました。具体的には埼玉、宮城、東京、神奈川です。
女子駅伝は距離がハーフで1時間ほどで終了するので、1回の取材でコースのあちこちを回って見られないんです。それで、京都取材の最初の年はスタジアムでスタートを見て、次の年からは別の場所に移り、最終的に作中に登場する第5中継所、つまりアンカーの話にすると決めるまでに5、6年かかりました。

――方向音痴の補欠選手、坂東、通称サカトゥーさんが大会前日に選手に抜擢される。そんな彼女の競技中や前後の気持ちが丁寧に書かれて、それだけでも面白かったです。
万城目 ある年に埼玉の予選を見にいったら、ゴールしたアンカーの選手が次々にボロボロ泣いていたんですね。他の県予選に比べても明らかに泣いている人が多かったんです。そこから、なんでそんなに泣くんだろうという探究が始まったんですよ。
泣けなかった子が選手控室で泣いている子からその理由を告げられる話などを考えるうちに、試合後に一緒に走った他校の子とコミュニケーションをとる展開がいいなと思い始めて。競技中に一緒に非日常を経験したことをきっかけに、会話をすることになるという。
――その時の会話がものすごくいいんですよね……。「八月の御所グラウンド」は、大学生の朽木君が猛暑の夏休み中、先輩から強制的に草野球大会の凸凹チームに参加させられる話です。
万城目 構想段階から、編集者の人たちにざっくり内容を説明したら、必ず「その話は絶対いい」と言ってもらえて、異様に反応がよかったんです。あとはいかにわざとらしくないように、安いお涙頂戴に近づかないようにするか、ということを考えて書きました。
御所グラウンドの思い出
――万城目さんも御所グラウンドで草野球をやったことがあるのですか。
万城目 学生時代に、ほんの1、2回ですけれど。『巨人の星』で星一徹が飛雄馬に「1、2、3と数えて打て」と教えていて、それをやったらほんまにヒットを打てたんです。それを小説の中ではシャオさんという人が忠実にやっています。
――御所グラウンドもそうですが、朽木君とシャオさんが行くパスタ店「セカンドハウス」も実在するんですね。
万城目 そうそう。メニューも本当にあるものを書いています。
――「八月~」を書き上げた時、いつもと違う手応えがあったそうですが。
万城目 明らかにこれまでとは違う何かがあったんです。でも、あれはもう二度と手に入らない感覚です。「こう書けばいいのか」と思った時にすぐメモをとればよかったんですが、そうしなかったので翌日には全部忘れていました。無念です。いつかまた会いたいです。
作風の変化のきっかけ
――万城目さんは日常の中に非日常が紛れ込む話をお書きになりますが、デビュー前の学生時代に書いていたものは私小説っぽいものだったとか。どうして作風が変わったのですか。
万城目 大学生の頃は、学生が講義に出て、バイトをして、恋に破れてという、本当にどうでもいい話を書いていました。そういうものを新人賞に応募しても一次選考も通過できなかったので、一回、自分とはまったく重なるところのない、冴えない中年の貧乏探偵の話を書いたんです。

若者のウジウジした悩みとは関係ない、自分語りしようにも、どこにも共通点がない主人公にしたところ、一気に好きなこと――、無駄な話、余計な話、ウソの話を好き勝手に書けると発見しました。
そこに到達するまでに7年くらいかかりましたけど、「こっちの路線のほうがいいんちゃうか」と思って『鴨川ホルモー』を書いたら突然デビューできたので、その後はこの作風で行こうと迷わなかったです。
それでもやっぱり反抗期というか、あれこれ試したいお年頃だったというか、真面目な歴史小説へのあこがれから『悟浄出立』(新潮社)、全力で変テコ・ファンタジーにのめりこんだ『バベル九朔』(KADOKAWA)などを書いたりもしましたが、今はその時その時で一番いいと思うものを書けばええわ、と思っています。
――昨日、選考委員の講評でも日常の中にふわっと非日常が入ってくる、そのバランスの良さが評価されていました。そういえば前に好きなファンタジーについて、パターンに分けて説明してくださいましたよね。
万城目 竜が登場する物語には3パターンあるという話ですね。『指輪物語』のように、はじめから竜がいる世界で話が展開するパターン1。
『ナルニア国物語』や『ハリー・ポッター』シリーズのように、こちらに日常があって、扉の向こうに異世界があって、お互い干渉しない、行っても帰ってくることができるのがパターン2。
パターン3は、何の説明も注釈もなく、この日常のどこかに普通に竜が存在している話。僕はパターン3を採用しがちなんです。そっちのほうが想像の余地があるというか、読み手としても書き手としてもイマジネーションを刺激されるんです。
この場合、はじめからあるものはあるというテイで話が進むので、説明なしに非日常が作品のなかに紛れこんでくる。ただし、やりすぎると嘘くさくなります。自分では日常が9割、非日常は1割の案配で書いています。

「今までは直木賞が横にいて…」
――受賞してメンタル的に楽になって、今後万城目さんの中で何かが変わっていくんですかね。
万城目 どうですかね。1年前に受賞している小川哲さんには「権威を持っちゃったから、いじけキャラはもう使えないですね」って言われました。確かにいじけて厭世的に振る舞うスキルは、使い勝手もよく、かなりレベルアップしていたのに強制ジョブチェンジです。
――これからは何キャラになるんですかね。
万城目 なんやろ。案外、アイデンティティーにかかわる深刻な問題かもしれない(笑)。今までは直木賞が横にいて、一緒にぼやき漫才をしてくれていた。観客のウケもよかったのに、受賞したことでひょっとしたらコンビ解散してしまったかもです。今までは、どんなに文句を言っても受け止めてくれて、直木賞に甘えていたのかもしれない。獲ったらいなくなる存在だったのか、直木賞。
――ピン活動開始ですね。では、次の刊行物は何になりますか。
万城目 「六月のぶりぶりぎっちょう」を入れた単行本になるのかな。京都という街で、生者と死者がすれ違う話であることは共通していますが『八月~』とは対照的な内容なので、A面とB面のような関係性の本になると思います。レコードやカセットを知らない若者のみなさん、古いたとえですみません!