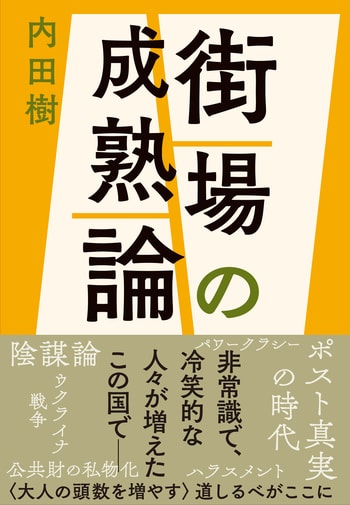〈「決して正解は教えない」孔子、親鸞、レヴィナス……偉大な師ほど弟子を“徹底的に困らせる”訳〉から続く
『街場の成熟論』が版を重ねる内田樹さんと、稀代の作家・高橋源一郎さんが身体性と成熟について語り合った。
◆◆◆
高橋 成熟というものを考える上でとりわけ重要なのが、鶴見俊輔さんだと思うんです。内田さんにとってのレヴィナスのような存在で、僕は毎回読むたびに新しい発見があるんですね。一番最初に中学生で読んだときは、生ぬるくてつまんないなと思った(笑)。「べ平連とか言って甘いな」なんて馬鹿にして。生意気ですよね(笑)。

内田 中学生だとそうでしょうね(笑)。
高橋 それから50年経って鶴見さんは93歳で亡くなられましたが、晩年に『もうろく帖』というノートを書いて亡くなられたんです。鶴見さんが本当に凄いなと思うのは、戦争論、転向論、大衆文化論、漫画論と、戦争に行った自分がどうしてもやらなくてはいけないもの、自分が経験したものと取り組んで、それらを一つずつ哲学化していることです。だから、どの言葉も身に沁みる。
そんな鶴見さんの最後のテーマが老いだったんですね。それはある意味必然ですよね。そして、鶴見さんはあるとき、「老いの本質はもうろくにある」と気がついた。でも、哲学のテーマとして研究しようにも、そもそも、もうろくすると研究そのものが不可能になるんじゃないか? そう考えた。そして、どうしたかというと「もうろくの中にもうろくを研究する方法を見つける」ことにしたんですね。
ちょっとずつもうろくして日が陰っていく中で、ひたすら老いの本質を調べていく。そもそも、もうろくがわかるのは老いてくたばっていく人間だけだから、明晰な人間がどんなに分析してもわからないコアみたいなものが、もうろくの只中にある鶴見さんと一緒に立ち上がってくる。そして91歳のときに「自分はのっぺらぼうの仏像になるだろう」と書くんですね。
その後、鶴見さんは脳出血を起こして、最後の2年間は、言葉も発せず、一行も書かず、本だけを読んで亡くなった。そんな晩年も踏まえると、鶴見さんってほんとうに身体的な思想の持ち主だったと思うんです。
内田 壮絶ですね。実はこの間、体育系の学会で、大学の体育の先生たちを前に基調講演をしてきたんですけれど、そこでこんな話をしたんですね。
みなさんは子どものときから身体能力が高くて、アスリートとしても立派な成績を残し、賢いので、それから大学院に行って博士号を取って、今では大学の体育の先生をされている。でも、そういうキャリアの方たちって、学校で体育の成績にずっと3とか2とかをつけられてきた子どもたちの気持ちはなかなかわからないと思うんです。みなさんはたぶん日本のアスリートをどうやって世界のトップアスリートにするか努力されている。自分が教えている中で「一番身体能力の高い者」に最優先に、場合によっては全部のリソースを注ぎ込む。それほど身体能力のない95%の子どもたちにはほとんど関心を向けない。
でも、学校で「運動神経が鈍い」とか「身体能力が低い」と判定された子どもたちだって、みんな身体を持っているんです。身体を使う喜びを経験したいと思っている。自分の身体に敬意を持ちたいと思っている。でも、そういう95%の「ふつうの子」には体育の先生は興味がない。一人一人が蔵している可能性を最大化する仕方って、教えないじゃないですか。僕は数百万の「鈍くさい子」たちが自分の身体可能性を開花させることの方が、大谷翔平をもう一人つくるよりも身体教育としてはずっと大事なんじゃないですか、ということを申し上げたんです。
高橋 本当にそうだよね。
内田 僕自身は、子どものときに心臓弁膜症になって、中学卒業するまで激しい運動ができなかったんです。ふつうの子どもは、外で遊びながら身体の使い方を覚えてゆくわけですけれども、その経験がごっそり抜けているんです。だから、大人になってから身体の使い方を体系的に学ぼうと思って武道の道場に入った。それしかやり方がなかったんです。たまたま幸運にも多田宏先生に出会って、自分の身体を使う喜びを知ったわけです。
身体能力が高い人が経験する「身体を使う喜び」と、身体能力が低かったり、身体が弱かったりする人が、工夫しながら自分に割り当てられたわずかな身体資源を活用して動く喜びは、ずいぶん違うものじゃないかと思うんです。
もうろくの話に戻すと、弱い体・動かない体・衰える体を通じても、身体を使う根源的な喜びを発見することは可能じゃないかと僕は思うんです。

高橋 もうろくに宿る老いの本質は、鶴見さんが最後に残した宿題のように思います。おそらく、人間的な変化のプロセスの本質的な形がそこにはある気がするんですよ。
鶴見さんもまた体が弱い人だった。だから彼の思想は自分の生きた経験、身体に裏付けされたものに基づいていた。老いってダイレクトに身体的な問題ですよね。歩けなくなる、膝が痛い、よく眠れない、腰が痛い、そして記憶力が無くなってくる……昨日より今日と、少しずつ、でも確実に衰えていく中で、「自分」でいられるにはどうしたらいいかというのが、鶴見さんの最後の15年のテーマでした。老いていく身体――そんな自分を世界と向かい合わせながらどんなふうに最後に向かっていくのかを実況中継してくれている。
僕はああいう仕事が最後にできるといいなと思っているんですよ。僕の書く小説には身体が出てこないから。
内田 えっ、そうなの? 若いころこのまま土建の専門家として生きていこうと思っていたら、腰を痛めてしまったのを機に小説を書き始めたんじゃなかったっけ。
高橋 でも、そういうことは全部、小説の外側に置いておくことにしています。だから、小説を書くとき何の情景も浮かばないし、外形的な想像もしないし、描写もしない。僕は、たぶん言葉しか見ていないと思います。ある意味で、親鸞と一緒ですね。言葉を見て、言葉について、言葉のことを書いている。
『ぼくらの戦争なんだぜ』のような戦争をめぐる批評でも扱うのはあくまでテキスト。戦争小説だったり、兵士が戦場にいって書いた手記や詩についてのみ書いています。あるいは戦争をめぐる言説について。書かれたテキストについてならきちんと分析できる自信があるんです。
内田 現実そのものではなく、そこから派生した言葉を分析しているということですか?
高橋 そう。シャーロック・ホームズの兄のマイクロフト・ホームズっているでしょ。絶対に自分の机から、動かない人。兄のほうは現場には行かず、聞いた話だけで推理をするんだけど、シャーロックより正確なんですね。僕は、マイクロフトタイプ(笑)。
内田 なるほど、高橋さんて病的なまでに英知的な人なんですね! 貴重なことを聞きました(笑)。僕は身体感覚による裏付けがあるものしか言葉にできない体質なんです。ぼんやりした、星雲状態のアモルファスな身体経験を、できるだけ明晰な言葉にしたいというのが僕の願いなんです。
身体と言語ということについて言うと、アルベール・カミュが僕の理想なんです。カミュはすばらしく感度のよい、上質な身体を持っている一方で、常人ではなかなか言葉にできないような微細な身体感覚を言葉化できる卓越した言葉の使い手でもあった。だから、カミュにおいては、身体感度を上げてゆくということと、鮮度の高い言語表現を達成することが一致していた。これは稀有の例だと思います。

高橋 なるほど、僕にはできないと思っちゃうけど(笑)。もう一つしたい話があって、しばらく前にミュージシャンの大友良英さんと話をしたんですよ。彼は、僕の8つ下で59年生まれなんですが、音楽に関しては共通体験がある。それは、中高時代に大友さんが触れた音楽はすべて「誰々君のレコードを借りて聴いた」「誰々君が弾くのを聴いて知った」と、友人の固有名詞付きなんですね。受験校にいて、早熟の天才に囲まれていた中・高校生時代、僕が触れるものは、音楽にせよ本にせよ、すべて友人経由だったのとよく似ています。
それから、大友さんは高柳昌行という有名なジャズギタリストのもとに習いに行っていたそうですが、そのたくさんの弟子たちのなかで一番下手だったと言っています。渡辺香津美のような天才は、弟子が普通2年かかるメソッドを3か月でやってのけてしまう。だから大友さんは、自分は何をやっても下手で遅いという感覚をずっと持っていた。でも気づいたらミュージシャンとして残っているのは自分だけだった、と。
僕も同じで、周りが天才ばかりだったので、詩を書いても、小説を書いても、ジャズを聴いても、映画を見ても、全部誰かに劣っていた。自分には突出したものが何もなくて、ずっと自分が一番遅れているって思っていました。けど、気がついたら残って、いまも書いているのは僕だけだった。
「二人とも遅れて良かったね」って話をしていたのですが、僕は決して文章のエリートではなく、いまだにどこかで「いつか作家になりたい」と思って書き続けています。この「遅れている」という意識こそが、作家を成熟させていくのかもしれませんね。そこには終わりがないのだから。
内田 レヴィナスに、「始源の遅れ(initial après-coup)」という言葉があります。自分は世界の創造に遅れてやってきたという、人間における宗教的覚醒のことなんですけれど、信仰の一番基本にあるのは、この「遅れている」という感覚だとレヴィナスは言うんです。この世界には自分がやってくる前にすでに「誰か」がいて、その人が設定した場に自分は後から参入してきた。そこがどういうゲームのルールで成り立っているかはわからない。でも、すでにプレイヤーとしてそのフィールドに放り込まれているから、何かしなければいけない。必死にプレイをしながら「これは一体どういうゲームなのか」「このフィールドはどういう構造になっているのか」「自分はプレイヤーとして何をすることを求められているのか」を学ばなくてはならない。それを「始源の遅れ」と言う。
高橋 まさにそれ!
内田 レヴィナスはそれを一神教信仰について語っているわけですけれども、師に就いて武道を修行することもそれと同じなんですよね。弟子はやっぱり「始源の遅れ」のうちにいる。修行しているんだけれど、どういう目的地に向かっているのか、自分は全行程のどの辺にいるのか、このあと何をしたらいいのか、そういうことは決して一覧的には開示されない。先生に「僕はいったい何をしているんですか?」と訊いても、そのつど違うことを言われる。多田先生もそうですし、孔子も、親鸞も弟子の問いに対してそのつど違うことを即答する。
高橋 鶴見俊輔さんは息子に「自殺していいか?」と聞かれたさい、「してもいい、二つのときにだ。戦争にひきだされて敵を殺せと命令された場合、敵を殺したくなかったら、自殺したらいい。君は男だから、女を強姦しそうになったら、その前に死んだらいい」と即答しています。
普通、重大な問題には軽々と答えず熟慮したほうがいいと思われていますが、逆なんですよね。人生で重大な問題ほど、即答したほうがいい。それもひとつ師の役割かもしれません。僕は鶴見さんに倣って、大学で教えていた頃、新入生のための5回の特別ゼミの最終日には、学生たちに「どんな質問をしてもいいよ」と言って答えることにしていました。もちろん即答です。「何のために結婚するですか?」とか、14年やって、4000人くらいからの質問にすべて答えました(笑)。

内田 すごい!
高橋 これって一々考えてから答えていたら即答できないんです。でも、「身体」は「自分」の答えを知っています。正解を答える必要はなく、自分にとっての答えを伝えればいいわけです。というか、そもそも、この世界で起きる問題に正解なんてないものだしね。そして、それが、なぜか、生徒からの質問へのいちばんの回答になる。さっきの小説のときとは正反対ですが、身体性がすべてに優先している。鶴見さんの考え方の根本にあるのは、身体性に基づいたプラグマティズムなんですね。
内田 鶴見さんの原点は、ハーバード大学を出るときに敵国民として捕まって、監獄に入れられていた体験にあると思うんです。そのとき、最後の交換船で出国するわけですけれども、このとき逡巡せずに即答する。「帰ります」って。鶴見さんにはこの戦争で日本が負けることはわかっていたし、大日本帝国の戦争指導部に一片の共感も感じていなかった。でも、負けるときは負ける側にいたいと思った。この話を鶴見さんは繰り返し書いていますよね。でも、それはたぶん鶴見さん自身にも、自分がなぜあんな決断をしたのかがわからなかったからだと思うんです。なぜ、自分は敗けるとわかっている国に戻ると即答したのか。その「わからない自分」を一生の宿題にした人のような気がします。
高橋 ちょっと卑近な話でいうと、僕5回結婚してるんですが(笑)、やっぱりさっさと決断してきたわけです。
内田 そのつど、即答してきたの!?
高橋 うん、即答(笑)。それで後悔をしたことはない。いや、正確にいうと、失敗はいっぱいしているんだけど(笑)、後悔はしていません。そのとき、そう思った身体の判断は尊重しないといけないと思う。その後は、そこから発生する責務を粛々と負えばいいだけだから。何か大事なことを決めるときに熟慮するのは、実は変だという感覚が、ずっとあるんだよね。
内田 それは、僕も全く同じ意見ですね。人生の岐路では、身体の声に直感的にしたがったほうがいい。成熟のもう一つの側面とは即答力である、ということで今日の話は締めくくりたいと思います(笑)。
高橋 ありがとうございました。
(紀伊國屋書店新宿本店にて)
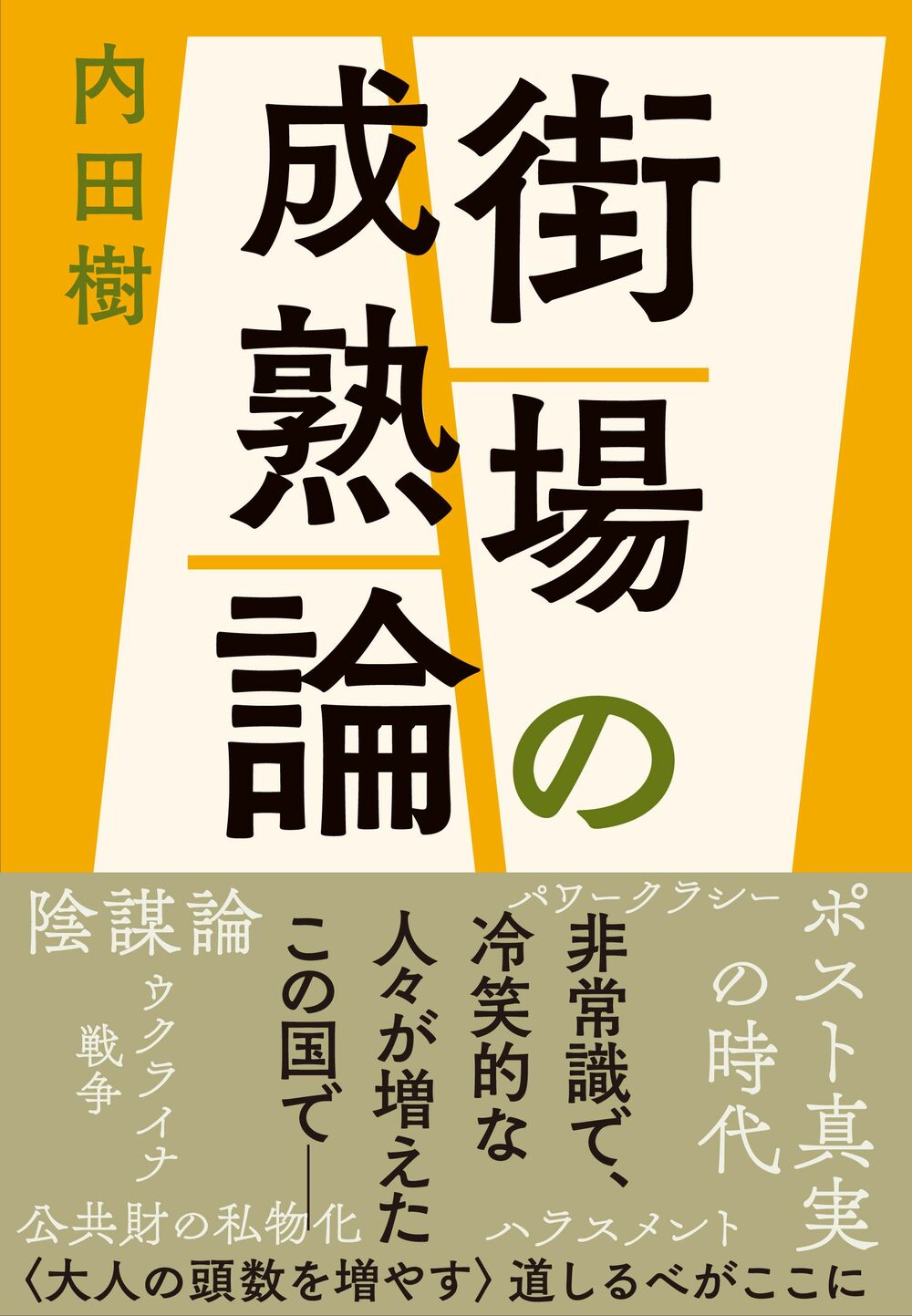

内田樹(うちだ・たつる)
1950年、東京都生まれ。思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。『私家版・ユダヤ文化論』で小林秀雄賞、『日本辺境論』で新書大賞を受賞。他の著書に、『ためらいの倫理学』『レヴィナスと愛の現象学』『サル化する世界』『日本習合論』『コモンの再生』『コロナ後の世界』、編著に『人口減少社会の未来学』などがある。
高橋源一郎(たかはし・げんいちろう)
1951年、広島県生まれ。作家、明治学院大学名誉教授。81年『さようなら、ギャングたち』で群像新人長篇小説賞優秀作受賞。88年『優雅で感傷的な日本野球』で三島由紀夫賞、2002年『日本文学盛衰史』で伊藤整文学賞、12年『さよならクリストファー・ロビン』で谷崎潤一郎賞を受賞。著書に『ニッポンの小説』『「悪」と戦う』『ぼくらの民主主義なんだぜ』『ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた』『ぼくらの戦争なんだぜ』『だいたい夫が先に死ぬ これも、アレだな』『一億三千万人のための「歎異抄」』他多数。