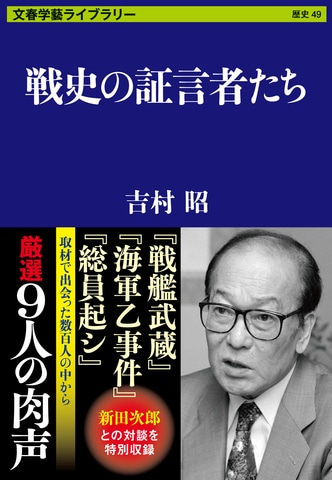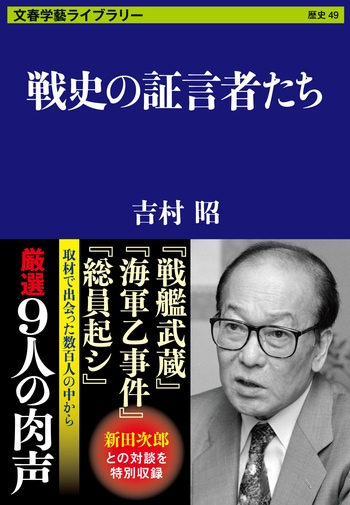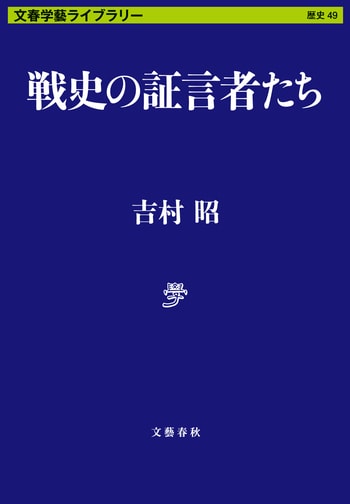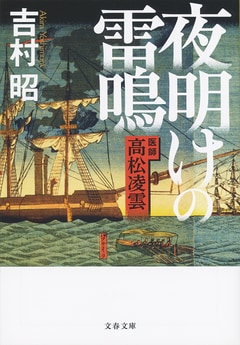人の話を聞く力が落ちている。しばしば、そうした声を耳にする。たしかに、マスメディアでインタビューの光景を見たり、記事を読んだりすると、質問が抽象的で、何を聞き出そうとしているのか、迷う場面に出くわすことがある。そんなことを言っているわたし自身、果たしてどれだけ聞く力を持っているか、心細くもなる。答える側も漠然としたことばしか繰り出せない、そんな問い方では話も弾まないだろう。話を聞く、しかも、その人の人生の大事な核心の部分にふれる出来事について聞くことは並大抵ではない。正面から人と向き合い、ひるむことなく話を引き出す技を、いったい吉村昭はどこで体得したのだろうか。
吉村昭は、丹羽文雄主宰の雑誌『文学者』で修業を重ね、『青い骨』(小壺天書房、一九五八年)や『少女架刑』(南北社、一九六三年)など、芥川賞候補作をふくむ短篇小説集を出した。その後、太宰治賞を受賞した『星への旅』(筑摩書房、一九六六年)で注目されたものの、一気に名前を知られるようになったのは、調査に調査を重ねて書いた、ノンフィクションもかくやという戦史小説『戦艦武蔵』(新潮社、一九六六年)からであった。文学を書こうとして目指していたのに、いったん文学を離れるかのように事実に即して書いた著作で、作家としての評価を獲得したのである。
実は、吉村は学習院大学に在学中、同人雑誌にこんなことを書いていた(注)。
……事実の中には、小説は無い。事実を作者の頭が濾過して抽象してこそ、そこに小説が生れる。カミュの「異邦人」の価値は、二十世紀の抽象小説であることだ。川端康成の小説も、畢竟作者の頭脳によって抽象された美であり、断じて現実美ではない。秀れた小説は僕達の理性を納得させ、感性を納得させてくれる。……
想像力が小説をつくりあげる。かれはそう確信していた。ほんとうにそうか。「事実を作者の頭が濾過して抽象してこそ」という、さりげない一言がある。しかし、「濾過」して「抽象」するまでに、どれほどの模索と葛藤の過程がおりたたまれているか、この時期の吉村にはまだ分かっていなかったのだろう。自然や社会の現実を描写すればいいわけではない。ある光景をあたかも目に浮かぶように描いたとして、それは語り手や焦点化された人物の内面の反映にとどまってしまう。自分の頭に収まりきらないくらいの「事実」の圧倒的な重量感を描くことの意義に気づいたとき、吉村昭はそれまで考えていた既存の文学概念から抜け出して、文学そのものに目覚めたのである。
その後、『零式戦闘機』(新潮社、一九六八年)や『陸奥爆沈』(同、一九七〇年)など、太平洋戦争のさなかに起きたさまざまな事件・事故に取材した小説を次々と発表。やがて、その対象は、日露戦争下の日本海海戦や、幕末維新期の内戦にさかのぼり、一方また苛酷な環境をくぐりぬけ、過剰なまでに生のエネルギーあふれた人間たちに及んだ。『羆嵐』(同、一九七七年)、『遠い日の戦争』(同、一九七八年)、『破獄』(岩波書店、一九八三年)、『天狗争乱』(朝日新聞社、一九九四年)など、吉村の著作の多くは今でも多くの読者を惹きつけている。
『戦史の証言者たち』は、吉村が戦史小説を書く上で取材した軍人や民間人の証言集である。一九六〇年代はまだ戦争体験者たちが健在であり、その記憶も保たれていた。百本以上に及んだ録音テープのなかから、一部を抜き出してまとめたものである。しかし、こうした取材やインタビューは吉村昭単独でなされたものである。大きな新聞社や出版社がバックについて、その支援のもとになされたわけではない。北海道から沖縄まで証言者たちの所在地におもむき、話を引き出していった。私はその執念と持続力に粛然とせざるをえない。経済的にはパートナーである作家の津村節子が彼を支え続けた。当時、しばしば吉村は親友に「おれはヒモだよ」と自嘲したという。証言者たちも、名前も背景ももたない相手を前にして戦争中の激烈な経験を語った。こうした数々の証言の書かれざる前には、それぞれが聞き手と話し手として立ち上がり、呼吸がととのうまでの長い間合いがあったにちがいない。彼らの警戒をほどき、ときに拒絶を乗りこえて、信頼を得るにいたるやりとりをへて、ようやく閉ざしていた記憶の封印が解かれたのである。
第I部の「戦艦武蔵の進水」は、『戦艦武蔵』を生み出した証言のひとつである。『戦艦武蔵』は数多くの関係者への取材から成り立っているが、ここに選ばれたのは、巨大な戦艦の進水を指揮したひとりの工作技師である。巨大な船を限られたスペースの港で進水させること自体、困難をきわめるが、まして機密保持のために戦艦の造船やその完成、進水式の日時まですべて隠さなければならない。ガントリークレーンにシュロのスダレをかけ、その上にさらにシートを下げたエピソードがくりかえし語られているが、分からなかったのは長崎市民だけではない。進水の神様と言われた大宮丈七氏みずからも、巨大すぎるがゆえに「ちょうど大きなビルの外壁の近くに立っている」ようで、船全体を見たのは進水後、海上に浮かんだときだったという。わずか二年二ヶ月に終わった巨大な「化けもの」の誕生と消滅のすべてを見届けたものはいない。発案した軍人たち、多くの設計技術者、発注された民間企業の職員、夥しい数の職工、そして乗り込んだ兵士・軍医たちそれぞれが各々の主観を通して、「化けもの」の断片を凝視し、記憶に刻んだ。その細部にこそ生きた歴史が宿っている。
本書の中心をなす第II部「山本連合艦隊司令長官の戦死」と第III部「福留参謀長の遭難と救出」は、それぞれ「海軍甲事件」「海軍乙事件」という小説のもとになった証言である。どちらも『海軍乙事件』(文藝春秋、一九七六年)に収録されており、照らし合わせることができる。
吉村は、一九二七年生まれの戦中派世代にあたる。戦後のアメリカへの従属と民主主義の到来を言祝ぎながらも、軍国主義批判の高まりによって、戦時下の真実がかき消されていくことに眉をひそめていた。戦争中にも日常があり、日本人の多くは黙々とみずからの仕事を続けていた。しかし、そうしたなかで戦争の拡大を防ぐいくつかの契機があったにもかかわらず、軍と一体となった国家はそのチャンスを逃し、隠ぺい工作をつづけた。「海軍甲事件」「海軍乙事件」という呼び方で匿名化された事件は、太平洋戦争における日本軍の失敗例である。ひとつは日本軍の暗号がアメリカに解読されていることに気づかないまま、連合艦隊の最高司令官をみすみす死なせてしまった。その護衛機に搭乗していた飛行士の生々しい証言は、戦争の潮目の転換がどのように起きたかを物語っている。もうひとつの捕虜交換事件は、ゲリラ討伐隊が救出部隊に転じたときの大隊長、捕虜引き渡しを担当した副官、捕虜となった参謀長機の搭乗員の立場から、それぞれ証言が引き出される。捕虜交換に現れたフィリピン人ゲリラがなごやかな空気のなか、「ノー・ポンポン」と、互いに銃を撃ち合いたくないという意思を示していたなど、印象的なエピソードが記録されている。そうした証言のあいまから、参謀長らが捕虜となった事実自体を隠し、その一方で兵士に死を強いた日本軍の不合理な精神主義が浮かび上がってくる。
第IV部の「伊号第三三潜水艦の沈没と浮揚」は、『総員起シ』(文藝春秋、一九七二年)に書かれた潜水艦沈没事故をめぐる証言が集められている。しかし、それにしても日本海軍は伊号第三三潜水艦について何度、事故を起こしたことか。最初に出撃したソロモン諸島方面で修理作業中に沈没し、三三名が犠牲になった。その後、引き揚げられ、呉海軍工廠で完全修理がなされたが、瀬戸内海で訓練中にふたたび浸水、沈没。乗員一〇二名が亡くなった。この潜水艦が稼働したのは最初は三ヶ月、二度目は二週間足らずである。もっとも科学的で軍事技術、造船技術の粋を極めたはずなのに、このようなミスがくり返される。しかも、ここでもやはり徹底した情報統制と隠ぺいが行われた。
この第IV部には、沈没する潜水艦から脱け出して救出された生存者二名と、戦後、引き揚げ作業にあたった技師と、浮揚した艦内に入り込み、生きたままのような状態で保たれていた死体の写真を撮影した新聞記者の証言が並んでいる。浸水しなかった完全密閉の一室で酸素がなくなり、低温で保存されていた遺体は九年後の引き揚げによって、戦後の空気のもとにさらされた。死体はみるみるうちに変色し、荼毘に付されたが、撮影された写真は死者たちのことばにならない無念を語り続ける。
最初の問いに戻ろう。証言者たちが重い口を開いたのは、なぜか。あえなく潰え去るとしても、彼らは戦争という巨大な歯車のなかで、心と身体に深い傷を負いながらも、黙々と職務に励んだ。そうした証言者たちへの敬意と、亡くなった人々への憂愁の思いを、吉村昭が身をもって呈していたからだろう。それは話術の妙などではなかった。
半世紀のときを超えて、ふたたび証言者たちは甦った。現実の戦争をめぐる報道が飛び交う一方で、戦争が比喩やイメージで語られる二一世紀の日本において、本書の価値はきわめて高いと思う。
注 吉村昭『戦艦武蔵ノート』(図書出版社、一九七〇年)より。