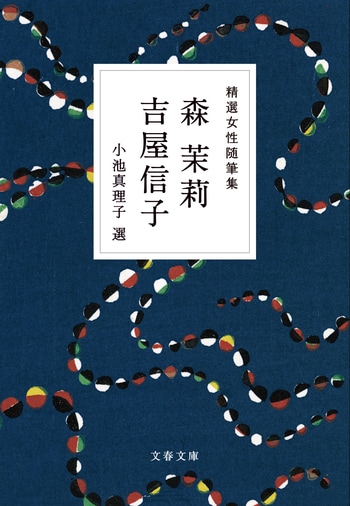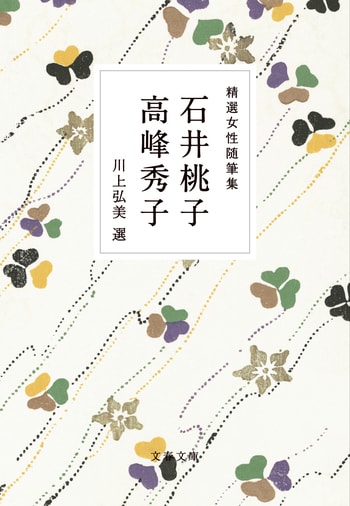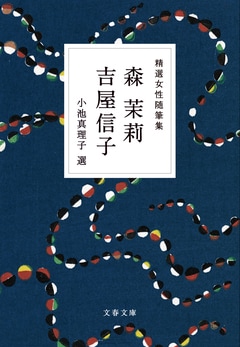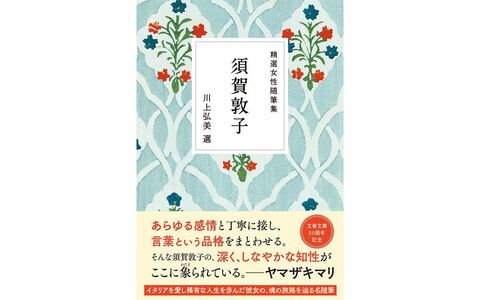小池真理子さんと川上弘美さん――現代を代表する小説家二人が、明治・大正・昭和時代を生きた女性作家たちの随筆を読み込み、今の読者のために選んだエッセイ・アンソロジー『精選女性随筆集』全12冊が今年、文庫になりました。
それを記念して、今秋、青山ブックセンター本店で行われた対談イベントを前後編でお届けします!(後編に続く)
構成・文春文庫
◆◆◆

エッセイと小説で自分を切り替えるか
小池 もう15年近く前のことになりますが、この選集の打ち合わせでお目にかかったのが、我々の正式な初対面だったかもしれませんね。物故作家たちのエッセイ・アンソロジーを編む仕事を依頼されて、受けてはみたものの、はたして自分に出来るのか、半信半疑で文藝春秋の会議室に行ってみたら……。
川上 明治、大正、昭和の女性作家の本や資料がたくさん並べてあった。二人とも決断が早くて、迷わずに、それぞれの担当する作家が決まった、という記憶があります。9人ずつ、全部で18人。小池さんは、森茉莉さんはじめ、小説を書く方を多く選ばれました。私は、不思議と、いわゆる「小説家」ではなく、高峰秀子さんのように、女優であり、そして素晴らしいエッセイを書く方、本業が小説家ではない人を中心に選んでいたんです。
小池 川上さんの作風というか、行間に滲み出る川上弘美的ふんわりした感じ、それに通じるものを感じさせる方々を、選んでいらっしゃいますね。私が選んだのは、これも無意識なのですけれど、理屈っぽいというか。
川上 論理的な人が多い。倉橋由美子さん、大庭みな子さん……。
小池 エッセイと小説、私たちは両方書きますけれども、作家で、小説は書いてもエッセイはあまり書かない方、いらっしゃいますよね。
川上 私が担当した中では有吉佐和子さんが、殆どエッセイを書いていなかったので、ルポルタージュなどから選びました。
小池 川上さんご自身は、エッセイを書くことと小説を書くことの間に違いを感じていらっしゃいますか。私はもともと、文筆の道に入ったきっかけが『知的悪女のすすめ』というエッセイ集でした。だから早いうちから、職人芸みたいな感じで、エッセイの書き方は体得していたのですよね。でも私にとって、小説を書くこととエッセイを書くことは全く違う。小説は、あらかじめ自分の中で物語の構想を練った上で、自分の観念性、抽象的な考え方を駆使して書いていく面白さがある。エッセイは、自分の内側から湧き上がってくるものを、どれだけ読者に分かりやすく表現できるか、ということなので、いつも頭の中では切り換えて書いていますね。
川上 私は実は、小説とエッセイにあまり差がないです。というのは、エッセイにも嘘八百を書いている(笑)。私、小説家になりたいと思っていましたが、その頃の一番の悩みは、絶対に自分はエッセイを書けないだろう、ということでした。
小池 そうなんですか。
川上 書きなさい、と言われたらどうしたらいいんだ、とすごく悩んでいました。ところが芥川賞をとったら、すごい勢いでエッセイの注文がくるんです。どこの媒体か忘れましたが、「作家になる前のことを書いてください」という依頼があり、「公民館のエッセイ教室を受講して課題のエッセイをたくさん書いたけれど全く良い評価をもらえなかった」というエッセイを書いたんですけど、ほとんど作り話(笑)。そして小説の方ですけど、幽霊が出てきても、ついてきても、自分は幽霊を見たこともないし信じている訳でもない。だから意識としては虚構を平然と書く、ただ、その中には、不思議と真実が含まれていたりするんです。また私の場合、自分の考え、たとえば「世界と人類が平和でありますように」という願いを込めた小説を書きたい、と言語化すると、もうその言語の外に出られなくなってしまう。そういう思いは、ぼんやりと、エクトプラズムのように(笑)体のそばに浮いていてもらいながら、感じていることをいかに文章にしていくか、ということが私の、文章を書く、ということなので、そういう意味で、小説もエッセイも一緒かもしれないです。
エッセイの語り手は誰なのか

小池 私、4年前に夫が亡くなったのですけれど(作家の藤田宜永氏。2020年1月に永眠)、すぐに編集者から熱心に頼まれて、朝日新聞に藤田との惜別の記録みたいなエッセイを連載したんです。その時期、巧く書こうとか、読者に分かってもらおうとか、野心や企みみたいなものがまるでなかった。それどころではない精神状態だったので。結果として、このエッセイ集『月夜の森の梟』が、これまでの中で一番いいものを書き残すことができたと思ってます。私は物語作家なので、小説は、どうしても、ある種、たくらみます。でもエッセイは、たくらまずに、時に秩序みたいなものも無視して、溢れ出て、零れる言葉を並べていくだけで、十分に読者と作家がつながることが出来る、ということが、この年になって、初めて分かりました。
川上 私、リアルタイムで拝読していました。もちろんエッセイで、実際におこった藤田さんの死、それをご自分がどう受け止めて、今どうやって生きているか、という現実のことを書いていらっしゃるのだけれども、なにか、小説を読んでいるような気持ちで、いつも読んでいました。つらい時もたくさんあっただろうな、と思いますが、祈りのようなものが結実した、小説ともエッセイともつかぬ、小池さんの創造物になっている。
小池 同じ時期に、連載小説も書いていたのですが、こちらは、以前のようにすらすら書けました。おそらく私の中であるメカニズムが働いて、小説の場合は、虚構の世界として受け入れて、自分がその虚構の中に飛び込んでいけば、現実でどれほどつらい体験をしたとしても、絶望を感じたとしても、書けてしまうんじゃないかと思う。
川上 藤田さんが亡くなったということとは、別の場所で、その小説を書いていた、ということですか。
小池 もちろん生身の人間だから、半分は、意識の中にいつも藤田の死があるのですけれど、そのことで覆いかぶさってくる諸々の感情が、小説に影響することはなかったです。
川上 私はそれ、逆かもしれません。たとえば、すごく信頼していた人に裏切られるとか、落ち込むようなこと、腹が立つようなことがあった場合、小説が微妙に変わる。
小池 私の場合は、最初に構築した物語からはずれまい、とすると、落ち込んでも、またその物語の中に戻っていくんですよね。
川上 なるほど、長編だとそうかもしれないです。でも私は短編を書くことも多くて、するとその時の感情が色濃く出てしまうことがある。自分にしかわからないですけど(笑)。それで憑き物が落ちて、次に行ける、ということもある。ただ、小説にはネガティブな体験が活かされてくれることがあるのですけど、エッセイには出ない。小池さんと逆ですね。
小池 川上さんの『東京日記』、私、愛読者なんです。一度、家で転んで足を骨折して療養していた時、送ってくださって、読んですごく救われました。
川上 『東京日記』は今、「ウェブ平凡」で毎月一回連載しています。もう二十五年以上続いている。
小池 今、何巻目?
川上 七冊です。
小池 川上弘美という作家の個人的な生活がそのままあるのかな、と思いながら当然読むのですが、サラッとしていながら、不意に、読み手を別の世界に連れて行く。
川上 『東京日記』は、わりと、実際に起こったことを書いているのですが、読者としては生のものをさしだされたと感じるかな、と思ったら、脚色してまったく雰囲気を変えます。「中の人」である私と、『東京日記』の語り手は、違うんです。
小池 「中の人」?
川上 そもそもは着ぐるみに入っている人を指したと思うのですけど、ある役柄を演じている俳優自身などのことを「中の人」と言ったりします。昔は、悪役、敵役を演じると、その俳優自身が憎まれたりしたけど、今は「中の人(俳優)と役柄の人とは違う」と、みんな承知している。エッセイに書かれている「川上弘美」と、「中の人」である生の私は、微妙に異なっているんです。
小池 なるほど。ものを書く、文章を書く作家という種族は、不思議なものですね。
川上 演じているようなところがありますね。
小池 演じていますね。
川上 この『精選女性随筆集』の書き手たちは、どれぐらい、それを意識してやっていたのでしょう。武田百合子さんは、夫・武田泰淳さんのお葬式の席で、中央公論社の村松友視さんに依頼されて書き始めたけれど、最初の『富士日記』から、文体がはっきりしていて、武田百合子としか言いようがない。
(後編に続く)