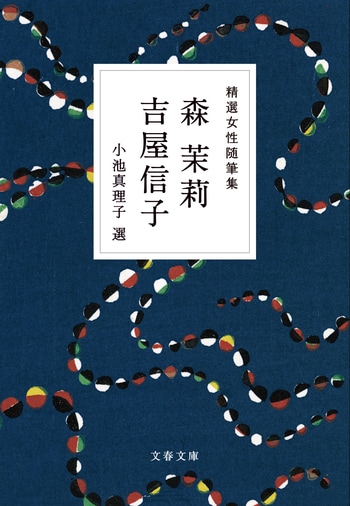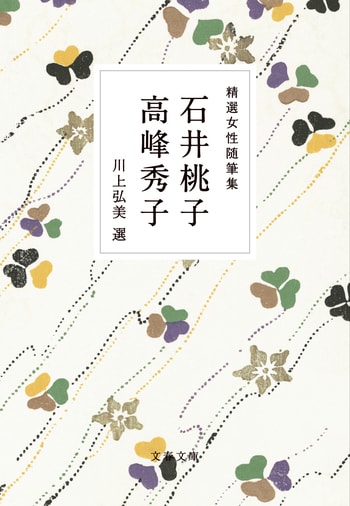〈エッセイと小説はどう違う? 対談 小池真理子×川上弘美〉から続く
小池真理子さんと川上弘美さん――現代を代表する小説家二人が、明治・大正・昭和時代を生きた女性作家たちの随筆を読み込み、今の読者のために選んだエッセイ・アンソロジー『精選女性随筆集』全12冊が今年、文庫になりました。
それを記念して、今秋、青山ブックセンター本店で行われた対談イベントを前後編でお届けします!(前編から読む)
構成・文春文庫
◆◆◆

近い距離、濃密な人間関係からうまれた傑作エッセイたち
小池 昭和の時代に活躍していた方々というのは、波瀾万丈な中を淡々と生きてきて、どれだけ大変だったことだろうと思うけれども、文章を読むと、懐かしさも感じるし、彼女らの人生を追体験するような面白さがありますね。石井好子さんがパリで三島由紀夫さんと会った時の話が可笑しい。三島さんは小柄で、石井さんはグラマラスな女性で、レストランに行くと、お店の人が石井さんの方に勘定書を差し出す。そのことに三島さんがちょっとムッとしたということが書かれていて、さりげないけれど、すごく観察力があります。
川上 文化人たちがよく交流していますよね。私などは、小説家の人たちとはあるのですけど、音楽家とか、画家とか、違う分野の方々と、対談の仕事でお目にかかることはあっても、個人的に訪ね合ったり食事をしたり、ということがない。
小池 当時は、人と人との距離がすごく近かった。
川上 作家同士でも、エッセイの中に交流のエピソードを書くというのは、今だったら遠慮しちゃったりする。でも、昔は書けた。だけどその場合、背後に濃密な人間関係がないと書けないはずです。
小池 白洲正子さんは、軽井沢に別荘をお持ちでした。この選集に、軽井沢で文壇の大御所、正宗白鳥の家を訪ねた時の話が載っています。筋金入りのニヒリストで、ヨレヨレの恰好で、「自分にたった一つ書きたいことがあるとすれば、それは『恐怖』というものだ。『此の世に生れて来たことのおそろしさ』だ」と元気に語る様子。こういう描写、中毒になるくらい面白い。白洲さんはあまりエッセイでご自分のことは書かれないけれども、本当にきちんとした目を通して人を観察している。随筆の真髄だと思います。
川上 ご自分の人生のことを書いている方は、たとえば高峰秀子さんや石井好子さん。どうやって今の職業の道に入ったか、その仕事をしていてどうだったか、ということを書かれていますが、ルポルタージュのように、かなり自分のことを客観的に書いている。一番主観的なのは岡本かの子。
小池 太郎ラブがすごいから。
川上 太郎とかの子は、一緒にいると、ぶつかってしまい、ダメだった。精神科のお医者さんに離れなさい、と言われ、太郎がパリに留学したのだそうです。でもその後の二人の手紙のやりとりも、激しく、そして愛に溢れすぎ。たとえば「毒親」という言葉があるけれども、今、太郎とかの子のような親子関係があったら、すごく異常な関係とくくられちゃうと思いますが、それをさらに越えている関係だと感じます。愛も束縛に近い執着もどちらも濃密で、その関係を、岡本かの子はもうそのまま書いているんです。そしてそれが作品になっている。
小池 宇野千代さんも、すさまじい恋愛を繰り返していましたね。かの子のように、夫と恋人とかの子と太郎が同じ家で暮らしていた、というようなことはなかったけれど、付き合いが重なっていた時期はあるだろうし、そういうことを割とあっけらかんと書いちゃう。「あの人いやね」と言う人はいたんでしょうけど、それが問題となる社会ではなかった。
川上 『生きて行く私』という毎日新聞の、宇野千代さんの連載が始まったのが、もう40年以上前ですね。その頃の価値観と、ここ10年くらいの価値観は、大きく変わりました。
恋愛小説とは何か?
小池 恋愛小説を書くのがすごく難しい時代になりました。恋愛が成立しづらい。関係性を善か悪か、で決めつけるから、不倫は絶対的な罪になる。恋はただ、落ちてしまうものだと思うんですけどね。性的欲望も同じで、これまた自然にわきあがってくるものだから、いいも悪いもない。そういう観点で私は小説を書いているので、どうしても設定として配偶者がいる人の恋愛を書くことが多くなる。一部の読者から、不潔で汚らわしいから読まない、などと嫌われてしまった時期もありました。でも、『アンナ・カレーニナ』や『ボヴァリー夫人』を例にあげるまでもなくて、世界の文学史に残る恋愛小説の多くは、許されざる恋がテーマになっています。現実の自分に引き寄せて読めば、こんなことを夫(妻)にされたら、許せない、ということになるのでしょうけどね。小説をそんなふうに読むのは、もったいないのひと言。

川上 私も、恋愛小説を書く小説家、と言われてきましたが、ずっと悩みがあって、素敵な男の人、を絶対に書けなかった。『センセイの鞄』という本が恋愛小説として皆さんが読んでくださるのですけど、あのセンセイだって、動物としてはかわいいけど、男の人としては、ちょっと違うんじゃないかと(笑)。去年、『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』という本を出して、それは、恋愛小説じゃないんです。老人小説なんです。60代の、昔からの知り合いの男女の話なのですが、コロナのもとで、会ったり会わなかったりするのですが、この小説で、はじめて、素敵な男の人を書けました。
小池 それは官能的というか性的な要素を省くことによって?
川上 意図して省いた訳ではないのですが。実は、恋愛って性欲部分がほとんどなのでは、と内心ずっと思っておりまして。
小池 私も思っていますよ。
川上 それなのに、なんでみんな、恋愛が素敵、と言うんだろう。ある年齢までは、性欲に衝き動かされることは、どうしようもなくありますが、そうではなくなった時に、本当に相手を見る、ということが一番素敵かな、と。
小池 年と共に失っていくものはあるけど、これまで知らなかったことがわかってくる。
川上 年取っていいこと、それですよね。
小池 ただ、性欲というと生々しいですけれど、性的な関心があるからこそ、異性に惹かれて、恋愛感情をいだくわけで、それがなければ恋愛小説、恋愛文学は成立しない。私達もそういう意味での恋愛小説を読んで、自分でも書いてきたと思うんです。でも今、この年齢になって、本当に、若い頃には夢にも思わなかったような、未知の世界が拓けてきました。
川上 人と人との関係は、いつも書いていたいことなのですけれど、それを恋愛に特化しなくてよくなった、というのが、この年になってすごく嬉しいことかな、と思います。
小池 私、古希を迎えました。今一番真剣に考えているのが、老い、そして死。万人に襲い掛かってくるものが見えてくる時期にさしかかった一人の作家として、何をどう書くか、ずっと考えてる。
川上 私は今、66歳。63歳を過ぎた頃、「しめた!」と思いましたね。これからは、多くの場合、小説の中で「おじいさん」「おばあさん」とくくられてきた60代以上の人たちを、実感を持って、細かく、具体的に書けるぞ、と。『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』は60代小説で、70代になったら70代小説を書きたいです。
小池 だけど私、コロナ禍の頃からすごく気になっていたのですが、高齢者、高齢者、と言われるけれど、もっと他の言い方がないものかと。
川上 え、わたしは自慢気に「前期高齢者だから」と言っていますよ。気に入っています。昔は「老人」と言っていましたしね。小池さん、「高齢者」の代わりの言葉を発明してください。
小池 うーん、「マダム」「ムッシュー」ではどうかしら。
川上 それ、やだなあ(笑)。
小池真理子(こいけ・まりこ)
1952(昭和27)年、東京生まれ。96年『恋』で直木賞、98年『欲望』で島清恋愛文学賞、2006年『虹の彼方』で柴田錬三郎賞、13年『沈黙のひと』で吉川英治文学賞を受賞。近著に『神よ憐れみたまえ』、エッセイ『月夜の森の梟』、短編集『日暮れのあと』など。
川上弘美(かわかみ・ひろみ)
1958(昭和33)年、東京都生まれ。96年「蛇を踏む」で芥川賞、2001年『センセイの鞄』で谷崎潤一郎賞、14年『水声』で読売文学賞、23年『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』で野間文芸賞を受賞。近著に『明日、晴れますように 続七夜物語』、エッセイ『東京日記7 館内すべてお雛さま。』など。