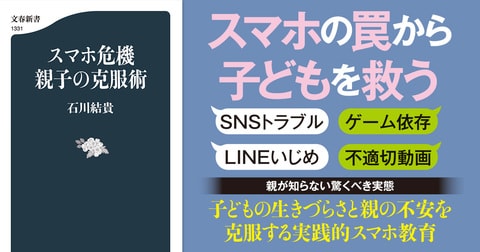〈「やられる勇気ある?」と言われ、答えられなかった…早稲田大学1年生がジャニーズJr.オーディションで経験した“その人”との出会い〉から続く
30年来のジャニーズ(現STARTO ENTERTAINMENT)ファンであり、『ジャニーズは努力が9割』(新潮新書)の著者でもある霜田明寛さんが、2023年の一連のジャニーズ性加害問題以降に感じてきた葛藤と思いを込めた『夢物語は終わらない ~影と光の“ジャニーズ”論~』(文藝春秋)を上梓した。
ここでは同書より一部を抜粋して紹介する。「キムタク」こと木村拓哉の人気が一過性のブームに終わらず今も健在であり続けている理由とは? その活動の軸にはどんな価値観があるのだろうか。(全3回の2回目/続きを読む)

◆◆◆
「キムタク」という商品であることへの葛藤
まず立てたいのは、ジャニーズ事務所の中で“芸能界”に生きたように見える人たちは、“芸事”へのこだわりはなかったのだろうか、という問いである。
ジャニーズ事務所の芸能界での大成功例と言えばSMAPだろう。91年にデビューした当初はジャニーズのグループとしては珍しくオリコン1位を取れなかった彼らが、バラエティ番組やドラマなどテレビを主戦場に大きな人気を得ていったことは、様々な場所で語られている通りである。芸能界で大爆発することで彼らは国民的アイドルグループになったといってもいい。
冠番組『SMAP×SMAP』は歌の時間的な割合は少なかったが、コントや料理対決も人気のバラエティ番組で、約20年の長きにわたり高視聴率ランキングに入り続けた。
少年隊の錦織一清はSMAPを「いろんなテレビ局に行って、メンバーを個別にして『笑っていいとも!』みたいなバラエティやドラマに入れていった。僕らとはまったく被るところのないグループだった」(※1)として“平成のドリフターズ”と形容しているが、ISSAも指摘したような演技に歌にバラエティにオールマイティーなグループ、という捉え方は多くの日本人が共有するものだろう。
だが解散から6年が経ったタイミングで、その指摘に「踊り揃ったことない」「なんちゃってオールマイティー」と木村が自虐的に語ったのは先に述べた通りである(※2)。これは“芸事”を生きてきた先輩のことも近くに見てきたからこそ、彼がどこかに感じてきた罪悪感が表出したものだったのではないだろうか。
ジャニーズ事務所どころか、平成の芸能界随一の成功例といってもいい木村拓哉。90年代、20代の木村拓哉が芸能界の最前線を走る大スターだったことは誰もが認めるところだろう。Supremeの服、リーバイスのジーンズ、クロムハーツのシルバーリングetc……彼が身につけるものは同性も多く買い求め、今でいうインフルエンサー……といった言葉にまとめてしまっては陳腐すぎるほどに、流行を作り出す活躍ぶりだった。
だがそんな流行の最中で、木村は、自分が商品として扱われることへの抵抗を示していた。それを如実に表しているのが「キムタク」という呼ばれ方への嫌悪感である。
木村は「キムタク」について「あるとき、自然に発生して、自分の意思とは関係なく、ダーっと世の中に広がっていった」(※3)と語っている。
さらにこうも述べる。
「キムタクっていうのは、メディアというフィルターを通ったり、何らかの他の人の力が加わったときに出てくるものでしょ。ま、一言で言っちゃうと商品だよね」(※4)
この発言がされたのは社会現象ともなる『ロングバケーション』と『SMAP×SMAP』が4月に放送開始する直前の1996年2月で、当時、木村拓哉・23歳。この若き日の発言は、自分と「キムタク」は別個であるという叫びのようにも聞こえるし、自分が「キムタク」という商品にされていることへの怒りでもあり諦念のようなものすら感じられる。
「自分をつくってるのは自分」という矜持
同じ96年2月のタイミングでこんな文章も綴っている。
「自分は、あくまで、“木村拓哉”っていう人間ではあるんだけど、同時に“SMAP”という商品でもある。ブランドって、その名前がついただけで、同じものが高く売れたりする。今、“キムタク”とか“SMAP”っていう名前が、ひとつのブランドみたいになってきちゃってる。でも、『俺たちを見たり聞いたりっていうふうに消費してくれてるみんなは、俺たちの価値って、どう位置づけてるのかな』ってときどき思うんだ。うちらの場合は、自分をつくってるのは自分。並べて売るのは事務所かもしれないけど、あくまでも、自分が自分の生産者」(※5)

SMAPとしてCDデビューしてから5年。すぐにブレイクとはいかず、やっとブームの波がやってきたその渦中である。むしろすぐにブレイクしなかったからこそなのか、舞い上がってもいい状況の中でこれだけ冷静に状況を捉え、客観視できる若者であったことに改めてその底知れなさを感じる。
この26年後、50代を目前にした木村拓哉は、当時を振り返って、やはり「キムタク」呼びが嫌だったことを語っている。
「20代の頃は、すごくイヤだったんですよ。『キムタク』って呼ばれるのが。人なのに商品っぽいっていうか。その呼び名でパッケージされて、店頭に並ぶ商品と同じ存在になった気がして」(※6)
キムタクという商品にされること――。それは、“芸能界”に生きることと同義のようにも感じられる。
20代の若者だった頃から、木村拓哉は自分の違和感を発信し、ときに拒むような態度すら見せていた。大ブレイクの最中にいながらも、商品として売られることに安易に迎合しないその姿勢は、芸能界に彼を消費させ尽くすことを許さなかった。その結果、 “キムタク”は一過性のブームで終わらず、今も健在だ。

キャスティングにも進言するプロデューサー気質
木村拓哉には、若き日の時点で“プロデューサー目線”を持っているという自負があった。以下は、1996年11月の言葉だ。
「仕事の現場では、木村拓哉っていうてめえ自身をてめえで見るっていうか、プロデューサー的な目で客観的に見る自分が必要だと思ってる。自分で自分にやらせる仕事がわかってないと、責任だって持てないし、それは周りに対して失礼だからね。以前は、仕事の状況は誰かが用意して、自分は単にその一部になってたこともあった。でも、今は“現場”の人。『スマスマ』だったら『スマスマ』の人。取材だったら、そこの雑誌の人。いつも、つくる立場のほうにいる」(※7)
自分が単なる一部、パーツになってはいけない、と作り手としての意識をも持つ。「アイドルとはお膳立てされるもの」だと思っていた錦織とも似た意識の変化を木村も辿っている。
そして“このプロデューサー目線である”というのは単に自負があるだけではなく、実際に行っていたことでもある。
1994年、木村拓哉は主演・萩原聖人の友人役で出演したドラマ『若者のすべて』に、自身の好きな映画『アウトサイダー』に内容的な近さを感じ、映画の主題歌であるスティーヴィー・ワンダーの「ステイ・ゴールド」を挿入歌として流せないか、とプロデューサーに“ゴリ押し”して流してもらったという(※8)。
挿入歌だけではない。1993年のドラマ『あすなろ白書』において、木村には男一番手である“カケイくん”のオファーが来ていた。一方、ヒロインに一途な思いを抱く取手くん役は筒井道隆のはずだった。だが、木村は筒井と相談の上、2人の役を交換できないかプロデューサーに提案。プロデューサーが「このドラマで人気が出たら、いまオンエアされているどのCMの誰のポジションに就きたいのか、イメージできているのか」を確認したところ2人とも明確なイメージができていたため、それを了承。結果、木村演じる取手くんの「俺じゃダメか?」という切ない台詞とともに後ろから抱きしめる“あすなろ抱き”は視聴者の心を釘付けに。木村の人気に大いに火をつけた(※9)。
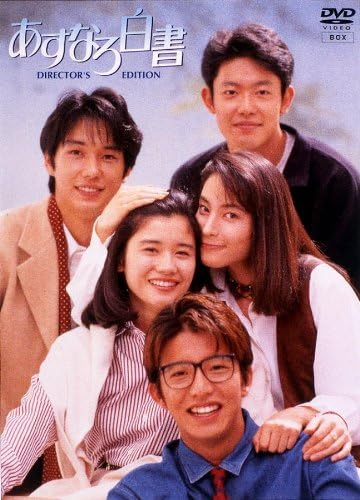
商品ではなく作品を作る
プロデューサーにも物を言うこの行為に対し、「生意気」と思う人もいたはずだ。木村拓哉を商品とみなし「アイドルだ」と高をくくっていた人には異質なものとして映ったかもしれない。
だが、木村拓哉はジャニーズ事務所で、アーティストとして自分の頭で考える教育を受けてきた人間である。これらの行動は、自身をも消費されかねない芸能界の中で、商品ではなく作品を作ろうとする、そして自分自身も作品であろうとする、20代の木村拓哉の必死の抵抗にも思えるのである。
ちなみに両作品とも、プロデューサーは亀山千広。この後、木村拓哉初の主演ドラマとなる『ロングバケーション』に加え、その翌年には『踊る大捜査線』で大ヒットを飛ばし、2013年に57歳でフジテレビの社長に就任した人物である。典型的なテレビマンに思えるかもしれないが、その実、浪人中に年間400本の映画を見て、大学時代には映画監督・五所平之助のもとで書生をしていたという映画寄りの出自を持つ(※10)。
90年代のフジテレビのドラマというテレビ業界のど真ん中にいるにもかかわらず、現場の人間として作品作りをしようとするこの木村拓哉の情熱は、受け入れる側も“芸事”寄りの人物だったことで成立していたということだろう。
《出典》
※1 「デイリー新潮」2023年2月2日配信
(https://www.dailyshincho.jp/article/2023/02021102/)
※2 TOKYO FM『木村拓哉 Flow』2023年3月19日放送
※3 木村拓哉『開放区』(2003年、集英社)
※4 「an・an」1996年2月23日号
※5 木村拓哉『開放区』
※6 「MORE」2022年5月号
※7 木村拓哉『開放区』
※8 TOKYO FM『木村拓哉 Flow』2021年8月29日放送
※9 「THE21」2008年5月号
※10 「就職ジャーナル」2015年8月17日配信
(https://journal.rikunabi.com/p/career/topproject/6885.html)
〈オーディションを3回もバックれた“ワル哉くん”だったのに…木村拓哉(52)が“日本で最も数字を持つ男”であり続けているワケ〉へ続く