2001年『インストール』で文藝賞を受賞し鮮烈なデビューを飾ると、2004年『蹴りたい背中』で芥川賞を受賞。以来、常に文学界の第一線で活躍し続けてきた、作家の綿矢りささん。「文學界」で4年にわたって連載された作品に大幅な加筆修正を加えた、集大成的長編恋愛小説『激しく煌めく短い命』が刊行されました。
物語は90年代半ばの京都から始まります。中学の入学式で出会った二人の少女、久乃(ひさの)と綸(りん)。惹かれ合い、手さぐりで愛をはぐくむ二人ですが、ある出来事をきっかけに決定的に引き裂かれます。そして十数年後、東京で会社員として働く久乃は、思いがけない形で綸と再会を果たすことに……。
「誰かを傷つけるのはこわいけど、傷つけなければ生まれない感情もある」と、語る綿矢さんは、この壮大な物語に何をこめたのでしょうか。
◆◆◆

「住んでる人も謎に思ってる」――京都の底知れなさと、謎の“山の音”
――本作は二部構成ですが、第一部では京都を舞台にした主人公たちの中学時代が描かれています。これまでも『手のひらの京』などで京都を描かれていますが、『激しく煌めく短い命』では少し違った側面、ある種のダークサイドも描かれているように感じました。
綿矢 そうですね。これまで京都のいい部分というか、自然の美しさとか、読んでいて楽しい部分を書いてきたんですけれども、今回は自分の学生時代を振り返り、いいことだけじゃない、京都のある一面も書いていけたらいいなと思いながら書きました。
――物語は、主人公の久乃が「山の音」を聞く、印象的なシーンから始まります。川端康成の小説を彷彿とさせるこの音は、いったい何なのでしょうか。
綿矢 実は「山の音」というのは、私が京都にいた時に家で寝る前に聞いていた不思議な音なんです。なぜその音が鳴っているかが今も分かってなくて。ボーッてこう汽笛みたいな感じの、鼓膜を直接震わせるような音が、窓を閉めても聞こえてくるんです。
家族もその音を聞いていて、「近くの山から聞こえるのかな」とか色々話したんですけど、大人になっても正体がつかめないままなんです。今回の小説を書く時にその音を思い出して、私の中の京都のイメージと、その謎の音っていうのがすごく密接につながっているなと。京都の持ってる底知れなさとか、住んでる人も謎に思ってるけど理由は分からないし、分からないままずっと謎に思っておきたい、というような気持ち。そういう京都の底知れないミステリアスさを象徴する場面として書きました。
――実際のところ、「山の音」が何の音なのか答えは出ていないんですね。
綿矢 山にこもって修行してる人がほら貝を吹いてる音なんじゃないかとか、給湯器の音じゃないかとか、ネットで調べると色々出てくるんですけど、それにしては街中に響いてるし……。本当に謎なので、もしご存知の方がいたら教えてほしいです(笑)。

自身の記憶から「大人になってから再体験したくて」描いた人権教育
――京都のミステリアスさ、生々しさという点では、作中の「人権教育」も重要な要素です。二人の恋愛にもこれが影を落としていきますが、綿矢さんご自身の経験がもとになっているのでしょうか。
綿矢 はい。私が小中学生の時、京都の授業では人権学習や平和学習が非常に盛んに行われていました。私はそれが全国的なものだと思っていたのですが、大人になってから、京都ではより手厚く行われていたと知りました。その時の授業はどういうもので、それを受けていた自分はどんな風に感じていたんだろう、というのを改めて考え直したくて。大人になってから再体験するような気持ちで、ほぼ、自分の記憶のままに書いています。
――当時は、その教育に違和感を覚えるようなことはありましたか?
綿矢 当時は他の授業と変わらず、道徳のような感じで純粋に受け入れていました。でも大人になってから思うと、教育によって差別があることを知り、歴史を知るということが、果たして良かったのかどうか……。もちろん、熱心に取り組んでくださった先生方や地域の方たちの真面目な思いもすごく伝わってきたので、悪かったとは思いません。ただ、そういう授業があったということを、生徒だった自分が大人になってからもう一度考え直すのも大事かなと思って、主人公たちにもういっぺん授業を受けてもらうことにしました。
なぜ女性同士の恋愛を描くと大長編になるのか
――綿矢さんが女性同士の恋愛を描いた、上下巻の『生のみ生のままで』を超える、本作は大長編となりました。女性同士の恋愛を描くと、物語が長くなる傾向があるのでしょうか。
綿矢 何でしょうね(笑)。おそらく心の動きを二人分書いていると、「もっと丁寧に書かないと、お互いがどうして好きになったか伝わらないんじゃないか」って思っているうちに、どうしても長くなってしまうんです。さらに今回は、第一部が中学生時代ということで、学校行事だったり家庭内の出来事だったり、時間の流れ方が大人の頃よりもゆっくりなこともあって、すごく枚数が必要になりました。
――いわゆる異性愛を描く時との違いはありますか?
綿矢 異性愛を書く時は、女性の主人公が相手の男性をちょっと偶像的に見て、恋焦がれるということが多いんです。でも、女性同士の恋愛になると、相手を神格化するよりは、もっと友達のような目線ではじまって、だんだん距離が近づいて恋人になる、というスタイルがあるみたいですね。
今回も二人は友達同士みたいな感じからはじまり、お互いのことを好きになっていきます。自分が恋愛小説の読み手の時も、じわじわ距離が近づいていくところを読みたいタイプなので、そういうところは書き込んだ方が、読み応えがあるかなと思って書いています。

性的な場面や喧嘩に込めた“生きてる”という感覚
――連載時から単行本化に際しては、かなり加筆修正をされていますね。特に二人の性的な場面には、最後まで細かく手を入れていらっしゃったのが印象的でした。
綿矢 性的な場面は、非常に情緒を必要とする場面だと思ったんです。二人は昔からの知り合いで、それまでに色々なことがあってそこに至るので、ただ、相手を愛し合うというだけじゃなく、もっと色々な思い出とか、相手への慈しみみたいなものがちゃんと感じられないと、感情移入できないなと――連載の締め切りに追われていると、完全に集中して書くのが難しい時もあって、単行本にする前にもう一度集中して、この場面についてはしっかり書き直しました。
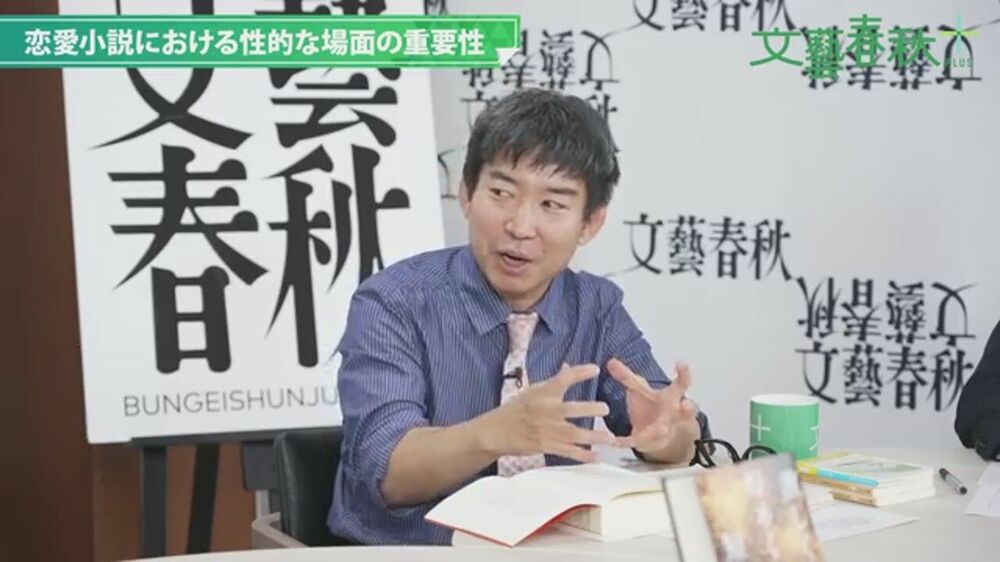
――綿矢さんの作品は、デビュー作から性的な場面をぼかさずに、はっきりと描かれている印象があります。
綿矢 ずるっと深みにはまっていくような感じで小説が進んでいくのが好きなんです。性的な場面は、読者を引きつけるためというより、結構自分のために書いていて。自分がそのシーンの深みにはまりたいから書いているので、カットはしたくないですね。
――自分のため? ですか。
綿矢 はい。ギアを上げるというか、自分の中でドライブ感を回すために書いています。性的な場面だけじゃなく、喧嘩したり、裏切ったり、ポロッと何かを言ってしまうとか、そういう動物的な場面もそうですね。こういう部分は、私の小説に魂がこもる、血みたいな感じなんです。そこをカットしてしまうと、どうしても「生きてる」っていう感じがなくなってしまうような気がします。理性で蓋をしている部分を、小説の中では解き放ってしまえる。書いていても面白いですし、そういう冒険の場でもあるなと思います。
平成という“異様だけどエネルギッシュ”な私の青春時代
――さまざまな激しいテーマを扱いながらも、本作は不思議と軽やかに、スイスイ読めてしまいます。随所に散りばめられたユーモアがその理由のひとつかと思うのですが、「笑い」は意識されていましたか?
綿矢 今回の小説は、あんまり笑いを意識はしていなかったんです。でも、主人公の久乃が真面目だけど突っ走るタイプの性格なので、笑いを入れようと思わなくても、だんだん笑えてくるような場面が時々あって。真面目すぎる人を書いても、逆にちょっと笑えるようなことが起こってしまうんだな、というのに今回初めて気づきました。
――第一部は90年代後半から2000年頃の中学校が舞台で、綿矢さんご自身の時代とも重なります。綿矢さんにとって、中学時代はどんな3年間でしたか。
綿矢 人生の中で一番よく記憶が鮮明に残ってる時代ですし、毎日がすごく新鮮でした。私にとっての青春って中学時代だったのかなって思うぐらい、みずみずしかったです。
――当時はコムロファミリーが活躍し、女子高生ブームがあったりと、特別な時代でした。
綿矢 私にとってもすごく変わっていて、異様だけど、すごくエネルギッシュだった特別な時代です。J-POPの影響もあったかもしれないですけど、その時代は女子高生に価値があったから、中学生の私は言いようのない焦りを感じていて。「女子高生が終わった後、自分の価値はなくなるのか」とか考えたりもして。今から振り返ると、なぜそんなに刹那的だったんだろうって思うほど、焦っていた気がします。高校生のうちに小説を書こうって思ったのも、その影響かもしれません。

作者も意識していなかった結末はハッピーエンドなのか?
――連載時は漢字四文字の『激煌短命』だったタイトルを、単行本化にあたっては『激しく煌めく短い命』に変更された理由は?
綿矢 連載時から、作中のどこかで「激しく煌めく短い命」という言葉を出そうと決めていました。四字熟語の『激煌短命』というタイトルも気に入っていたんですけど、単行本にするにあたって色々直しているうちに、できるだけクリアにしたい、伝えたいことをひねらずにそのまま言葉に込めたい、という気持ちが強くなってきたんです。それで、『激しく煌めく短い命』の方が頭に入ってきやすいかなと思いました。
――さらに意外なエンディングは、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのか、読者の間でも意見が分かれそうです。この結末は最初から考えていたのでしょうか。
綿矢 いえ、最初のうちはどうするか考えずに書いていったので、ラストは本当にこの登場人物の二人の決断、みたいなものが出たっていう感じです。自分であんまり意識してこのラストに持って行ったという気持ちはなかったですね。できるだけ幸せになってほしいという気持ちでは書いていたんですけど、私も最後までこうなるっていうことは意識せずに書いていました。
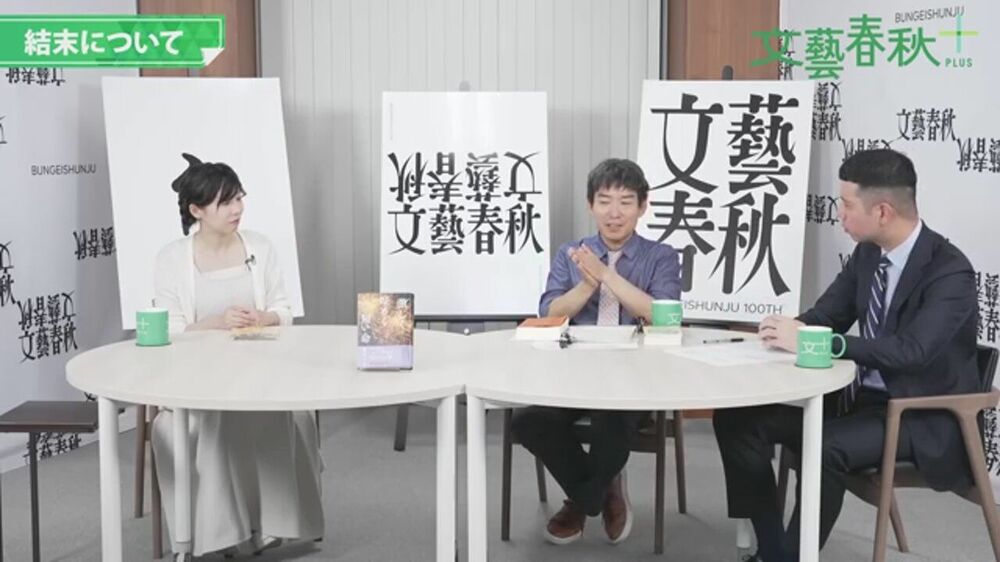
――まさに、作者も読者も、小説を通じて自分の知らなかった地平に到達できるという、長編小説の醍醐味が詰まっていますね。最後に、この本をどんな方に読んでいただきたいですか?
綿矢 日々、今日という日に適応するために精一杯で、過去を懐かしく思い出す瞬間が取れてない人も多いと思うんです。忘れ去ったままでいる中学時代や高校時代を、本を読んで思い出すことで、もう一度その時代に戻れたような感覚になってもらえたら、書いた方としてはすごく嬉しいです。平成時代っていうものをもう一度思い出してみたいとか、振り返ってみたいっていう気持ちがちょっとある大人の人に読んでもらえるのも嬉しいなって思います。
◆◆◆
人生の甘さと苦さがすべて詰まった、熱い恋愛小説『激しく煌めく短い命』。640ページという分厚さながら、一度読み始めると止まらないドライブ感で、読者は久乃と綸の人生を追体験することになります。懐かしくて新しい平成の空気とともに、圧巻の読書体験をぜひ味わってみてください。
※こちらのインタビューは文藝春秋PLUS公式チャンネルにて動画でもご覧いただけます。




















