「ハンチバック」執筆にあたり、市川沙央氏が大きな影響を受けたと語る『凛として灯る』の著者・荒井裕樹氏との往復書簡「世界にとっての異物になってやりたい」(『文學界』2023年8月号)は、掲載当時、大変話題になりました。文庫版巻末に全文を収録するとともに、【特別付録】として、2年ぶりに交わされた新たな往復書簡を追加、ここに公開します。(後編・荒井氏による書簡はこちら)
◆◆◆
市川沙央→荒井裕樹
荒井裕樹さま
『文學界』の往復書簡から早いもので二年が経ちました。これまでの二年間を振り返りますと、往復書簡のやりとりから程なくして二〇二三年七月に『ハンチバック』は芥川賞を受賞し、当事者作家としての作者ともども多くのメディアで取り上げられ、「読書バリアフリー」という言葉が一躍脚光を浴びることとなりました。
荒井さんとお目にかかって初めて直接お話しできたのも、同年八月の芥川賞贈呈式でしたね。
その二三年末には海老原宏美基金のイベントでの上映のため拙宅に荒井さんをお招きして対談させていただきました。私が「読書バリアフリー」を知ったのは、海老原さんを取材したNHKの記事がきっかけでした。二〇二一年十二月に海老原さんは逝去され、無念なことながらお知り合いになる機会はありませんでしたが、医療的ケアとともに生きる女性として声を残された海老原さんの、世の中に伝えるべきことを丁寧に伝えるその言葉には得難い響きがあったとしみじみ思い、足跡の大きさをずっと感じています。「読書バリアフリー」に関して、海老原さんの言葉を継いで世に広く知らしめることができましたことは、『ハンチバック』という胡乱な小説、通俗道徳に抗する破壊的な物語を書いた人間として、小さく――そして唯一――誇れる一部分だったように思います。
出版界からは「読書バリアフリーに関する三団体共同声明」(日本文藝家協会、日本推理作家協会、日本ペンクラブ)や、「読書バリアフリーに関する出版5団体共同声明」(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、デジタル出版者連盟、日本出版者協議会、版元ドットコム)といった声明が出され、関係者の方々のご尽力に心を打たれました。
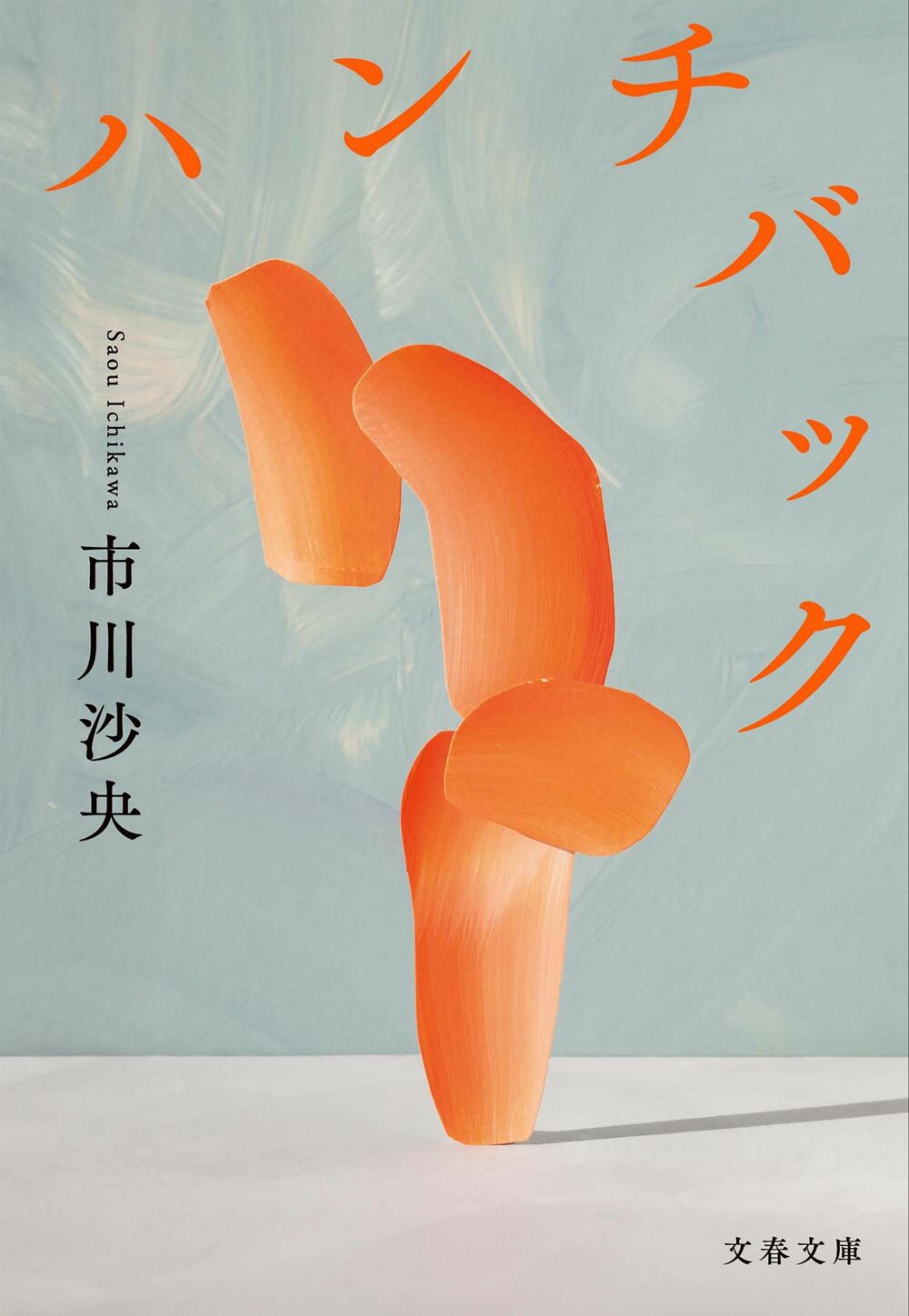
『ハンチバック』を発表してからの反響
往復書簡のやりとりを改めて読み返すと、おっかなびっくり初々しい語りをしている自分に苦笑いしてしまいます。二年の間には本来のお調子者の地金がちょろちょろと露出してきて、収拾がつかなくなりはじめてもいる今日この頃です。荒井さんに釈華を「世界にとっての異物になってやりたい」情念を抱く人物と解釈していただき、それがこの往復書簡のタイトルに切り出されてもいるわけですが、異物としての強度と一貫性を保つことの難しさとでも言いますか……。いえ私自身は世界の異物になってやりたいなどと思ってはいないのですが。思っていないのですが、私の言葉だと誤解している方が多いようなので、ここで誤解を解くとともに念を押しておきます。
そう、私はそもそも障害者を異物と見做して排除する社会に異議を唱えるために『ハンチバック』を書いたので、その主人公が「世界にとっての異物になってやりたい」情念を持つ者として読まれるというのも面白いことだなと思います。障害者につきまとう異物のイメージを何とかして消したい、無効化したい、解消したいと、あらゆる知恵を絞り策を弄しても、そのもがき方に異物という言葉が似合ってしまう。障害者につきまとうこの異物感が消えてなくなる日って来るんでしょうか?
釈華が「世界にとっての異物になってやりたい」という情念を抱えていたとして、その異物たらんとする自己像の殻を崩壊させてやる物語の構成までが作家の仕事と言えるのかもしれません。
『ハンチバック』発表以来の反響には、健常者(強者)としての罪悪感を感じた、という声が多くありました。それは作品の感想のみに収まらず、当事者作家として姿を現している私を障害者(弱者)側に置いてのものでもあったろうと思うのですが、しかし、その罪悪感は私にとって、とても馴染み深く、よくわかる感覚でした。むしろ、それは私が人生の大部分において感じてきた罪悪感でした。私にはできる⇔彼女にはできない、という強者側の罪悪感。感想をサーチしては、それはよくわかる、わかるんだよー、と心の中で呟いていました。その辺りから、「女の子の背骨」(単行本『女の子の背骨』文藝春秋刊に収録)という話を書く動機が生まれたのでしょう。「女の子の背骨」は、七歳上の寝たきりの姉がいる女の子の話です。姉妹は同じ先天性の難病を患っているけれども、いつでも姉のほうが妹よりも不自由で、妹は姉よりも自由。『ハンチバック』は私小説とは言いがたいが、「女の子の背骨」は私小説と言っていいかもしれないと私は位置付けています。しかしいずれにしても、『ハンチバック』の釈華は経済力の面で強者性を持ち、「女の子の背骨」の主人公は健常児と比べれば身体的弱者でありながら姉に対しては身体的強者である――こうした相対性、インターセクショナリティの提示によってあらゆる二元論の解体を試みることが、障害者につきまとう異物のイメージを粉砕するための、私なりのアプローチであると言えそうです。
ある一面では弱者であっても、別の一面では強者である――このようにして強者と弱者の相対性を自覚することは、誰であろうと必ず持つべき観点であり、現代の社会に広がる意識の分断に呑まれないためにも効果的な処方箋だと思っています。何よりも大事なこととして、こうした思考法を自己正当化のために用いるのではなく、相互理解ということを忘れないでほしい、絶対に諦めないでほしいと私は思います。
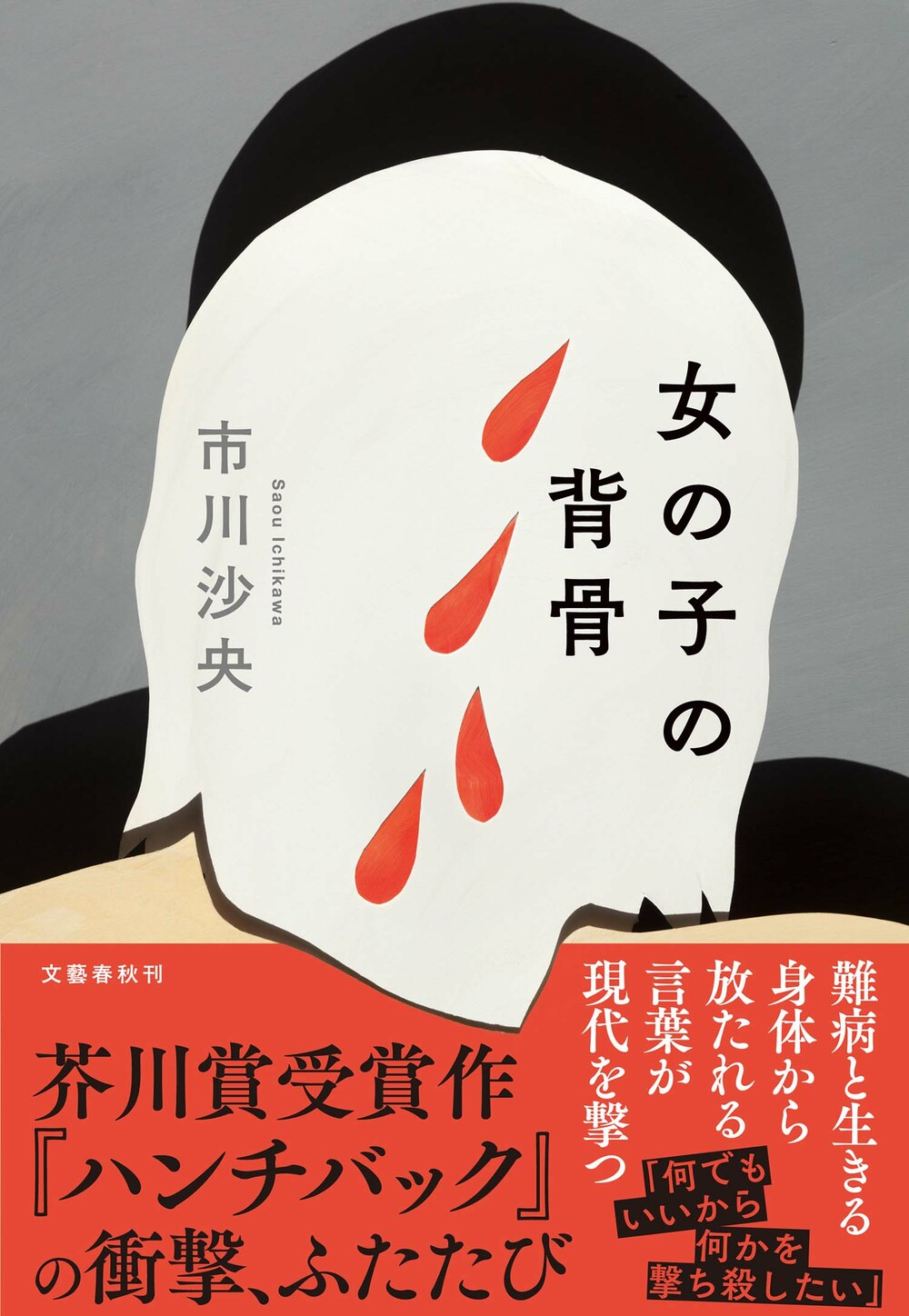
十代のころは、読書の力を信じていた
特に芥川賞の受賞以来、私が意識的に主張してきたのは、読書文化が象徴する読み書き能力の神聖化への警鐘でした。言葉を理解して喋れること、読み書きできること、言葉で感情や意思を伝えられること、勉強や発信ができること――社会にはそんな人間か、訓練すればそうなれる人間しかいないのだという思い込み。〈そりゃあ例外はいるかもしれないがあくまで例外であって社会の成員として数える必要はない〉とでも言いたげな、あらゆる知識人の言論。高等教育機関で学んだエリート(体力エリートでもある人たち)が社会を設計して動かしていること。これらの大本にある、言語能力を中心に据えた人間観。それらに対して無警戒で無邪気で無疑問であること。――つまるところ近代社会を基礎づける言葉信仰を、私はすべて問題視しています。小説家になっておいてあるまじきことですが、私は言葉というものを信じていません。
なぜ警鐘を鳴らさなければならないか。理屈ならいくらでも美々しい倫理を積み上げられるのですが、第二便ですでに「近代社会が自己決定権の印籠の元に、明晰な自己意志を持つ標準的な身体のみを社会に揃えることを目指しつづけ、不良品の排除を進めるというのならば、――」と、片鱗を記してもいますから、ここでは割愛します。理屈とは別に、私があえて警鐘役をやる理由は、ただ単に私が天邪鬼だからです。
私も十代の頃は、読書の力を信じていたんですよ。本を読めば他者への想像力が付いて思慮深くなれる。だからみんな本を読むべき。読書こそが人間と社会を成熟させる。本は素晴らしい。と純粋に思っていましたよ。しかしインターネットの発達とともに生きてきて、特にSNSの時代になって、年がら年じゅう喧嘩している学者・知識人やら、ガラス張りの図書館を紹介したライターに(紫外線が本を劣化させるのが許せないからって)口汚く苛烈な言葉を浴びせてののしる本好きたちなどを見ていると、本ってたくさん読めば読むほど人間をかくも攻撃的にするんですねえ、と嫌味の一つも言いたくなるではないですか。昔の文芸誌や言論誌で、ある程度の長文論考のやりとりを載せて成立していた論争になら一定の価値もあったように思うのですが、消え物でしかないSNS上の口喧嘩ほど不毛なものはない。彼人らは何を思って飽きずにあんなことを続けているのでしょうね。
知性!
意思の疎通!
自己決定権!
くだらない。

私がいちばん邪悪かもしれない
知性も意思の疎通能力も自己決定能力も備えた健常者が、毎日毎日やってることは喧嘩とか殺人とか憎悪煽動なのですからね。ケアで成り立つ障害者の世界のほうが、よほど人間性の防波堤になりえている。
ケアの現場が必ずしも優しくて温かいと言いたいわけではありません。もちろん人間愛の模範みたいな現場は多いけれども。しかし、生きるためにケアの手を必要とする障害者は、彼人らのようにいちいちくだらない思想上の価値観で他人の言動を善悪に分けて断罪して対立などしていたら、生きていけない場面もある。割り切ったリアリストでなければ、重度障害者の生活は成り立たない。本当は障害者だけでなく、この世界の誰でも、ありとあらゆる他者の手を間接的に借りて生きているのです。障害者はそれを直接的に体感してしまうというだけです。もちろん、何でもかんでも我慢して従属せよという話でもありません。
「目の前にナイフを持って向けられているのでない限り、どんなに思想の異なる人とでも友人知人にはなれるはずだ」と、私はインタビューでよく言っています。〈それでもあれやこれやの邪悪は例外でしょう? 邪悪を包摂はできないでしょう?〉と言ってくる人が必ずいるのですが、例外はありません。こちゃこちゃと理屈をこねて例外を作ればそこから近代社会の自由と公正と人権を支える理性は綻びていく。だから例外はない。邪悪というなら私がいちばん邪悪かもしれないし。
往復書簡の三便に渡っていろいろと書いてまいりましたが、私は小説の外ではとりわけ言いたいこともなく、締切と字数の要請で無理やり言葉を捻り出しているだけですので、私のことをあまり信用しないほうがいいのにな、といつもいつも思っています。私には、障害者として頻繁に街に出て障害者らしい苦労をしてきた経験もないので、私に一般的な障害者のことを訊かれても困ってしまうのが正直なところです。
荒井さんには事あるごと、メディアの取材に巻き込むかたちになってしまい、申し訳ないかぎりです。先日は『ハンチバック』英訳版の発売に伴うニューヨーク・タイムズ紙の取材でもお時間を割いていただき、どうもありがとうございました。帯文を採用していただいたご著書『無意味なんかじゃない自分』(講談社刊)では、『いのちの初夜』の作者・北條民雄の人物像が生々しく立ち現れる筆致に荒井さんのお仕事の真骨頂を見ました。北條民雄のあられもないプロ志向と野心が、あまりにも私のそれと似ていて赤面を抑えられなかったという話を、今度お会いした時にしますね。
市川 拝
(二〇二五年六月二十日)
〈読書バリアフリーは利便性ではなく人権の次元、あるいは社会的排除の問題として語られるべき。いまも文学そのものから遠ざけられる人がいる〉へ続く





















