〈壊れゆく世界で、法の砦を守る――国際刑事裁判所(ICC)と赤根智子所長が挑む「正義の最前線」〉から続く
第二次世界大戦終結後のニュルンベルク裁判、東京裁判の系譜を受け継ぎ、2002年に設立されたオランダ・ハーグに拠点を置く国際刑事裁判所(ICC)。赤根智子さん『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』では、二つの戦争とアメリカの制裁に対峙する奮闘の日々を綴った。他方、日本では今年6月、刑法改正にともない従来の懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化された。加害者更生と復帰支援の大きな変革期を迎えるいま、日本はICCの被害者救済の正義のあり方から何を学べるのか?新しい犯罪被害者支援、加害者の更生プログラムの可能性などを探る日本財団のプロジェクトチームとともにICCを訪問した訪問記。
被害者の救済を中心に据えた「修復的司法」というアプローチ
「修復的司法(Restorative Justice)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。従来の刑事司法が加害者に刑罰を科すことで犯罪を減らそうとする発想に基づくのに対し、犯罪によって引き起こされた被害をより被害者中心に繊細に捉え、様々な関係性の修復を通じて回復させようとするものだ。そこでは、被害は被害者本人が受けたもののみならず、加害者と被害者の関係、それぞれの家族や周囲の人々、社会にまで広く及ぶと考える。広範なダメージを修復するには、加害者の責任を問うだけでは足りない。加害者もまた問題を抱えていることが多い。複合的な要因が絡む加害行為の背景、加害者の心理にも目を向けつつ、加害者と被害者それぞれにおける様々な関係性の回復が目指される。
その過程では加害者・被害者をはじめ様々な関係者が対話の機会を持ち、話し合いを通じて互いの葛藤を伝え、心の回復や償いを模索するという実践の形が模索される。加害者は被害者の声を聞き、反省や謝罪のきっかけとする。そうすることで被害者の回復はもちろん、加害者の更生と社会への再統合、コミュニティが負った傷の回復、犯罪の抑制も促されると考えられるのだ。[i]コミュニケーションを重視したより包括的なケアが目指されているといえそうだ。
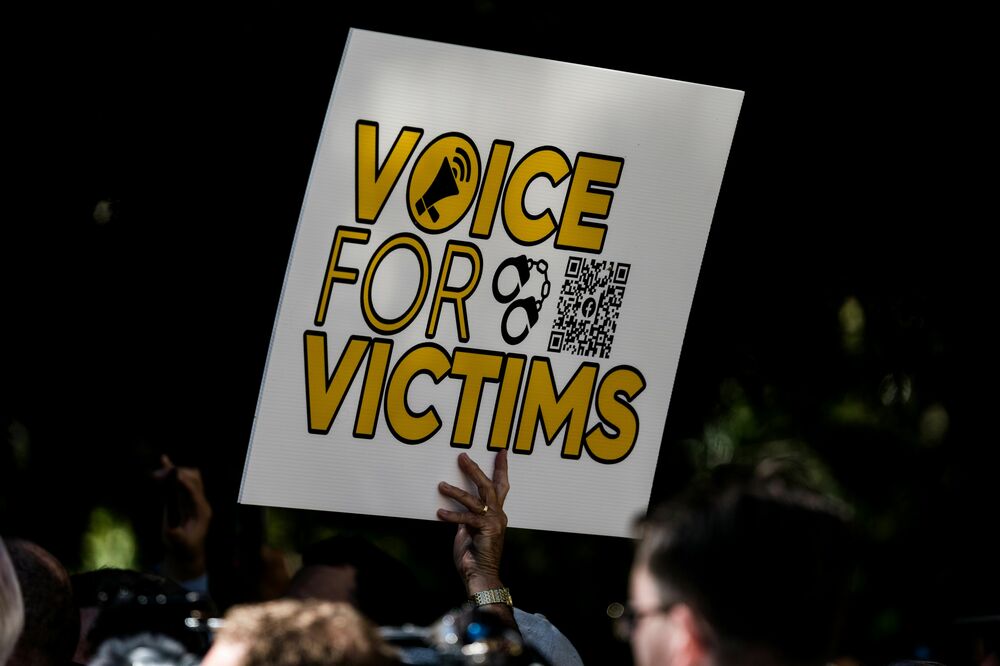
ドキュメンタリー作家の坂上香さんのドキュメンタリー作品「プリズン・サークル」でも、この修復的司法の試みが撮られているとして話題になった。カメラが入った舞台は官民協働の新しい刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」。受刑者同士の対話をベースに犯罪の原因を見つめ、更生を促す「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」というプログラムが取り入れられている。[ii]比較的軽微な罪が多いとはいえ、プログラムの実践を通じてそれぞれが自らの加害と向き合う姿、入り組んだ生い立ちや、加害者自身も時として何かの被害者であるという加害と被害の分かち難さなどをも映し出していた。
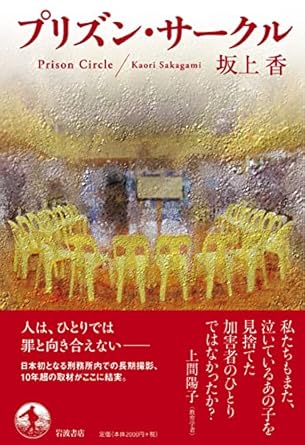
日本財団の再犯防止プロジェクト
官民連携の勉強会を立ち上げ、日本でこの修復的司法のアプローチを司法の現場に広げようと奮闘する一人に日本財団公益事業部部長の福田英夫さんがいる。過去に再犯防止プロジェクトチームを率いた経験がある福田さんは、刑期を終えたあとの受刑者の社会復帰をスムーズで着実なものにするために、「働く」ことを軸に捉え、企業側に働きかけて受け入れ先を増やす「職親プロジェクト」に長年携わってきた。いわば企業と受刑者のマッチングシステムだが、出所した後に再び社会で生活基盤を整えて生きていこうとしても、そこに高いハードルが立ちはだかることが少なくない。再犯を犯して刑務所に戻る人が多いことも指摘されてきたためだ。再発防止を実質的なものとするためにも、就労支援のみならず、さらにその先へ、という思いが強くあるという。

「日本では高齢者や障害者を含め、50%近い再犯率の高さが問題になっていますが、背景には加害者の更生プログラムが従来的なものに限られているといった問題もあります。そこで、加害者と被害者の対話を可能にする取り組みを模索しながら、被害者支援も加害者の更生のあり方も充実したものへ変えていきたい。
例えば現在、加害者と被害者のコミュニケーションは刑務官を通じてしかできないのですが、刑務官の教育プログラムを充実させることで、まずは刑務官と加害者の関係に変化がもたらされ、加害者の実質的な更生につなげられるかもしれない。加害者と被害者の直接の対話のみならず、間接的な働きかけも含めた様々な可能性があると思っています」
開放型刑務所、修復的司法--「北欧の実践に学びたい」
参考になるのが北欧の事例だ。修復的司法の考え方を取り入れたノルウェーでは、6~7割と高止まりしていた再犯率が約20%まで下がったという。その中には、2010年頃から始まった受刑者の生活の自由度が高い開放型刑務所の取り組みも含まれている。そして福田さんは現在、開放型刑務所の日本での実現に向けた研究会を重ねている。
「北欧にならって日本でもソフト面、ハード面の双方の改革が必要でしょう。日本では今年の6月から明治以来の懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑という新たな刑が創設されました。これは受刑者の更生と社会復帰のあり方を再考する大きな見直しです。矯正についても従来の画一的な「作業」を課すというあり方から脱却して、受刑者の様々な背景、特性に合わせ、カウンセリングや教育も含めて充実させていこうという機運にあります。それが結果的に再犯を防ぎ、被害者を減らすことにもつながっていく」
2023年10月から、日本全国の刑務所ではすでに「オープンダイアローグ(開かれた対話)」の手法を取り入れた実践が始まっている。[iii]オープンダイアローグとは、もともとはフィンランドのラップランド地方にある病院で行われていた、統合失調症患者のケアの技法だ。患者と家族、専門家チームがチームとなり、患者の声に耳を傾ける「開かれた対話」を実践するというシンプルなものだが、この実践によって患者の精神病が回復に向かい、発症率の低下が見られたという(オープンダイアローグという静かなる革命 | 斎藤 環 | 文藝春秋PLUS)。
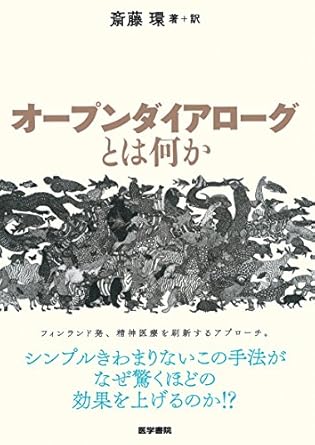
受刑者が自身の罪を客観的に見つめ直すために、刑務所でもこの技法が応用され始めたのだ。そこでは刑務官が受刑者の声を対等な立場で聞き、更生への意欲を高めることが目指されている。
「被害者のニーズに合った賠償」を追求する ICC「被害者信託基金(TFV)」の取り組み
福田さんがまず目指すのは、加害者の更生のあり方をアップデートするために心理士や刑務官といった、加害者と被害者を取り巻く人々の教育を充実させることだ。そのために近年、ノルウェーやスウェーデンといった北欧の国々に学び、協働の教育プログラムを模索してきた。さらに今回、ICCにおける修復的司法の実践にも学び、協働できるところがあるのではないか、「日本にも持ち帰れるものがあるのではないか」と視察に訪れたのだ。
ICCのセッション2日目の「被害者信託基金(TFV)」というファンドの取り組みは「被害者支援の観点からも学ぶところが多かった」と福田さんも言う。#前篇で、このファンドは支払い能力がないことの多い被告人の肩代わりをし、膨大な数に及ぶ被害者に賠償を可能にし、損害回復を目指して創設された取り組みであることに触れたが、「賠償は被害者のニーズに合ったものでなければならない。彼らに起きたことが今後再び起きることがないよう、(犯罪で被害を受けた家族の構成員の)世代を超えた被害をも含む賠償でなければならない」とのメッセージがTFVの職員からは語られた。被害者の救済が何より中心にあるのだ。
では「被害者のニーズに合った賠償」とはどのようなものだろうか。どの範囲までを損害と捉えて賠償でカバーされるのだろうか? TFVの賠償プログラムが実施された具体的な事例をここで一つ見てみたいが、興味深いのは物理的被害のみならず、トラウマに配慮した心理的被害からの回復、尊厳の回復も大切なものとして捉えられていたことだ。
賠償総額85億円のウガンダのオングウェン事件
ウガンダの元反政府勢力「神の抵抗軍(LRA)」の元司令官のドミニク・オングウェンに対し、ICCは戦争犯罪と人道に対する犯罪で2021年2月、61件の有罪判決を下した。強姦や殺人、子どもの誘拐などその犯罪は多岐にわたり、被害者数は約5万人。2024年2月、総額5240万ユーロ(約85億円)の賠償が命じられ、これはICC史上最大の賠償命令となったが、オングウェンに支払い能力がないと判断され、裁判所はTFVに賠償金の支払いを補填するよう要請した。
賠償には、一人当たり750ユーロの賠償金支払いと、医療的・心理的支援、さらに破壊された社会・経済の修復や再建までもが含まれる。なお、賠償命令までかなりの時間がかかることから、TFVは賠償とは別に捜査地域に対して独自の被害者支援を行う役割がある。ウガンダにおいては、目と鼻を失った女性が顔を元に戻すための再建手術や、性暴力によって生まれた子どもたちの教育支援、トラウマケアなどが行われているという。
被害が長期で被害者数も膨大であるため、十分ではないとの批判も一方であるようだが、理念として賠償内容が以下の(1)~(5)まで目指されていることには、戦争犯罪やジェノサイドも想定されているというICCに特殊な事情があるとはいえ驚かされた。
(1)心理的支援および医療的支援、(2)教育支援及び収入を生み出すための経済活動の支援、(3)建物の建設または修復、記憶の承継や追悼の活動、(4)コミュニティにおける平和構築および紛争解決の取り組み、(5)損失や被害の認識のサポート(主体性を取り戻せるようにするため)

なお、「修復的司法」の文脈でICCの賠償システムを紹介してきたが、「修復的ではなく賠償的正義に基づいていなければならない」とTFVのスタッフが話していたことも付け加えておきたい。共感をもって被害者の声が聞かれるだけではなく、実質的な救済が得られるように尽力しなければならない。より根源的な被害回復を希求する姿勢が「賠償的正義」という言葉で表現されている。
これは、越智萌さんの『だれが戦争の後片付けをするのか』で「不正を永続させ犯罪の温床となった社会状況を根本的に変えてしまうことを目指す「変革的アプローチ」に位置するものなのかもしれない。「ICCはいま、その変革的正義を実践に移そうとしている」と記述されている[iv]。
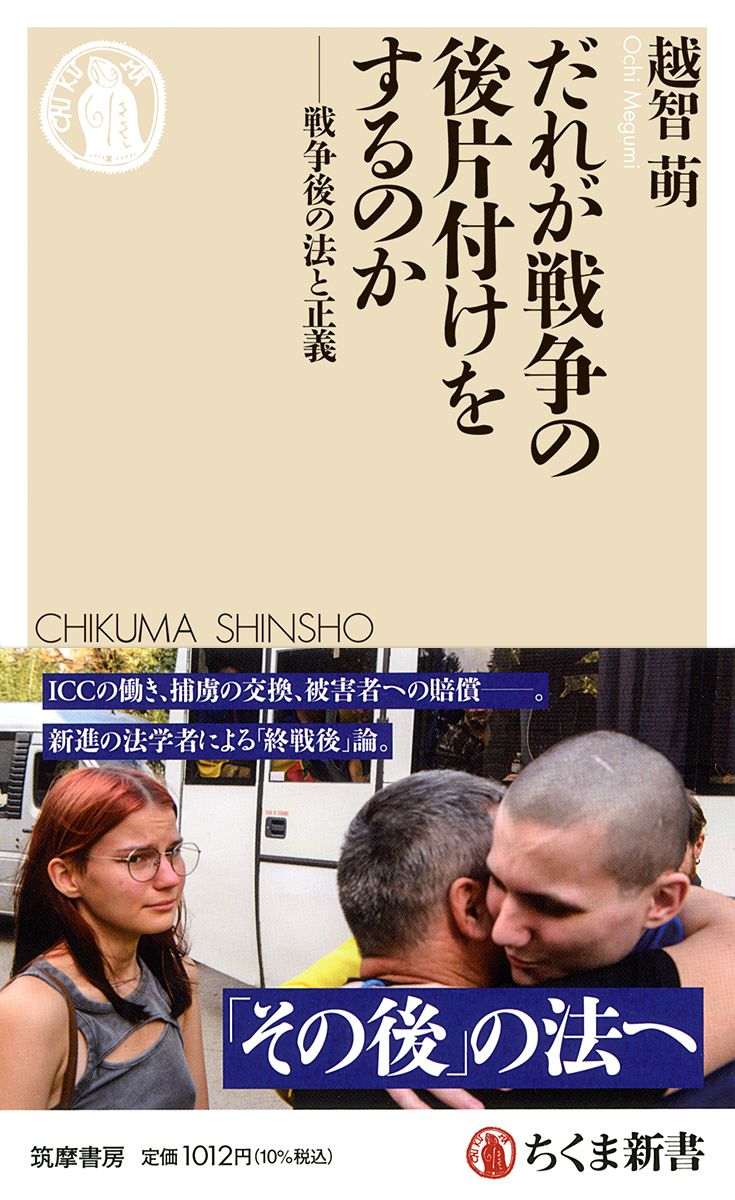
受刑者の更生、社会復帰――変革期にある日本が学べるものとは
ここで改めて日本財団の福田さんの視点に戻ってみたい。日本が学べることは何だろうか。
「ICCは国際的に重大な犯罪を扱う裁判所ということもあって、日本にそのまま応用するというのは難しいかもしれない。ただ、証人保護にあたっている心理士スタッフの人にしても、被害者信託基金のスタッフの人たちにしても、トラウマを負った証人や被害者の心のケアを非常に重視していた。被害者救済を中心に据えたアプローチ、これまで様々な事案を通じて培われてきたソフトスキルというものは、日本で矯正にあたる心理士や刑務官にとって学びになるところが大きいのではないか。教育的なプログラムで何か協働を模索していくことができれば」と未来への手ごたえを感じているようだ。
ロシア・ウクライナ戦争とイスラエル・パレスチナの紛争という二つの歴史的な戦争犯罪に直面し、今後戦争処理という難題にあたらなければならない国際刑事裁判所(ICC)。設立から20年以上の時を経て着実に積み上げられてきた被害者救済中心の正義の実践から、受刑者の更生や社会復帰が心のケアへも目を向けたものへ大きく舵を切ろうとしている日本が学べるところは大きいのではないだろうか。
[i] 「「犯罪という現象」から学ぶことのできる社会のあり方を目指して―Restorative Justice(RJ)(回復的・修復的司法)とは何か」 – 立命館大学人間科学研究所
[ii] 映画『プリズン・サークル』公式ホームページ
[iii] 001437235.pdf
[iv] 医療人類学者の大竹裕子さん『いきることでなぜ、魂の傷が癒されるのか 紛争地ルワンダに暮らす人びとの民族誌』(白水社)では、ジェノサイドからルワンダがどう回復したか、国際支援の枠組みからもこぼれ落ちてしまった人々に光をあてて書かれる。



















