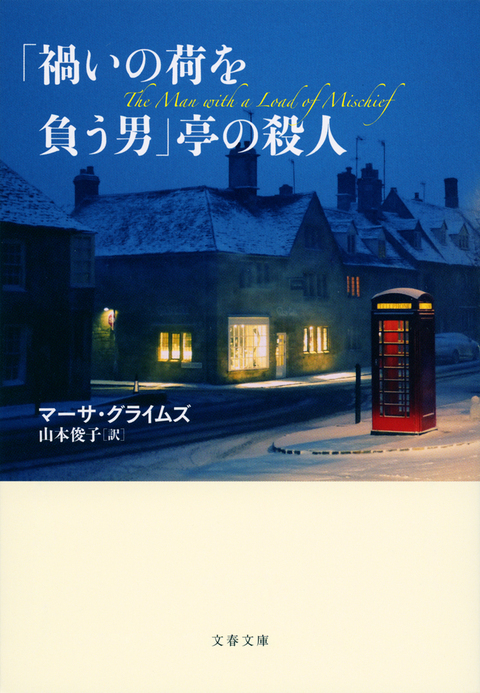今、アングロファイルという言葉を使った。そうなのである。マーサ・グライムズはイギリス人ではなく、生粋のアメリカ人なのだ。生年は公表されていないが(一説には一九三一年生まれ)、彼女の生地はペンシルヴァニア州ピッツバーグで、メリーランド大学で英語を専攻、作家デビューする前はメリーランド州のモンゴメリー・カレッジで英語教授として働いていた。もちろんイギリス古典探偵小説の熱烈なファンであり、自身がミステリー作家としてデビューするにあたってはそうした世界を使うことを選択したのである。本書の第十一章に牧師のデンジル・スミスが古い旅館やパブが使っている奇妙な店名や看板のいわれについて解説する場面がある。これらの興味深い知識は事実に基づいている。このシリーズの題名はそうした旅館やパブから採られているが、それらはすべて実在するものなのだ。今風の言葉で言うと、イギリスおたく、だったわけですね。
こうした英国ファンの代表格はジョン・ディクスン・カーだ。彼は好きが昂じてしばらくかの地に移住していたほどであり、心情的には彼をこっそり〈イギリス作家〉に仲間入りさせているファンも多いのではないだろうか(でも、結局はアメリカに帰っちゃったんだけど)。それ以外にもマリアン・バブスン(『殺人ツアーにご招待』扶桑社ミステリー)、エリザベス・ジョージ(『そしてボビーは死んだ』新潮文庫)、ポーラ・ゴズリング(『ブラックウォーター湾の殺人』ハヤカワ・ミステリ)、ケイト・チャールズ(『災いを秘めた酒』創元推理文庫)、ちょっと遅れてC・C・ベニスン(『バッキンガム宮殿の殺人』ハヤカワ・ミステリ文庫)といった作家が一九八〇年代から九〇年代にかけてイギリスを舞台にしたミステリーを発表し始めたアングロファイルである(最近〈英国王妃の事件ファイル〉シリーズで人気のあるリース・ボウエンは逆にイギリスからアメリカへの移住組)。
カナダのベニスンは別として、グライムズ以外のアメリカ出身アングロファイル作家たちには共通点がある。カーのようにイギリスへ移住するか、ジョージのように現地の文化を研究して、祖国と同等の評価をイギリスでも獲得したことだ。グライムズはそうではなく、あくまでメリーランド州の作家として活動を続け、アメリカでベストセラー作家になった。一九八七年に発表した第九作の『「五つの鐘と貝殻骨」亭の奇縁』で彼女の作品は初めてニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストに入り、以来連続でランクインし続けた。皮肉な物言いになるが「アメリカ人の好むイギリス・ミステリー」の書き手としての地位を確立したのである。アメリカ人のマーフィーがコージーの代表格としてグライムズを認めているのにも、そうした事情が反映されているはずだ。