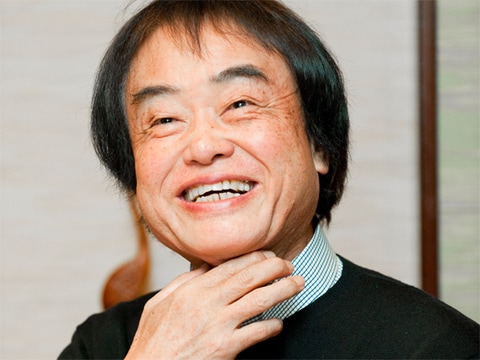そんなわけで、とにかく、「丸かじり」=カツカレー説については、おおかたのご了解を得たものとして、話を先に進めさせていただきたい。ちなみに、このオマケの小文を書いている二〇一五年二月現在、「丸かじり」の雑誌初出である「週刊朝日」連載の『あれも食いたい これも食いたい』のレイアウトは、「大」の絵が本文の前に置かれていて、なるほど、これなら読み進める順番を迷いようもあるまい。しかし、それは、あたかも「カツが別皿添え」のカツカレーを出されたような気もしないではない。僕は、断固として、「大」の絵が文章中に挿し込まれ、カツとカレーが渾然一体となった単行本版および文庫版のレイアウトを強く支持するものである。
さて、カツカレーの正しい食べ方について――『ホルモン焼きの丸かじり』では、さんざん「ああでもない、こうでもない」と理屈をこねたすえに〈カツカレーなんて、もともとどっちだっていいもんなんですから〉で終わってしまう。ひどい話である。
しかし、我々(いつのまにか、あなたも仲間だ)は、「丸かじり」をそんな文言でまとめてしまうわけにはいかない。
究極のカレー=文章については、いまさら僕ごときがモノを言うまでもあるまい。「丸かじり」シリーズの文庫版既刊の解説だけでも、『東海林さだお論集』が組めるだろう。
ならば、こちらは、至高のカツ=挿画について、いささかの感想を述べさせていただこうではないか。
「丸かじり」の主役は誰なのだろう。
ときどき考える。
文章の語り手は〈ぼく〉であり、その〈ぼく〉は明らかに東海林さだおさんである。
しかし、最も目立つ、アイキャッチーな存在として描かれる「大」の挿画に出てくるのは、東海林さんではない。ごくまれに――ヘンな食材や調理法の実践系エッセイの回などで、東海林さんらしき人物が描かれることはある(いや、それもまた「ショージくん」という虚構のキャラクターかもしれない)ものの、圧倒的多数の回で「大」の絵に描き出されるのは、一回こっきりの人物なのだ。
試しに、本書のページをまたパラパラとめくって本文に戻っていただきたい(読者にものをやらせることの多い解説だナ)。各編に一人ずつ、いや「中」や「小」も含めれば何人も、ほんとうにたくさんのひとが描き出されている。しかも、みんな……あなたのまわりにいるでしょ? 見たことあるでしょ? 電車で一緒になったでしょ? すれ違ったでしょ? そういう連中ばかりなのである。
心底、すごいなあ、と思う。一人ひとりの人物に、そのひとが生きてきた人生や、暮らしている日常が、しっかりと息づいている。だからこそ、そこに描かれた「食」に、厚みと温もりがある。
しかも(ここが肝心)、それを東海林さんは毎週毎週毎週毎週……この小文を書いている時点の『週刊朝日』最新号で、連載回数は千三百五十一回に達しているから、最低でも千三百五十一人の、いや「中」や「小」も含めて二千人、もしかしたら三千人近くの人物を描き出し、しかも、彼らを繰り返し登場させることはない。一期一会。いちげんさん。これがもし、一人の主人公をつくって、彼を毎回「大」の挿画に登場させるスタイルだったら、きっと毎週の作品を仕上げる負担はかなり減じられるだろう。だが、東海林さんは、まるで決して献立がダブらない日替わり定食を出しつづける食堂のように、バラエティとリアリティに充ち満ちた「ひと」と「食」の光景を描きつづけるのだ。
その潔さに圧倒され、畏れながら、思う。
いったい東海林さんの頭の中には、何千人、何万人の「ひと」がいるのだろう――。
その何千人、何万人が、それぞれ似合いの料理や食材を丸かじりする光景は、どれほど壮観なものだろう――。
たとえば、「丸かじり」シリーズ全編の、「大」だけでもいい、挿画を集めた画集ができたなら、それは間違いなく「昭和」の終わりから「平成」にかけての「食」の曼荼羅になるのではないか――。