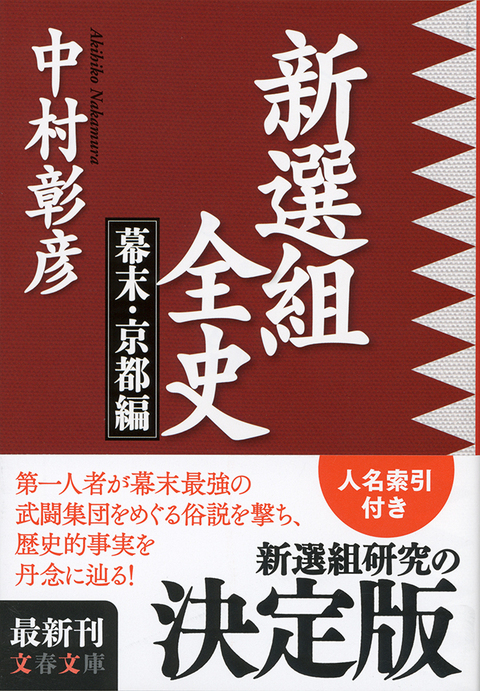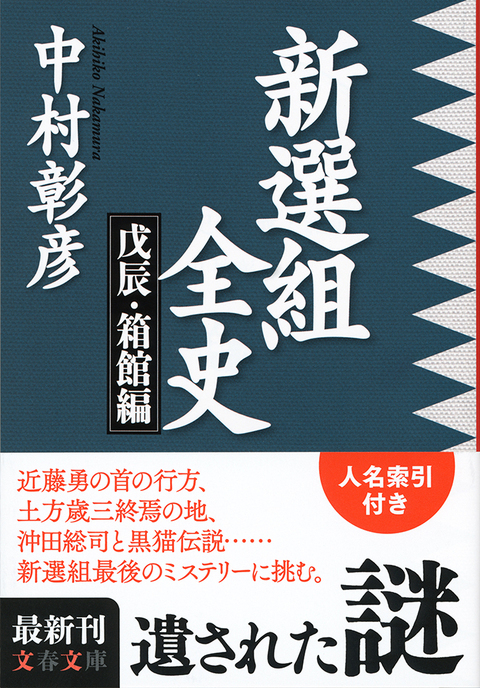第五は二者択一的なものの見方の画一性にも正面から挑戦している点だ。たとえば「官軍」という表現を極力避けているのは氏が佐幕派を決して賊軍と勧善懲悪的に認定していないからである。
氏には『松平容保(まつだいらかたもり)は朝敵にあらず』を嚆矢(こうし)に『保科正之言行録』『白虎隊』などの優れたノンフィクションがあるが、この頑固なまでの反権力の姿勢は一連の作品に繋(つな)がり、「埋もれた人々」に焦点を当て直す態度に直結している。だから氏は小説の主人公にしては英雄になりにくい男たち、むしろ英雄たちの陰に隠れて活躍した男たちのロマンを好んで描くのだ。かといって主人公であっても悪いところは鋭角的に悪いと批判する。
かくして読者は新選組がいったん甲陽鎮撫隊で壊滅したあと永倉新八らとの喧嘩(けんか)別れで「解散」した事実を識別し、再び復活して宇都宮、会津で烈(はげ)しくもめざましく戦ったこと。さらに蝦夷(えぞ)地政府の樹立をめざした榎本武揚(えのもとたけあき)軍に加わったのは厳密にいえば「箱館(はこだて)新選組」であったという歴史的沿革(これぞ新選組全史だ)を俯瞰(ふかん)できる。
本書の第六の特徴は中村彰彦氏の「歴史とは何か」というアプローチの方法が典型的に提示されている点である。
それは近藤、土方、沖田、山南、伊東甲子太郎(いとうかしたろう)らばかりに過去の小説のスポットが集中してきたのに比べ、それ以外の薄幸な隊士たちの運命をも逐一調べ上げ喜怒哀楽を淡々と叙している姿勢から感得できる。
箱館で土方歳三戦死のあと便宜的に新選組の責任者になった相馬主計(そうまかずえ)はそのために島流しになり、やがて許されて東京に戻るも切腹して果てる(この実話を膨らませたのが中村の小説家としてのデビュー作『明治新選組』)。
こういう悲劇の「戦後譚(たん)」などは中村彰彦氏の地道な発掘作業によって初めて知った読者も多いだろう。さらには「その後」を生き延びて隊士を弔(とむら)った、たとえば島田魁(しまださきがけ/彼を主人公とする『いつの日か還る』を後に中村氏は書くのだが)の後半生の悲劇まで詳細に辿り、疾風怒濤(どとう)の時代に運命を翻弄(ほんろう)された日本武士の様々な生き様をたっぷりと考えさせてくれる。
本書は著者畢生(ひっせい)の力作であり、新選組研究の必読文献である。