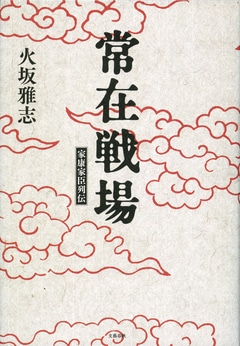今年、平成二十七年二月二十六日、NHK大河ドラマの原作となった『天地人』で知られる火坂雅志さんが、急性膵炎のために亡くなった。
まだ、五十八歳の若さであったというのに――。
体調が芳しくないとは聞いていたが、それも持ち直し、だいぶ元気になられたと聞いていたので、この急逝は、私にとって衝撃といってよかった。
それを思うにつけ、私の中でまぼろしのように浮かび上ってくる場面がある。
あれは昨年の秋頃のことであろうか。
ちょうど元日航ホテルのあった銀座八丁目のあたりを歩いていると、向こうからいつものように着流しに懐手の火坂さんがやってくる。
私が「やあ――」
と久闊を叙して、
「このあいだは安部(龍太郎)さんが直木賞をとったから、今度は火坂さんだね」
というと、
「僕には『天地人』があるからいいよ」
と、熱血漢の火坂さんにも似合わぬ、余りにも謙虚な答えが返ってきたので、何やら不思議な思いにかられたのを記憶している。
あれは何だったのだろうか。実際、火坂さんは、安部さんの受賞を心の底から我が事のように喜び、直木賞の二次会で熱い祝辞を述べている。
私は何か奥歯にもののはさまったような違和感を覚えたが、結局、それが最後の会話となってしまった。
火坂さんは、本名中川雅志。新潟市出身で、早稲田大学在学中、「歴史文学ロマンの会」を主宰、あまりの熱心さに、永井路子さんの家に押しかけたという挿話を聞いている。
同学を卒業後、新人物往来社に勤務、「歴史読本」の編集者を経て、昭和六十三年、歌人西行を拳法家としてとらえた異色の傑作『花月秘拳行』で作家デビュー。ところが当時は、そうした異色さが災いしたのであろうか。火坂さんの作品の持つ伝奇性には、鬼才山田風太郎の忍法帖のように、一抹の、いや、時にはそれ以上の歴史的根拠があるのだが、恐らく、ビジネスマン向けの歴史情報小説が跋扈している中、作品の持つロマネスクな面白さは、悔しくも評価されない嫌いがあった。
それでも彼は書き続けた。
さらには、刺客の兇刃を逃れた坂本竜馬が新政府の財源づくりのため、源義経が残した黄金を求めて蝦夷に赴く『竜馬復活』、川並衆の前野将右衛門にスポットを当てて、桶狭間急襲を新たな角度から描いた『信長の密使』、播磨の悪党伝説に材を得た陰の戦国史とでもいうべき『悪党伝説〈外法狩り〉』『同・信長狩り』『同・神君狩り』と続く三部等がある。
また文庫書き下ろし作品として『霧隠才蔵』や『柳生烈堂』等の連作長篇を、さらには幽玄妖美な世界に筆を遊ばせた短篇集『西行桜』や、火坂さんにとっての『妖星伝』(半村良)ともいうべき大河小説『神異伝』等、歴史にロマンを求めて彼の創作活動は続いた。
そして平成五年だった。PHP研究所から発刊されていた「歴史街道」の増刊として、歴史・時代小説の専門誌「小説歴史街道」を考えているのだが、誰か将来、有望な気鋭・新人はいないか、と編集長(当時)の小林成彦氏より打診を打けたのは――。
私は、即座に、安部龍太郎、東郷隆、中村隆資、火坂雅志、宮部みゆき、宮本昌孝の各氏の名を挙げた。この中で現在、中村さんだけが休筆中だが、その他の方々の活躍は、いまさら述べるまでもあるまい。
そして、同誌に作品を書きながら、皆よく遊ばせてもらった。飲みかつ歌い、その中で最も熱っぽく作家としての理想、将来の夢を語っていたのが、好漢、火坂雅志であった。
同誌は専門誌のむずかしさからやむなく休刊となるが、火坂さんが、いよいよブレイクを果たすのは、それからだった。
この実力派の真の力を世に喧伝するきっかけとなったのが、平成十一年に刊行された『全宗』であった。全宗とは秀吉の侍医であり、かつ参謀でもあった一種の怪人物である。豊臣政権の中枢にいて“医によって天下を取る”という、いわば〈賢〉と〈俗〉が何の矛盾もなく一体化した、戦国期の〈夢〉の象徴とでもいえる人物かもしれない。
そして、この大作を刊行して以来、火坂さんは、信長に〈商〉をもって天下を取らせた男、今井宗久を描く『覇商の門』や、第三の元寇を防ぐべく、大陸に渡った海の男の活躍を描く、『蒼き海狼』等を発表。
この頃から火坂作品の中で、確実に何かが変わった。
たとえていえば、それは、小高い丘の上に立って美しい風景を見るときに感じる、頬を打つ風のような、一陣の涼風が感じられるようになったのである。
こうした涼風は、以後、陸続と書き継がれる戦国小説――『黒衣の宰相』『黄金の華』『家康と権之丞』『虎の城』『沢彦』と続き、第十三回中山義秀文学賞を受賞した『天地人』で一つのピークを迎えることになるのである。
『天地人』の詳細については、文春文庫に収録されている同書の私の解説を参照していただくとして、この作品の画期的な点を挙げると次のようになる。
一つは、作者いわく、自分は、いままで故郷越後の人物を書かずにきたが、この作品ではじめて故郷と真正面に対峙することができたこと。
さらに、天下を取った男ではなく、“取らなかった男たちが”代わりに何を成し得たか、ということがテーマとなっている点――この小説の読みどころは、颯爽たる直江状のくだりもさることながら、関ヶ原合戦後の兼続が一見、歴史の表舞台から消えたときからがポイントであり、米沢三十万石に減封されるも、あくまでも“経済と義との両立”というテーマにのっとった“政治そのもの”の実現に辣腕をふるうことになる、正にそのくだりにある。
三つ目に、主君であり師でもあった故上杉謙信の「義」より高い次元で止揚するもの、すなわち、「愛」=民愛、慈愛がテーマとなっていること。
そして四番目に、この作品から作者の新しいテーマが生まれたこと。それは、利休切腹前後に〈中央集権〉派と〈地方分権〉派の対立があったと記しているように――〈地方の誇り〉である。これが、本書に続く、伊達政宗を描いた『臥竜の天』へとつながっていく。
題名は、天下をうかがって低く地を這う竜、すなわち、天下を取れなかった政宗のことを意味している。が、その代わりに彼が成し得たのは、秀吉の政治的矛盾を見抜き、家康の恫喝をすり抜け、乱世をしたたかに生き抜く術に他ならない。
戦国期を舞台に、いまと二重写しになっている活力ある〈地方の時代〉を描くこと。これは換言すれば、〈利〉の政治から〈義〉の政治への転換であり、火坂さんは閉塞的な現状だからこそ敢えて〈理想〉を描く、という姿勢をここから見せはじめた。
唐突だが、同じ北の出身者として、火坂さんの目には、東日本大震災はどう映っただろうか――復興、復興と掛け声だけは大きいが、現政権や東電のやり方に〈義〉はあるか? 〈慈愛〉はあるか? そんなことも話してもみたかったが、もはや叶わぬこととなってしまった。
火坂さんは、この後も、竹中半兵衛の〈義〉=利を超えた「できる限り血を流さぬいくさ」の理想が黒田官兵衛へ受け継がれるさまを描いた『軍師の門』や、権謀術数激しき乱世にあって己の〈義〉を引き裂かれた安国寺恵瓊の生涯を描いた『墨染の鎧』等を発表。火坂さんの作品は、戦国小説に新生面を招きつつあったのだ。
そして、本書『常在戦場』は、平成二十五年三月、文藝春秋から刊行された短篇集で、単行本時のサブタイトルに“家康家臣列伝”とあるように、いかにも火坂さんらしく、直接、家康を描かず、その周囲の人々、いわば脇役を主役に据えることで、家康をあぶり出そうという趣向の一巻である。
表題作は、有名な徳川秀忠の関ヶ原遅参が発端である。本多正信は秀忠と自らの保身のために、その責任を、牧野、大久保の二人に転嫁する。が、ここからが家康の眼力の凄いところで、出奔した牧野忠成は只者ではなかったはずだと判断した時点で、ある密命を与え、牧野家を再興する手柄働きをさせてしまう。その密命はぜひ作品を読んで味わっていただきたい。
この他にも、鳥居元忠と竹千代(後の家康)の交誼を思いっきり贅肉を削り落とした文章で描き、シンプルな感動を呼ぶ「ワタリ」、天下に名高い井伊の赤備え誕生の背後にある、男姿となって井伊直虎と名乗り、苦難の道を歩く姫を描いた「井伊の虎」、さらに「毒まんじゅう」は、築山殿一件の物語と並んで、その行動についてとかく謎の多かった石川数正を、さまざまな資料の踏査や作者の推理によって、はじめて整合性をもってとらえた作品ではないのか。
そして、「梅一輪」は、大久保長安事件のてんまつと、かつ大久保忠隣の声なき抵抗の物語であり、「馬上の局」は、家康に“惚れてしまった”阿茶の自ら致し方なし、と嘆息をついて歩む人生を描いている。
また正確には家臣団ではないが、家康と縁を結んだおかげで次々と夢を実現させていく角倉了以の姿を描く「川天狗」も面白い。
さて、この解説の冒頭で私は火坂さんが、
「僕には『天地人』があるからいいよ」
といっていた旨を記した。
一方、『天地人』が大河ドラマの原作となったとき、私は「新刊展望」で火坂さんと対談をした。そのとき火坂さんは、いままで自分は時代小説の読者には知られていたが、これで一般読者に認知された。これからは安心して時代小説を書いていける、と語っていた。
そう、“これから”――これからが正に作家として脂が乗って来るところだったのに。
私には、火坂さんの二つのことばが、何やら対になった奇妙な符号のように思えてならない。合掌あるのみ――。