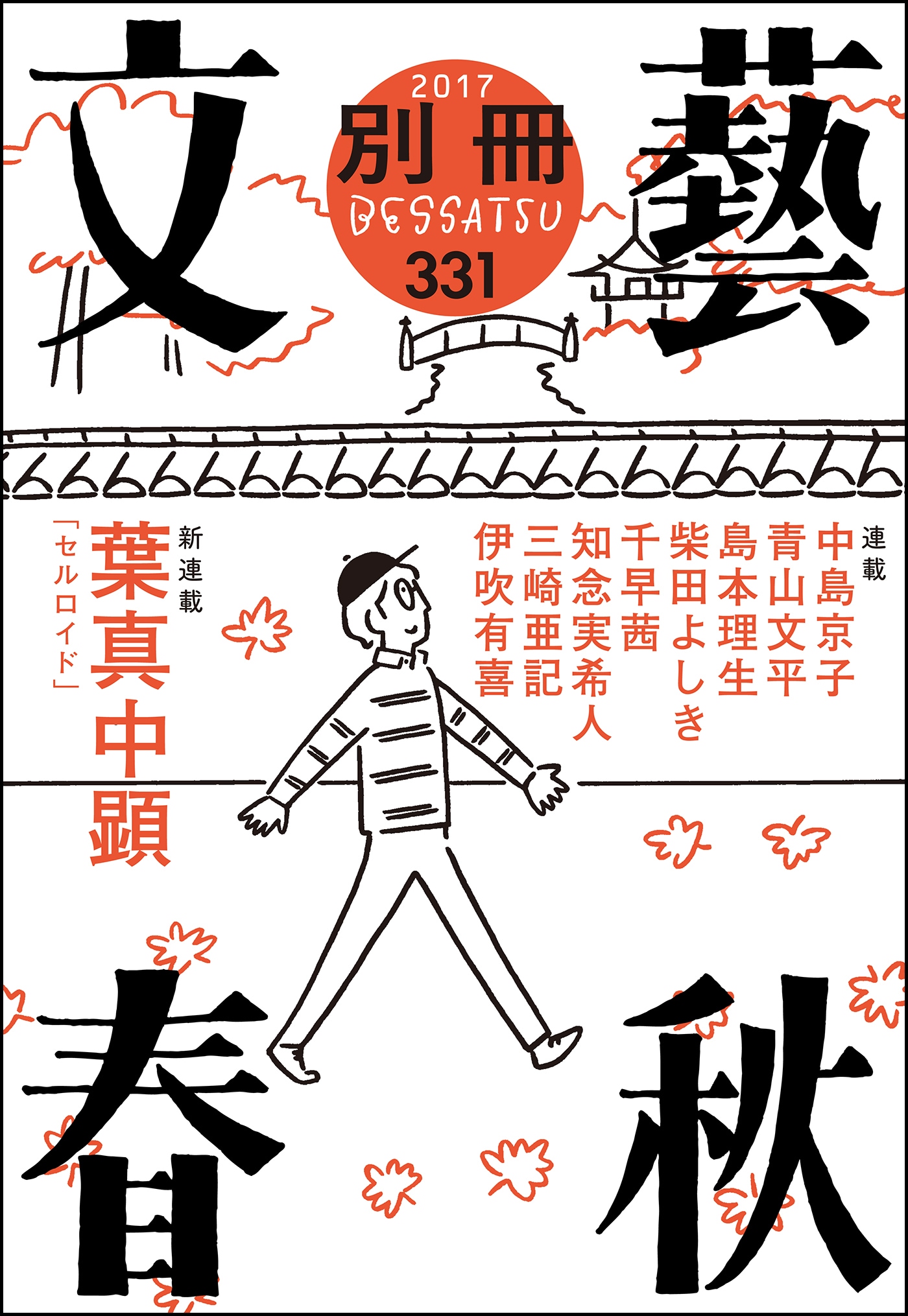
わたしは喜和子さんを促してエレベーターに乗り、三階まで上った。
三階の廊下には、明治時代に撮影された図書館内部の写真が展示されていて、この建物の歴史がわかる。
外に面した部分が全面ガラス張りの開放的な廊下部分は、古い建物の外壁を守る意味合いもあって改装のときに付け足したものなので、廊下の展示を見て歩く利用者は、古い建物の三階の外壁のすぐ横という、かつては宙に浮く能力でもなければ近づくことのできなかった場所を歩いていることになるのだった。
「こっちに閲覧室があったんだけど。あらまあ、こんなにきれいになっちゃって、なんだか違うねえ。新聞なんか、読めたと思うけど、ほんとにきれいになっちゃって」
喜和子さんはそう繰り返した。
ひょっとして懐かしい想い出が壊されてしまいそうで不満なのだろうかと気になって、部屋から先に出てしまった彼女を追いかけると、大きなドアの前で立ち止まり、ドアにつけられた銅板のプレートをしきりにさすっている。
「これは変わらないね」
プレートには、
「おす登あく」
と、書いてあった。
「おすとあく? 押すと開く? そのまんま? なんですかね、これ」
「これはずっと前からこうよ。ほんとにずっと前からこうよ。建物が建ったときから、このまんまだそうよ。明治の人は、押して開けるドアに慣れてなかったから、引き戸と間違えないように、こう書いてあるんだって」
そう言うと、喜和子さんは満足げに目を閉じた。以前に、古尾野(ふるおや)先生といっしょに湯島聖堂の大成殿に行ったときに、黒い柱に耳をつけて目を閉じたときのように。
「ほんと言うと、ちっさかったときのことは、あんまり覚えてないんだよね」
喜和子さんはしばらくすると目を開けた。
「だから、思い出そうとするとやっぱり、上京してこっちに住むようになってから、ときどき来てみた図書館のことになっちゃうわよね。だけど、ここ、古い図書館でさあ、しかも国会図書館の分室でしょ。来てる人もなんだか、役人くさい人が多かったのよ。男の人ばっかりでねえ。だから、来てもまっすぐ地下の食堂へ直行してたの」
「ミキヤさん?」
「美木屋さん。ぽってりしたカップで出てくるコーヒーが、わりにおいしかったの。だから、地下がなくなってしまったのは残念だわねえ」
それから喜和子さんは、部屋の中を順繰りに見てまわり、古い外壁に触っては、また感慨深げにその化粧煉瓦を撫でさすり、
「こう言っちゃなんだけど、こわいような建物だったわよ、いつだって」
と、いたずらっぽい表情になった。
「だけどさ、新しかったときもあったのよね。明治三十九年に建ったころはさ、そりゃ立派だっただろうねえ、こんだけの建物」
あたしが知る限りじゃ古いんだけど、と彼女はつけ加えて、それからわたしたちはしばらく図書館の中をうろついた。子ども図書館を訪ねるのは、わたしにはいつだって楽しかったし、喜和子さんは喜和子さんで気持ちを切り替えたのか、昔はどうだった、こうだったと言い募るのをやめにして、新しい建物を楽しみ始めた。


















