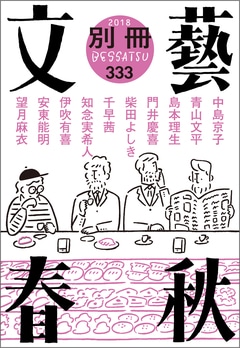「まちがいありません。わたくしは実際、提灯を持って縁側から床下へもぐりこんだのです。藁屋根の下にあたるところは、礎石までもが土にめりこんでいました。まわりは、“ありじごく”の巣のように・・・・・・」
「・・・・・・して?」
「え」
「原因はわかった。してその解決は如何。おぬしの言うのがまことなら、この家は、どうすれば元の扁平をとりもどすのじゃ」
父はなかば放心した顔で、そう聞き返した。非難ではない。純粋に金吾のこたえに、
――期待している。
そんな光がひとすじ瞳に浮いている。金吾は“あばら”骨のきしむような快感をおぼえつつも、
「それは」
ことばが出ぬまま、時間がすぎた。さっきまではどういうわけか、
(これなら、江戸の叔父さんも感心する)
などとまだ見たこともない人のよろこぶ顔まで見た気になったものだったが、いまはもう考えれば考えるほど自分が“ありじごく”に捕らわれたようだった。どうすればと言われても一から建てなおす金はもとよりないだろう。伝説上の巨人・大人弥五郎にたのんで片側だけ持ち上げてもらうわけにもいかない。
結局は、
「申し訳ありません」
頭をさげたら、のどの奧に、きゅうに込み上げるものがあった。
片頬のゆがむのが自分でもわかる。洟をすする音で感づいたのだろう、父はあわてて金吾の頭をごしごしとなでて、
「いや、まあ、よくやった」
ともあれ金吾は、そういう下級の武家にそだった。いっそ純粋な農家に生まれるほうが、暮らしむきも、心のありようも楽だったかもしれない。九歳になり、世子の行列を待つために腰曲輪の坂道へ、つまり二の丸よりも先の場所へ上がったのも、考えてみたら武士なのに人生最初の経験だった。粗相をしたら、
(お手討ち)
と、となりの大人のいましめを思い出して戦慄したとき、その当の大人が、
「来たぞい」
つぶやいたようだった。