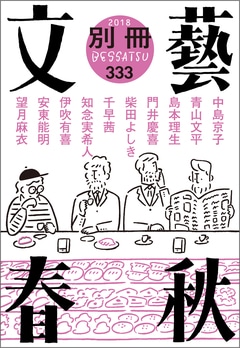前回までのあらすじ
将来、明治を代表する建築家となる辰野金吾もまだ三十歳になったばかり。三年に及ぶ官費留学で西洋をまわり、近代都市とはいかなるものかを学んで帰国した金吾は、いまだ江戸の面影を残す首都・東京をいかに新時代のそれに導くかという命題に胸を高鳴らせていた。さっそく工部省の役人兼工部大学校の教授という立場を得て意気揚々と改革に乗り出そうとした矢先、わずか一年で工部省廃省の知らせを突きつけられる。しかし、悲嘆に暮れる間もなく、金吾はあるヴィジョンを思い描く。それが民間の立場で都市計画に関わるという選択肢であり、建築家自ら会社を興すという発想であった。
2 藁葺きと瓦葺き
金吾は、はじめて達蔵に会った日のことをはっきりとおぼえている。
「記憶にないな」
と達蔵は言うのだが、どうだろう。それはまだ日本が徳川幕府のものだったころ、場所は、唐津のお城だった。
唐津城は、もともと満頭山という急な山をひらいて造られたため、本丸と二の丸のあいだに高さの差がある。本丸から二の丸へおりるには西向きの急な石段のほか、東側をぐるりとまわる腰曲輪と呼ばれる坂道があり、往来の用に資するところが大きかった。金吾はその日、その坂道のはしっこで、ほかの大人たちとともに一刻(二時間)も蹲踞の礼をとりつづけたのである。蹲踞というのは中腰くらいに両ひざを折り、こうべを垂れる姿勢だった。
何しろ九歳の子供だった。二時間どころか五分でも耐えがたいのだが、ちょっと身じろぎしただけで、右どなりの兄や父に、
「こらっ」
こわい顔で叱られる。うっかり、
「殿様は、まだ来んか」
などと聞こうものなら、こんどは左のほうの名も知らぬ、しかし自分たちと同程度の身分らしい中年の武士が、きれいに剃った月代をかがやかせて、
「藩主ではない。そのお世取りにあたられる小笠原図書頭長行様じゃ。このたびお世取りの身でありながら幕府の御奏者番に任じられ、大樹様(将軍)のお側ちかくでお世話することとなった故、江戸へお出張りになる。その晴れ晴れしい行列をわれらはお見送り申し上げるのじゃから、おぬし、粗相は禁物じゃぞい」