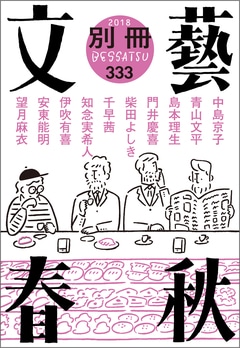「粥椀という名を付けてはいるが、スープやサラダボウルとしても使える。伝統工芸の作り手は時代に合わせて今、いろいろな模索をしているところです。ホームスパンもまたしかり」
大変でしょうね、と祖母が相槌を打つ。
「伝統工芸の品物って使う人が限られているし、後継者もいないでしょうし」
いないわけじゃない、と母が、祖母の言葉にかぶせるように言った。
「若い人たちもいるみたいよ。山崎工藝舎にも跡継ぎがいるし」
「継いでくれればうれしいが、縛るつもりはない。息子でさえ継がなかったものを、親戚だからといって押しつけるのも」
野菜、煮えたよ、と父がぶっきらぼうに言った。
「みんな取ってください。美緒、ねぎを除けるな」
急に話題が自分のことになり、小声で美緒は答える。
「ねぎ、苦手」
「あら、美緒ちゃん、そうなの? 冬ねぎは甘くておいしいのに」
「でも苦手だから」
美緒が除けたねぎを集め、祖母が自分の取り皿に入れた。しかし、すぐに祖父に向かって話し始めた。
「仮に美緒ちゃんがホームスパンの仕事をするとして、将来性みたいなものはあるんですか?」
「何をもって将来性と言うのか難しいですが、ありがたいことに、工房では二年先までの注文が埋まっています。ただ、新しい顧客については苦戦している。子や孫の代まで着られる布を作っても、今の時代はそこまで求めてはいない。良い物を長く愛でるより、安くて手軽なもので常に新しさを求めるスタイルのなかでは、我々の品は『高い』の一言で埋もれてしまう。そこにどうやって活路を見いだすか。好きというだけでは、やっていけない世界です」
「それなら、やっぱり学校だけはちゃんと出ておかないと」
ねえ、と祖母の視線が自分に向けられ、美緒はうつむく。
「夏に、学校の話をしているうちにけんかになって、お母さんが美緒ちゃんを叩いたって話、おばあちゃんも聞いた。暴力はいけない。でもね、お母さんの気持ちも少しは汲み取ってあげて」
「でも・・・・・・お母さん、私のこと、きらいだって。泣けばすむと思っているところがきらいって・・・・・・」
「それは」と言った母の言葉と「それはね」という祖母の言葉が重なった。祖母が軽く身を乗り出し、声を強める。
「美緒ちゃんのこういうところがきらいと言っただけで、美緒ちゃん自身をきらっているわけじゃない。好きだからこそ、直してほしいところをあげただけ」
「でも泣けばすむと・・・・・・思ってない」
祖父が小さくため息をつく。父が菜箸を軽く振った。
「食べながらこういう話はよしましょう。さっきから肉が煮えてる。固くなるから、みんな取って」
どうぞお先に、と母が祖父に勧めた。
いちばん小さな肉を祖父が取り、溶き卵にひたした。
「ほら、美緒」
父が菜箸で大きな肉を取ると、美緒の取り皿に入れた。
「お父さん、勝手に入れないで」
「自由に食べさせてやれ、広志」
父と祖父の視線が重なった。父が祖母にゆっくりと顔を向ける。
「お義母さんもどうぞ。あまり食べてないじゃないですか」
「美緒ちゃんのことでもう、胸がいっぱい」
「その話はあとにしませんか」
「そうやって、あなたたちが先延ばしにしてきたから、可哀想に、美緒ちゃんはとうとう留年することになったんじゃないの」