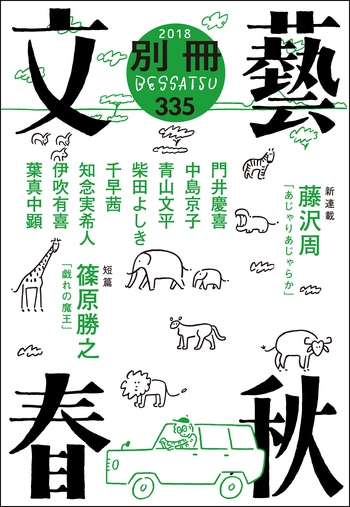古尾野先生は水割りの焼酎を入れた白い陶器のコップを、手の中でゆるゆる回しながら話した。
「結局、黒ヒョウはマンホールの蓋を開けて地下の下水道の通路に入り込んでてさ、大捕り物が演じられたわけだ、あの上野の、藝大のあたりでね。そのことは、古い人間なら誰でも知っている話なんだが、喜和ちゃんは大まじめで、だってあれは図書館に入り込んじゃってたいへんだったんじゃないのと、譲らないんだ。あの人、そういうところがあったよ。変なことを頭から信じててね、こっちがいくらまともな話で説得を試みても、いっこうに肯んじない。あのかたくなさはどこから来るんだろう。だって、黒ヒョウが図書館に迷い込んでみろよ。もっと話は大きくなって、それこそ誰だって知ってる事件として語り継がれてるはずじゃないか。しかしまあ、口を尖らして、頓珍漢なことを言うのが、なんというのかな、あの人のかわいらしさみたいなとこがあったよ」
年を取るとなんだ、涙もろくなるというのは本当だねとかなんとか言いながら、たしかに古尾野先生は背広のポケットからハンカチを取り出して、鼻の頭の先から陶器のコップに向かって垂れ落ちていきそうになっている鼻水を拭った。見るとたしかに赤い目をしていて、古尾野先生は泣いているのだった。
「まあ、慣れますけれどもね、年取れば。だけど、みんな死んじゃうからねえ。こんなとこ、こっちだって、もう長い事いてやるもんかと思うけどさ」
そう言って、老名誉教授が顔をぐしゃっとさせたので、わたしはそっとその背に手を回し、とんとんと軽く叩いて励ました。そんな仕草は、ふだんの自分からはあまり出てこないものだったけれど、喜和子さんだったらやりそうだった。彼女はそういう慰め方をするのが上手だった。だからせめて、真似でもいいからそうしてあげようと、そのときのわたしは思ったのだった。
「喜和ちゃんと出会ったのは広小路の飲み屋で、遅い時間に講義のある日や会合のあとの飲み会の流れで、その店にはときどき顔出したもんだよ」
古尾野先生は懐かしそうに喋り出した。
「まだバブルの余韻のようなものが街には残っていて、景気がいいというほどのこともないものの、ほら、円高差益還元とかなんとかでね、洋酒なんかがずいぶん安くてさ。店はそうだね、喜和ちゃんとそんなに変わらない年恰好のフユミさんという女の人がやってたんだ。居酒屋というか小料理屋というか、まあ、気取らない、入りやすい、ちっちゃな店だよ」
どういう経緯で当時まだ五十代だった喜和子さんがその店に勤めることになったかはわからないが、行きつけのその店にいる小柄なその女性に、古尾野先生はどうも一目惚れしたらしい。