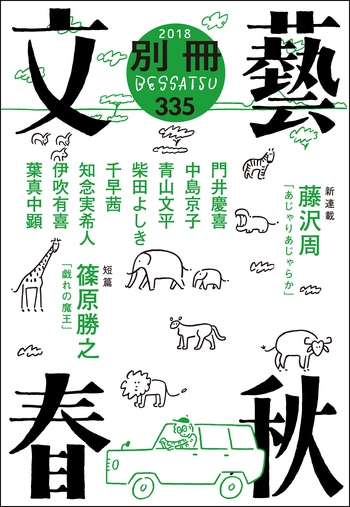ふいに胸がざわつく。サンダルをつっかけ、斜め前の廣瀬写真館へと走り、インターホンを押す。ガラス戸を叩く。中は暗く、全さんが出てくる気配はなかった。
そんな日々が一週間以上も続いていた。三木さんが運転する白いライトバンを二度ほど見かけたが、全さんの姿はなかった。
昨日と今日の区別がつかない、暑さと後悔でぐずぐずに溶けた日々。
このままぜんぶ消えてしまえばいい。浅い眠りの底に、意識を漂わせながら願う。ふいに、脳に電子音が響いた。反射的に携帯を掴む。耳にあててから、全さんが私の番号を知らないことも、携帯を持っていないことにも気付く。
「フジ? もしもし、フジ?」
女の子の声が耳に届く。急に起きたから心臓がばくばくしている。
落胆で痺れた頭をなんとか働かせて「菜月」と自分に言いきかせるように言う。
「やっとでた。フジ、メールしても返ってこないし。ねえ、元気にしてるの? あ、桃おいしかった。ありがとうね」
溌剌とした菜月の声を聞きながら、畳にできたよだれの染みを見つめる。私の頬にも痕がついているだろう。
「元気」と言えるほど元気でもないので、「ふつうに生きてるよ」と答える。菜月が愉快でたまらないというように笑う。面白いかな。この暑さの中、どうしてそんなに元気でいられるのだろう。
口にだしてしまったようで「えー、フジもしかしてエアコンつけてないの?」と驚かれる。キロクテキなモウショなんだよ、ネッチュウショウになっちゃうよ。菜月の言葉が、まるでテレビの向こう側から聞こえてくるみたいだ。機械的に相槌を打っていると、喋り続けていた菜月がちょっと黙った。
「ねえ」と、ささやくように言う。
「フジ、いまなにしてる?」
電話してると思いながら、「なにも」と答える。
「良かったあ。いまから、ちょっと会えない?」
やわらかく、けれど断る隙を与えない口調だった。なるほど、と思う。全さんにもこんな風に、そっと腕を絡ませるような話し方をすれば良かったのか。できはしないけど。
数日ぶりに笑いがもれた。
こめかみから顎にかけての汗を手でぬぐうと、「いいよ」と立ちあがった。
菜月が指定した白っぽいカフェは冷房が効きすぎていた。
パンケーキの店らしい。どのテーブルにも若い女の子たちがいて、彼女たちの前にはクリームやアイスやフルーツがこんもりと盛りつけられたパンケーキがある。店内はバターとシロップの甘い匂いに満ちていた。冷房が効いていなかったら、夏場は匂いだけで胸やけがしてしまうのかもしれない。