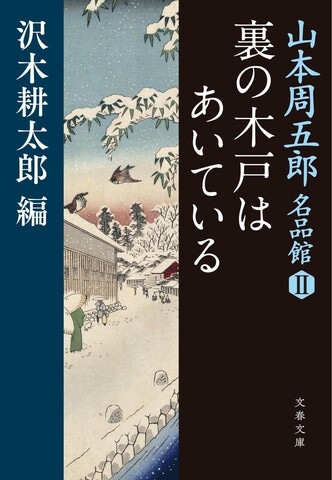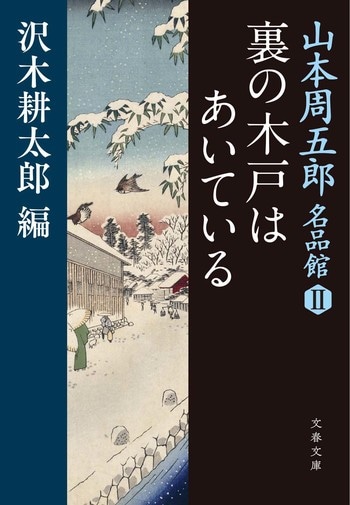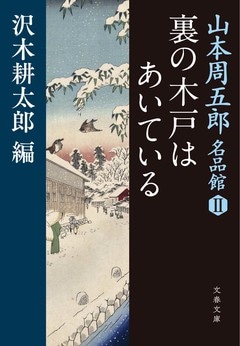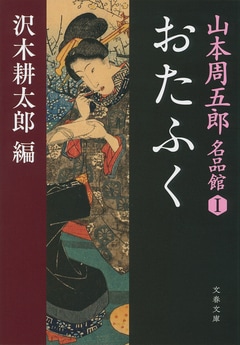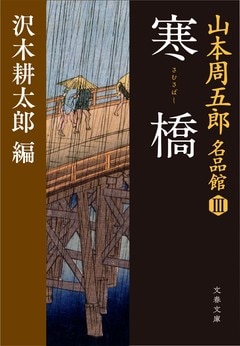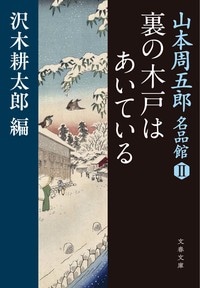
「橋の下」
武士と武士との果たし合いこそ、意地と意地とのぶつかり合い、意地の張り合いの結果かと思われる。
その意地の張り合いの行く末がどういうものになるか。
老いた「乞食」の過去の話が、果たし合いを前にした若い武士を根底から変える力を持つ。
――自分は恋しい女のために親友と果たし合いをすることになった。その親友を切り、恋しい女と二人で家と故郷を捨てた結果、体を壊し、いま「乞食」であるしかなくなってしまった……。
そのひとり語りをする老いた「乞食」の、悲しいけれど、決して哀れではない姿がくっきりと浮かんでくる。
まさに鮮やかな一幕劇のような物語である。
この「橋の下」の中には、山本周五郎の時代小説には珍しい台詞が出てくる。
《「七つじゃないか」と彼は云った、「捨て鐘をべつにして、たしかに七つだった、すると刻を間違えたのか」》
山本周五郎は、多くの場合、時刻の表現として「七つ」とか「六つ」とは言わず、現代風に四時頃とか六時過ぎとか書く。それは、いかにも時代劇らしい表現を用いたりせず、読者にもっとすっきり時間を頭に入れてもらい、物語を前に進めたいという思いがあったからではないかという気がする。
しかし、ここは武士の台詞として存在しているので「四時の鐘じゃないか」とは言わせられなかったのだろう。
「ひとでなし」
この作品の中心に、圧倒的な力を持って存在している言葉はひとつである。女が酔ったあげく、親切でやさしくしてくれる男に愛想づかしの台詞を吐く。それは、心にもない言葉に見えて、女の深いところにある思いが表出されているようにも見える微妙な台詞が続いたあげくの、ひとことだ。
《「そうよ、――あの人は悪党の人でなしよ、その代り自分も泥まみれになったわ」》
その台詞を聞いて、二人の男が強く心を動かされる。
女と結婚するため待ちつづけていた親切でやさしい男が打ちのめされ、それを物陰で聞いていたならず者の男がひとつの決意を固める。それによって、最後に、女の未来に微かな光がふたたび差してくることになるのだ。