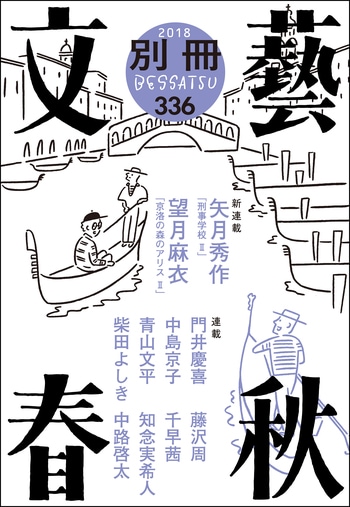それを聞いたのが、六歳から十五歳までの野宮での日々の、いつの頃だったのかは曖昧としている。覚えていたはずなのだが、気づいてみると模糊としていた。いまとなっては、いつ思い出せぬと気づいたのかすら思い出せない。なのに、なにを語ったかはくっきりとしている。
「能に関わる場を離れても、常に美しく居るということだ。美しく座して、立って、歩んで、語って、物を喰わねばならぬ。常の暮らしに要る所作のひとつひとつに、美しい形と、その形に至るまでの動きを想起する。稽古場と舞台だけで、能は舞えぬ。己れの常の暮らしまで舞台にして、舞台を常の暮らしにしなければならん」
保の言葉はすぐに正しいとわかったが、死を集めて流す野宮で日々を送る剛には正しすぎたし、美しすぎた。
「俺は昨日虫を喰った」
思わず保に言っていた。
「虫をも美しく喰えということか」
野宮にあって、いったい、どうやって美しく居ればよいのかという想いが、保の居る場処と己れの居る場処とのあいだに、あるはずのなかった裂け目を見させていた。暗に、己れの野宮での送り様を汚ないと責められている気もした。
「むろんだ」
けれど保は、その裂け目が見えぬようだった。
「当たり前ではないか」
即座に答えたその間に助けられて、剛は「美しく居る」を受け容れた。
ただし、能を美しく舞うためではなかった。
剛が能で目指していたのは鬼だった。跳んで跳んで跳びまくる能だった。美しい能ではない。
剛にとって「美しく居る」は能のためではなく、ひとえに常の暮らしを律するための文句だった。
能で生き延びて大人になることだけを念じてなんとか保っていた野宮の暮らしだった。日々のすべての時を能だけで埋めたいが、剛は霊ではない。生きようとする躰を持っている。喰い物を喰わねばならぬし、眠りもせねばならない。つまりは、喰い物を漁らねばならぬし、寝つくまでの時を遣り過ごさなければならぬということだ。そういう、能ではない時に、悪鬼が巣喰おうとする。こんな暮らしを重ねてなんになると嗤い、俺がなんとかしてやるよと歯茎を見せて能の時をばりばりと貪ろうとする。こんなことをやってるから、おまえはこんなところから離れられない、俺がきれいに喰らい尽くして思い切らせてやるさと、太い筋で盛り上がった背中を見せる。石舞台で跳んでいる剛は悪鬼を受けつけぬが、虫を喰う剛は悪鬼を引き止められない。悪鬼の後ろ姿の向こうに、突っかい棒を失ってどこまでも堕ちていく己れが透けて見えるが、やめろ、という叫びは掠れて声にならぬ。