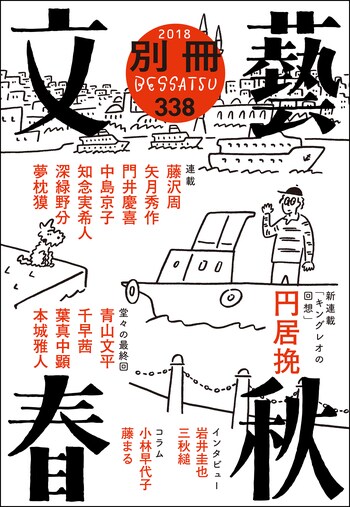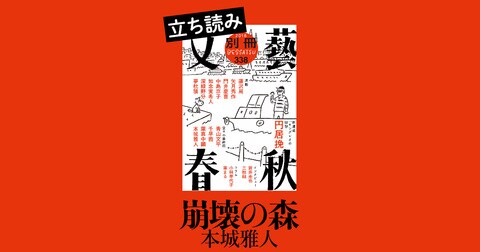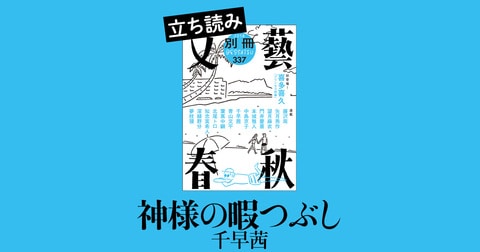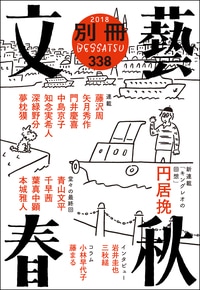
ぐつぐつ煮える鍋の向こうで缶チューハイに頬を染め、何事もなかったかのように喋り、笑い合う二人が大人に見えた。
私はきっと無理だ。今ここに、こたつの空いた場所に、全さんがかがむようにして入ってきたら。ぎょろりとした二重で私を見て、顔の半分でにやりと笑ったら。自分がどんな顔をするかわからない。なにもなかったことになんて、絶対にできないのは確かだった。
だから、変わったのだと思った。あのひとに出会う前とは。触れられた自分と触れられる前の自分は違う人間なのだと。少なくとも、誰にも見せない顔をあのひとには見せた。こんな風にいきなり捨てられたのに、再び目の前に現れたら私はまた溺れる。体の底にその確証があった。どんなに憎んでも軽蔑しても呪っても、私の体はあのひとを待っていた。
これこそが恋なのだと、半ば誇らしく、半ば絶望しながら、信じていた。
冬の夜は長い。菜月が終電で帰り、食べるのに飽きた里見が読書に戻っても、私は麺を入れたり雑炊にしたりしてだらだらと鍋をつついていた。部屋は静かで暖かく、手酌でしたたかに酔って目をとじると、凍てつく冬の夜でも夏の夢をみた。
揺れるゴーヤのカーテン、扇風機の唸り、蝉の声、しつこい蚊、スイカの赤と青くさい香り、がらんとした教室、窓の向こうの入道雲、ラジオから聞こえる高校野球、樹木の中の石段、桃の産毛、ビール瓶を傾ける筋ばった手。経験したいくつもの夏が混ざり合い、押し寄せてくる。裸足で畳を踏んで誰かがやってくる。黒い影がかかって、あのひとの声が聞こえる。